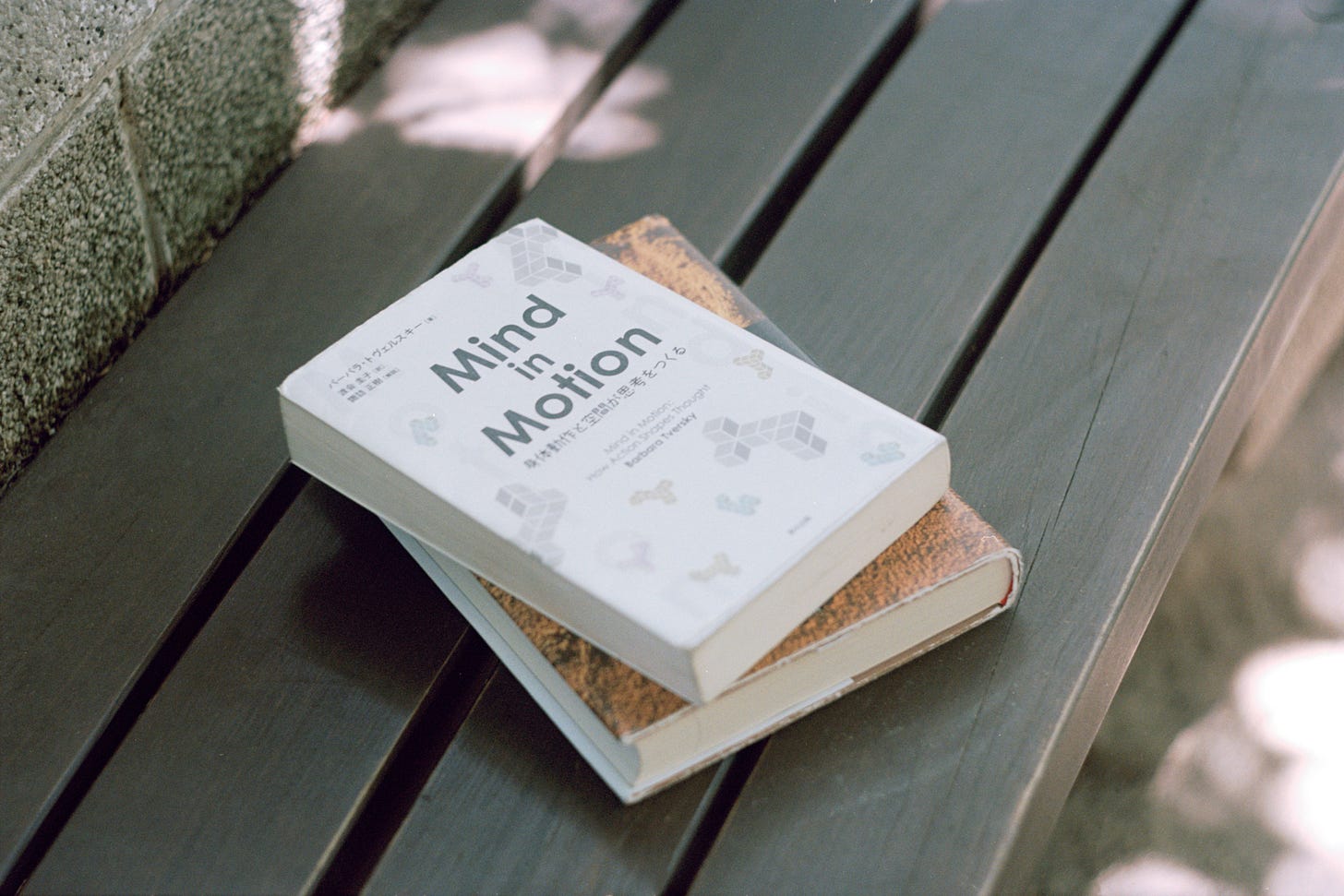一人ひとりの「生きているという実感」を見つけ出すために──メディア研究者・和田夏実
アカデミックインキュベーター・プログラム「デサイロ(De-Silo)」で、「『生きているという実感』が灯る瞬間の探求」という研究テーマに取り組む和田夏実さんに話を聞きました。
これまで学問、そして歴史やデザイン、建築は、人の“外”の世界ばかりを扱ってきた。しかし、本当は人の身体や頭の“内”には、一人ひとりそれぞれ広大な宇宙があるはず──メディア研究者の和田夏実さんはそんな問題意識のもと、頭の中にある言語以前の映像的・触覚的なイメージ、すなわち「内言」の研究をしています。「いま私たちはどんな時代を生きているのか」をアカデミアの知を頼りに探っていくアカデミックインキュベーター・プログラム「デサイロ(De-Silo)」で、和田さんが掲げる研究テーマは「『生きているという実感』が灯る瞬間の探求」。
「生きているという実感」が灯る瞬間の探求
人には誰しもの中に、ときめきを覚え、無我夢中になり、それに向かって走っていきたくなる衝動というものが存在する。もしくはその種が、それぞれの中に存在している。存在理由、生きている意味、そういった言葉ではなく、はりあいという、何かとの間で芯のあるぱりっとした感情と衝動が走り、自分の中でそうある自分自身、そこに没入している状態のことを心地よいと感じること、そうしたいきいき(LIVELY)とした状態はいかにして生まれうるのだろうか。本研究では、独自の世界認識や設定をもとにそれぞれが構築する内言のありようを探りながら、自分をとりまく世界から手応えを感じ、自らの中で種を咀嚼し、大切に育て、身体の中に息づくものとして耕す方法について検討する。いきいきとすることが描きうる世界の未来、ときめき自体がもたらす世界の開拓について、極限状態を起点として描きながら、一人ひとりの内なる世界が描く未来を探求する。
このテーマの背景には、和田さんのどのような思索やこれまでのキャリアがあるのでしょうか。当事者自身「による」、自律的な生き方の創造に向けた探求の軌跡を聞きました。
和田夏実(わだ・なつみ)
インタープリター ろう者の両親のもとで手話を第一言語として育ち、視覚身体言語の研究、様々な身体性の人たちとの協働から感覚がもつメディアの可能性について模索している。LOUD AIRと共同で感覚を探るカードゲーム《Qualia》や、たばたはやと+magnetとして触手話をもとにした繋がるゲーム《LINKAGE》など、言葉と感覚の翻訳方法を探るゲームやプロジェクトを展開。東京大学大学院 先端表現情報学 博士課程在籍。同大学 総合文化研究科 研究員。2016年手話通訳士取得。《an image of…》《visual creole》 "traNslatioNs - Understanding Misunderstanding", 21_21 DESIGN SIGHT, 2020
「生きているという実感」を灯すために
──和田さんは今回、「『生きているという実感』が灯る瞬間の探求」というテーマを設定されました。
はい。ときめきを覚え、それに無我夢中になり、それに向かって走っていきたくなる……人は誰しもそんな衝動、もしくはその種を持っていると思うんです。そうした芯のあるぱりっとした感情と衝動が走り、自分の中で、そうある自分自身、そこに没入している状態のことを心地よいと感じること。そうした一人ひとりを肯定し「いきいきとする」状態を生み出すような社会のあり方、それにまつわる知の体系を探求していきたいと考えています。
──いきいきとする状態とは、例えばどんな状態のことを指すのでしょうか?
まだ探求の渦中ですが、例えば岡潔が研究について、「もうかくれて見えないだろうと思っていたチョウを、谷間の杉の木で見つけたときの、強く、鋭い喜びは、いまも心のなかに鮮明に残っているが、これこそ発見の純粋な喜びで、私が研究の中で求めている純粋な喜びに通じるものがある」と述べています(神谷美恵子. 生きがいについて神谷美恵子コレクション (Japanese Edition) (p.17). Kindle 版)。こうした、強く、鋭い喜びのようなものに向かっていく、もしくはそうした景色が頭に浮かび、それに向かう状態が「いきいき」なのではないかと思います。
パーキンソン病のとある方は、妻と歌を歌う瞬間に身体がのびやかに広がり動きだし、子どもたちは言葉や概念を獲得していく過程で、多様な遊びを生み、遊びを通して理解を深めていきます。私の祖父は画家なのですが、認知症になってからも彼の中にある描くという営みが絶えず、日々生活の瞬間に美しさを感じては、作品を生み出すことが続いていく様子は、いきいきとしているように見えます。さまざまな喜びや衝動を起点とした、その人なりの世界の広げ方があるのではないか、と感じるんです。
ただ流れのままに身を任せるのではなく、そうした一人ひとりの固有のリアリティも想像しながら、50年後、100年後の未来の別のかたちを想像し、動き出すためのプロセスを踏んでいく。人間は整合性がなく、矛盾した生き物です。けれど、その中に熱や温度を持った水脈のようなものがある。一人ひとりに固有の“水脈”を発掘し、湧き出る環境や方法を探求していくことが、いきいきとした状態(LIVELY)を生み出すために必要だと思っています。
見過ごされてきた「内言」に目を向ける
──和田さんが今回のテーマを選んだ背景も知りたいです。これまで視覚身体言語の研究、ことばと感覚の翻訳方法を探るゲームやプロジェクトに取り組んできて、現在は「マテリアル・エクスペリエンス・デザイン」(物理世界の表現力拡張と体験のデザイン)の研究者・筧康明さん(東京大学大学院情報学環准教授)の研究室に所属しているのですよね。
はい。筧先生の研究室で表現メディアの研究を、そして言語と脳科学の研究室で学び、通訳者でもある私のテーマとして「内言」に関する研究をしています。頭の中にあるイメージの世界、写真の世界、触覚的な世界、考えている時に浮かぶものたち……ふだんの会話で使っている言語をはじめとした「外言」ではなく、頭の中にある言語以前の映像的・触覚的なイメージとしての「内言」。その存在を肯定し、それに目を向けていけるようにするための、メディアのようなものを構築できないかと研究しているんです。今回のデサイロのテーマは、その研究の一環でもあります。
内言の研究って、まだまだ未知数なんです。これまで学問、そして歴史やデザイン、建築は、人の“外”の世界ばかりを扱ってきました。人の身体や頭の中には、一人ひとりそれぞれ広大な宇宙があるはずなのに、その宇宙をそのままに探求するための学問はあまりなかった。一人ひとりの世界認識や社会探求の仕方をベースに、その人自身のイメージや感覚に近い形でのメディアを通して世界に触れ、それを伝えていくことで、個々が自らいきいきと存在できる人生をデザインできないか……そうした個から生まれる探求や探索に、とても興味があるんです。
──内言、おもしろい概念ですね。一方、外言と違ってその姿かたちが見えづらいからこそ、研究が進んでこなかった側面もあるような気がします。和田さんはどのようなアプローチで、内言の研究に取り組んでいるのでしょうか?
研究としては、脳科学的に脳の反応や信号を見ていくアプローチも学んでいます。でもそれだけじゃなくて、通訳を通して触れてきた、人の頭の中にある宇宙に身体を通して飛び込み、メディアも活用しながらその翻訳を探る方法も活用しながら、学びや知識の体系を作りたいと考えています。
これまで、想像したものを顔や手など身体で表すことでお互いの頭の中を伝え合うコミュニケーションゲーム「SHAPE IT!」、各々のカメラロールの中の写真を通してともに互いの感覚を探るカードゲーム「Qua|ia」といったプロジェクトを手がけてきました。デサイロでも今回のテーマを探っていくにあたって、そうしたプロジェクトやワークショップを作りたいですね。
──「内言」という研究テーマは、和田さんがこれまでさまざまな活動に取り組む中で名乗ってきた「インタープリター(媒介者)」というコンセプトにも通じますね。
はい。私はこれまで「インタープリター」と名乗り、さまざまな身体性や感覚を持っている方々の間で翻訳や通訳をしながら、それぞれの世界の見方に触れ、「翻訳」方法をともに探り、その人自身が感覚に近い形で外化するためのツール自体から作っていくことをしてきました。
博物館の学芸員さんなども伝え手として「インタープリター」と呼ばれることがありますが、私がこの肩書きがいいなと思っているのは、伝える方法を探るプロセスがあるから。さまざまな現場で出会ってきた人やコトたちに感じた愛や尊さ、その魅力がいかにその人らしく伝わるか、関わり合いを考えながら、その方法を探ることや魅力を探求・開拓するための場を作っていくことに興味があるんです。
アーティストとして表現するというよりは、出会った対象がいて翻訳について考える過程で生まれるものが多いゆえに、インタープリターという表現がしっくり来ています。
いま紹介したプロジェクトやツールも、研究やツール単体で成果を得るというより、それらを通して人の身体や内世界に出会う、それを受け手側の世界も尊重しながら互いに伝え、存在や関係性を立ち上げていく、といったものです。関わり合いの中で世界の豊かさを健やかに探求していく営みを、自分はやり続けていきたいなと思っています。
「未知なるもの」に感じたロマン
──「内言」に関心を抱くようになるまでの経緯もうかがいたいです。
私は幼少期から、未知なるものへの探求や探索に、大きなロマンを感じていた部分があって。ろう者の両親のもとで手話を第一言語に育ってきて、四歳くらいの頃にはその環境の特殊性に対する自覚も芽生えていました。とはいえ家の中ではそれが普通のことだったので、取り立てて強い関心は芽生えず、小学生の時は宇宙飛行士、中学生の時は深海魚に強い興味を持っていました。ですから大学受験の時も、生命科学科や海洋大学に進もうと思っていたんです。
──宇宙飛行士や深海魚……いまの和田さんのご活動とは、かなりイメージが違いますね。
そうですよね(笑)。でも、結局縁あってSFCに進学することになり、古石篤子先生という、バイリンガル教育を研究する先生のもとで、多言語教育やろう教育について学ぶようになりまして。
──そこで初めて、ご自身の出自にかかわる領域に出会ったのですね。
ただ、自分の原体験と近いけれど、状況が違うろう学校の子どもたちと接する中で、私の身体でどれだけその子たちに近づけるのか、悩むようにもなりました。ちょうど古石先生の退官のタイミングだったこともあり、アイデンティティ・クライシスのような状態に陥っていましたね。
そもそも私は、バイリンガルというより「バイモーダル」……それぞれの感覚器官による世界認識に興味がありまして。例えば、ろう者である両親と会話する時は、音自体の優先順位が下がります。そして、視覚による情報処理の精度が一気に高まる。たとえるなら、AirPodsでノイズキャンセリングした時のような感じでしょうか。
両親との会話の中で、頭の中のイメージが手によって身体を通して映像的に言語化されていく感覚と、「分けて、名付ける」音声言語由来の研究のあり方に対して、自分自身の感覚として相性の悪さを感じていました。大学時代から改めて、手話に惹かれて研究したいと考えていたものの、分けて名付けていくことと、手話を話すことからなるイメージの広がりに対して、身体感覚としてのズレを感じていたんです。
「by」(当事者による)のデザインを追い求めて
──分けていくアプローチだと、豊かな身体感覚が見落とされてしまう感覚があったと。
そんな中で出会った概念が、いまの指導教官である筧先生が当時提唱していた「HABILITATE(ハビリテート)」でした。マイナスをゼロにする考え方である「リハビリテーション」から「リ」を取り、ゼロを起点に人間がより豊かになっていくための技術開発を考えようという概念。「これこそがまさに自分のやりたいことなんじゃないか」と感じました。
そして縁あって、障害の原因を個人や医療ではなく社会の側に捉える「障害の社会モデル」に立脚し、マイノリティーの方々と一緒にデザインしていく「インクルーシブデザイン」を研究していた水野大二郎先生の研究室にも入ることに。そこではさまざまな就労支援施設も探訪しながら、当事者たち自身がデザインできる状態を作る「Design by People」を探求していました。
──和田さんの活動に引きつけると、ろう者の方々の「ために」こちらがデザインするのではなく、ろう者の方々「自身が」デザインできるようになるための探求をされていたということですか?
そうなんです。当時(2015年頃)は、「Design for People」(人のためにするデザイン)から「Design with People」(人とともにするデザイン)、そして「Design by People」への移行を推し進める流れがありました。
誰かの「ために」デザインしたものが、使い手自身の自己の探求から距離が遠かったり、まっすぐなアプローチができていなかったりと、実質的にあまり効果がないことがわかってきた。それで、当事者と「ともに」作っていこうという動きが起こったのですが、今度はデザイナーと当事者の間のバランス感覚が難しいという問題が生じてきまして。
ちょうどオープンソースデータをもとにしたオープンデザインの潮流が起きていたこともあり、問題解決のプロセスをツールキット化、レシピ化することで、当事者自身「による」デザインが行える生態系をつくろうとする動きが生まれていた。ですから、私も卒業制作では、ろうの方が自らの身体性に紐づいて社会とのつなぎ方を生み出していけるツールキットを作りました。
──ろう者自身の身体性を起点にするという考え方は、現在の研究テーマである「内言」、そして今回のテーマにつながりますね。
まさにその流れで、博士課程からは筧先生の研究室に入り、これまで作ってきた遊びやツールをヒントに、表現メディアをつくりながら、内言の研究をするようになりました。「生きているという実感」とは結局、自ら世界との接続のあり方を設計し、生き方を自律的に創造できるようになることだと思うんです。例えば、自分以外の人はもちろん、鯨たちや犬の持っている世界だって、私たちの知覚できない豊かさに溢れている。そんな前提に立って、共生のあり方を考えていきたい。一人ひとりの「by」を起点とした、共生のあり方を考えていきたいんです。
研究は「なかったことになってしまうもの」を照射する
──先ほど「既存の研究の体系に対する違和感」というお話もありましたが、和田さんの研究はユニークで、まだまだジャンルとして確立していない領域だと思います。だからこそ、研究を継続していくための環境作りや資金集めも容易ではないはずです。
そうですね。環境作りの中でも特に、表現メディアの研究や開拓と、文化を常に創造し続けられる集合体が大切だと思っています。例えば手話の研究をするにしても、私一人では進められないし、論文を読んでいてわからない部分も出てくる。そういう時に一緒に取り組める“研究体”のようなコミュニティを作るため、研究費の獲得に取り組んでいます。
さらに博物館や美術館といった文化施設を、世界にあるものを伝える場所にとどまらず、コミュニティの人たちとともに学びの体験を発掘し、世界にある文化と出会う場所にできないかとリサーチを行いながら仲間達と構想しています。研究者として当事者たちの中に一人だけ呼ばれてリサーチする「Design for People」的なアプローチではなく、「Design by People」的に当事者たちがポコポコと生み出した生命体や生態系みたいなものに出会い、世界のことわりや成り立ちの面白さをともに考える場所を作りたいんです。
──和田さんは一人ひとりの「by」を推し進めていくため、研究に取り組まれているのですね。
私の中での研究の定義、研究をしていることの意味は、「なかったことになってしまうものを、なかったことにしないためのもの」だと思っていまして。さまざまな方向から光を当てて研究を進めることで、それにどんな価値があったのか、どんなものなのかを考えられるものにするということです。
──アカデミズムの権威性をある意味でハックし、“巨人の肩に乗せる”ことで、「なかったことになってしまう」ものにかたちを与えようとしているのですね。
ただ、並行して“巨人の再構築”も必要だと思います。例えば、アリストテレスによるろう者への誤った理解とラベリングは今もなお“呪い”となり、未だにそれが参照されてしまったりもする。哲学の世界や工学の分野での女性やマイノリティーの割合の低さにも顕著に表れていますが、知の巨人たちの中にも、偏りはあり、また同時に研究を残すためのフォーマットにも論文や言語の優位性といった課題があるでしょう。
巨人を解体し、メディアや関係性の新しい形を創り直しながら、流れていくものをとどめて、みんなで扱えるものにする。そのプロセスこそを、研究と呼べたらなと思います。
Text by Masaki Koike, Interview by Kotaro Okada, Photographs by Kazuho Maruo
■ Twitter:@desilo_jp
■ Instagram:@desjp
■ Discord:https://discord.gg/ebvYmtcm5P
■バックナンバー
【10月22日開催】人文/社会科学領域の研究をエンパワーするには?──社会との接続、資金調達の方法を考える【De-Siloローンチ記念イベント】