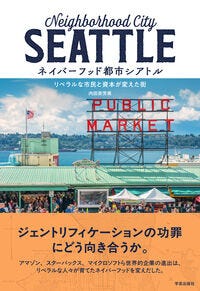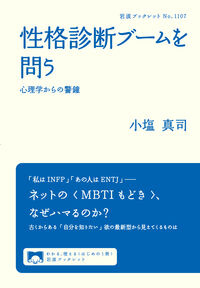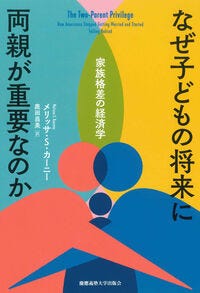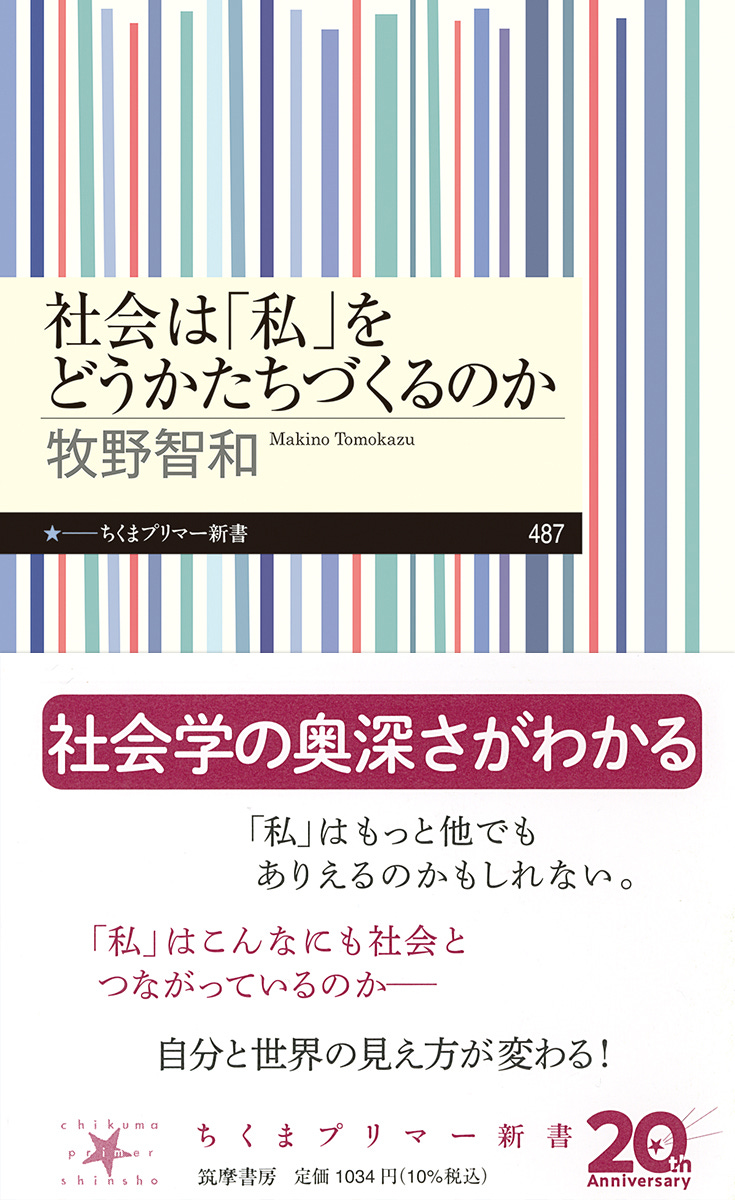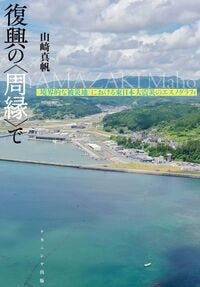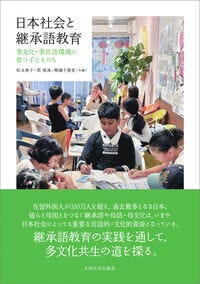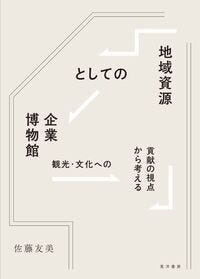【2025年4月刊】修理する権利、差別の現代民俗学、「脱観光化」の人類学……デサイロが注目したい人文・社会科学の新刊17冊
「いま私たちはどんな時代を生きているのか」──人文・社会科学領域の研究者とともにこの問いを探り、研究のなかで立ち現れるアイデアや概念の社会化を目指すアカデミックインキュベーター「デサイロ(De-Silo)」。
2025年4月に刊行の人文・社会科学領域の新刊書の中から、デサイロとして注目したい17冊をピックアップしました。
気になるタイトルがあれば、読書リストにぜひ加えてみてください。
1.脱観光化の人類学:かわりゆく観光と社会のゆくえ
概要(版元ウェブサイトより引用)
ポストコロナのツーリズムとは――
フィールドでの経験を踏まえこれからの観光を考える
現代社会で観光は誰もが享受できる娯楽として 大衆化した。本書は、「脱観光化」をキーワードに「善きもの」としての観光の光と影をフィールドでの事例にもとづいて具体的に論じる。
著者
東賢太朗 (編)
2025年3月現在
名古屋大学大学院人文学研究科准教授
福井栄二郎 (編)
2025年3月現在
島根大学法文学部准教授
奈良雅史 (編)
2025年3月現在
国立民族学博物館学術資源研究開発センター准教授
総合研究大学院大学先端学術院准教授
発売日
2025/4/3
版元
ミネルヴァ書房
2.ネイバーフッド都市シアトル: リベラルな市民と資本が変えた街
概要(版元ウェブサイトより引用)
ジェントリフィケーションの
功罪にどう向き合うか。
アマゾン、スターバックス、マイクロソフ
トら世界的企業の進出は、リベラルな人々
が育てたネイバーフッドを変えだした。
リベラルでアクティブな市民やオルタナティブなスモールビジネスが育む多様なネイバーフッドに、アマゾン、スターバックス、マイクロソフトら世界的企業が進出し、西海岸の地方都市を米国有数のスーパースター都市に変貌させた。ジェントリフィケーションがもたらす功罪、それに人々がどう向き合ったか、躍動感あふれる軌跡。
著者
内田奈芳美 (著)
埼玉大学人文社会科学研究科教授。2004年ワシントン大学(シアトル)アーバンデザイン&プランニング修士課程修了。2006年早稲田大学大学院博士課程修了。博士(工学)。金沢工業大学環境・建築学部講師などを経て現職。アーバンデザインセンター大宮副センター長。2021~22年、ワシントン大学・ラトガーズ大学客員研究員。主な著書に『金沢らしさとは何か』(2015年、北國新聞社、共同編集)、『都市はなぜ魂を失ったか:ジェイコブズ後のニューヨーク論』(2013年、講談社、翻訳)など。
発売日
2025/4/6
版元
学芸出版社
3.性格診断ブームを問う──心理学からの警鐘
概要(版元ウェブサイトより引用)
あなたは○○型です。○○型と相性が良さそうです。――ネット上の質問に答えるだけで人の性格を16にタイプ分けする〈MBTIもどき〉検査が若者の間で大流行している。コミュニケーションのツールとして楽しむ人がいる一方、採用活動にまで使われることは妥当なのか。「コスパとタイパ」時代の私たちの欲望を解き明かす。
著者
小塩 真司 (著)
1972年愛知県生まれ.名古屋大学教育学部卒業,同大学院教育学研究科教育心理学専攻修了.博士(教育心理学).2012年より早稲田大学文学学術院教授.専門はパーソナリティ心理学,発達心理学.著書に『自己愛の青年心理学』(ナカニシヤ出版,2004年),『はじめて学ぶパーソナリティ心理学』(ミネルヴァ書房,2010年),『性格を科学する心理学のはなし』(新曜社,2011年),『性格がいい人,悪い人の科学』(日経プレミアシリーズ,2018年),『性格とは何か――より良く生きるための心理学』(中公新書,2020年),『「性格が悪い」とはどういうことか――ダークサイドの心理学』(ちくま新書,2024年)など.
発売日
2025/4/8
版元
岩波書店
4.なぜ子どもの将来に両親が重要なのか:家族格差の経済学
概要(版元ウェブサイトより引用)
・「家族の衰退」が子どもの経済格差を拡大させる。
・40年間で激増した「ひとり親家庭」の原因と困窮をデータ分析し、格差解消のための支援を考える。
米国の1980 年~2020年のデータを分析することで、ひとり親世帯の激増と出産数の減少、また子どもの将来の所得や生活に家族構成が大きく関係していることを示す。日本における子育て支援策等にも大きなヒントを与える1冊。
著者
メリッサ・S・カーニー(著)
メリーランド大学のニール・モスコウィッツ経済学教授。アスペン経済戦略グループ・ディレクター、全米経済研究所(NBER)リサーチ・アソシエイト、ブルッキングス非常駐シニアフェロー。ノートルダム大学ウィルソン・シーハン経済機会研究所(LEO)の研究員および理事、マサチューセッツ工科大学アブドゥル・ジャミール貧困行動研究所(J-PAL)の研究員を務める。プリンストン大学で経済学の学士号、マサチューセッツ工科大学(MIT)で経済学のPh.D.を取得。研究は社会政策、貧困、不平等に関する実証研究。論文はトップジャーナルに掲載され、一般紙にも頻繁に引用されている。
鹿田昌美(訳)
翻訳家。国際基督教大学卒。翻訳書に、ドゥプケ&ジリボッティ『子育ての経済学─愛情・お金・育児スタイル』、ゴールディン『なぜ男女の賃金に格差があるのか─女性の生き方の経済学』(以上、慶應義塾大学出版会)、アレキサンダー&サンダール『デンマークの親は子どもを褒めない』(集英社)、ドーナト『母親になって後悔してる』(新潮社)など多数。翻訳経験と子育ての経験を生かした著書に『翻訳者が考えた「英語ができる子」に育つ本当に正しい方法』(飛鳥新社)がある。
発売日
2025/4/10
版元
慶應義塾大学出版会
5.観光という虚像―アイデンティティをめぐる地方自治体の自問自答
概要(版元ウェブサイトより引用)
遠くて近きは観光地。そこには地域社会に生きた人々の葛藤の歴史がある。地域の貌をめぐる「自問自答」の末に、地方自治体が見出した指針とは何だったのか。神戸市、水俣市、むつ市それぞれの観光政策はどのような意味を持つのか。観光業が知らない観光のあり方が、ここにある。
著者
宮﨑友里(著)
兵庫県出身
神戸大学大学院国際協力研究科博士後期課程修了,博士(政治学)
龍谷大学地域公共人材・政策開発リサーチセンター博士研究員(2020年度)
現在、立教大学観光学部 助教
主要業績
「水俣市における教育旅行:水俣病への説明変化に着目して」『日本観光研究学会全国大会学術論文集』第33号、2018年。
「地方自治体の観光政策と社会心理学の視点」『実験社会心理学研究』第58巻第2号、2019年。
「むつ市と恐山イタコ観光:地域像に着目して」『国際協力論集』第27巻第1号、2019年。
「神戸市によるファッション都市事業開始後の地域社会における神戸像:社会科副読本に着目して」『立教大学観光学部紀要』第24号、2022年。
発売日
2025/4/10
版元
晃洋書房
6.社会は「私」をどうかたちづくるのか
概要(版元ウェブサイトより引用)
社会学の奥深さがわかる
「私」はもっと他でもありえるのかもしれない。
「私」はこんなにも社会とつながっているのか――
自分と世界の見え方が変わる!
なぜ「私」は、今のような「私」であるのだろうか?
他者との関係性からより広い社会的状況までに影響を受け、
「私」という存在は複雑にかたちづくられている。
社会学のさまざまな観点からその成り立ちについて考え、
「私」と社会をめぐる風通しをよくする手がかりを示す。
著者
牧野 智和(本文)
1980年、東京都生まれ。早稲田大学大学院教育学研究科博士後期課程単位取得退学、博士(教育学)。現在:大妻女子大学人間関係学部教授。専門はアイデンティティ論、社会学。著書に『自己啓発の時代――「自己」の文化社会学的探究』、『日常に侵入する自己啓発――生き方・手帳術・片づけ』、『創造性をデザインする――建築空間の社会学』(いずれも勁草書房)など。
発売日
2025/4/10
版元
筑摩書房
7.差別の現代民俗学――日常の中の分断と排除
概要(版元ウェブサイトより引用)
民俗学において被差別部落や「ケガレ」に関する研究は重ねられてきたものの、現代社会で多様化し複雑化している日常の中の差別に民俗学は向き合ってきただろうか。生理的嫌悪感やニオイ、食べ物、電車で起こる軋轢等から改めて差別と排除の問題を問い直した民俗学革新の書。)
著者
「差別・排除の民俗学」研究会 (編著)
発売日
2025/4/13
版元
明石書店
8.復興の〈周縁〉で: 〈境界的な被災地〉における東日本大震災のエスノグラフィ
概要(版元ウェブサイトより引用)
「ここはB級被災地だから」
「俺たちは置き去りにされている」
「私たちは被災者じゃないから」
広範な地域に甚大な被害をもたらした東日本大震災。直接的な津波被害を受けず、被災と非‐被災の境界に位置する地域が存在する。そこに暮らす人びとは自らのポジショナリティに苦悩し、災害体験を語ることを躊躇していた。彼/彼女たちにとって復興とは何か。
著者
山﨑真帆 (著)
一橋大学大学院社会学研究科地球社会研究専攻博士後期課程退学。博士(社会学)。現在、東北文化学園大学現代社会学部講師。専攻は人文・社会科学的な災害研究。共著に『〈メガイベントの遺産〉の社会学』(青弓社)、論文に「住家への津波被害を免れた人々における東日本大震災からの「復興」」(『日本災害復興学会論文集』第15号)、「復興過程における「被災者」の自己認
識に関する一考察」(『日本災害復興学会論文集』第16号)など
発売日
2025/4/14
版元
ナカニシヤ出版
9.政治哲学講義-悪さ加減をどう選ぶか
概要(版元ウェブサイトより引用)
混迷の時代に灯火をともす一書。
正しさとは何かを探究してきた政治哲学。向き合う現実の世界は進むも退くも地獄、「よりマシな悪」を選んでなんぼの側面をもつ。
命の重さに違いはあるのか。汚い手段は許されるか。大義のために家族や友情を犠牲にできるか。
本書はサンデルの正義論やトロッコ問題のような思考実験に加え、小説や戯曲の名場面を道しるべに、「正しさ」ではなく「悪さ」というネガから政治哲学へいざなう。混迷の時代に灯火をともす一書。
著者
松元雅和(著)
1978年東京都生まれ.慶應義塾大学大学院法学研究科博士課程修了.博士(法学).島根大学,関西大学を経て,2018年から日本大学法学部准教授,2020年から同教授.専攻は,政治哲学・政治理論.単著『リベラルな多文化主義』(慶應義塾大学出版会,2007年),『平和主義とは何かー政治哲学で考える戦争と平和』(中公新書,2013年,第35回石橋湛山賞),『応用政治哲学ー方法論の探究』(風行社,2015年),『公共の利益とは何かー公と私をつなぐ政治学』(日本経済評論社,2021年).共著『ここから始める政治理論』(有斐閣,2017年),『正義論ーベーシックスからフロンティアまで』(法律文化社,2019年),『現実と向き合う政治理論』(放送大学教育振興会,2022年)など.主要論文は,International Relations,European Journal of International Relations,International Politics,AI and Societyを含む国内外の学術誌に掲載されている.
発売日
2025/4/22
版元
中央公論新社
10.集団はなぜ残酷にまた慈悲深くなるのか-理不尽な服従と自発的人助けの心理学
概要(版元ウェブサイトより引用)
集団の光と闇を解明する試み
組織の不祥事が報道されると「自分なら絶対にやらない」と思う。だが、いざ当事者になると、個人ならしない悪事でも多くの人は不承不承、あるいは平気でしてしまう。 なぜ集団になると、簡単に同調・迎合し、服従してしまうのか。 著者は同調や服従に関する有名な実験の日本版を実施し、その心理を探る。 一方でタイタニック遭難など、緊急時に助け合い、力を発揮するのも集団の特性である。 集団の光と闇を解明する試み。
著者
釘原直樹(著)
大阪大学名誉教授.1952年,福岡県生まれ.1975年熊本大学教育学部卒業,1982年九州大学大学院教育学研究科博士後期課程(教育心理学専攻)満期退学.大阪大学人間科学部助手,九州工業大学工学部教授,大阪大学人間科学研究科教授等を経る.博士(教育心理学).専攻・社会心理学.
著書『人はなぜ集団になると怠けるのか――「社会的手抜き」の心理学』(中公新書,2013),『パニック実験――危機事態の社会心理学』(ナカニシヤ出版,1995),『グループ・ダイナミックス――集団と群集の心理学』(有斐閣,2011),『スケープゴーティング――誰が,なぜ「やり玉」に挙げられるのか』(有斐閣,2014),『あなたの部下は,なぜ「やる気」のあるふりをするのか――組織のための「手抜き」のトリセツ』(ポプラ社,2017)ほか
発売日
2025/4/22
版元
中央公論新社
11.民主主義——終わりなき包摂のゆくえ
概要(版元ウェブサイトより引用)
民主主義はどこへ行くのか?
民主主義の危機が問われるいま、その普遍的な「理念」と具体的な「実現」とはどのようなものなのだろうか。
本書は、ポスト・トゥルース的な右派ポピュリズムが席捲するように見える現代の民主主義の危機を理解し、それに応答するために、民主主義の普遍的な理念とその具体的な実現の両方に軸足を定めつつ、古代から中世・ルネサンス、社会契約論から十九世紀のマルクス主義などの進歩主義、第二次世界大戦の衝撃から二十世紀後半の社会運動、そして現在進行中の出来事へと論を運ぶ。
さらには、気候変動、パンデミック、排外主義的なポピュリズムの席捲などを見すえて、民主主義の「未来」を覗き見ようと試みる。
政治学史ではここ数十年、ケンブリッジ学派の台頭や個別的な研究の深まりのなかで、〈どう生きるべきか〉という規範的な問いはややもすれば後景に退いてしまった。
広く長い歴史的視座で簡潔にまとめられた本書は、「民主主義」を思考するための新たなスタンダードとなるはずだ。オックスフォード大学出版局の人気シリーズの待望の翻訳! 「合衆国権利章典」「人および市民の権利の宣言」「世界人権宣言」を付す。
著者
ナオミ・ザック(著)
1944年,ニューヨーク市生まれ。1970年,コロンビア大学で博士号を取得。その後20年のブランクを経て,1990年,学界に復帰。ニューヨーク州立大学オールバニ校,オレゴン大学で教鞭を執り,現在,ニューヨーク市立大学リーマン校哲学教授。専門は,批判的人種理論,アイデンティティ哲学,フェミニスト理論。
河野 真太郎(訳)
1974年生まれ。一橋大学法学部卒,2005年,東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得満期退学。現在,専修大学国際コミュニケーション学部教授。専門は20世紀イギリスの文化と社会だが,関心は文化史,ジェンダー論など多岐にわたる。主な単著および単独訳として,『新しい声を聞くぼくたち』(講談社,2022年),『この自由な世界と私たちの帰る場所』(青土社,2023年),『増補 戦う姫,働く少女』(筑摩書房,2023年),『ぼっちのままで居場所を見つける』(筑摩書房,2024年),P・バーク著『文化のハイブリディティ』(法政大学出版局,2012年),T・ジャット著(T・スナイダー聞き手)『20世紀を考える』(みすず書房,2015年),W・ブラウン著『新自由主義の廃墟で』(人文書院,2022年)などがある。
発売日
2025/4/24
版元
白水社
12.修理する権利: 使いつづける自由へ
概要(版元ウェブサイトより引用)
なぜスマホのバッテリーはすぐ交換できないのか?
短い保証期間、高額な修理費用、交換のできない部品……わたしたちは修理することからますます遠ざけられている。「壊れたら買い替え」へ消費者を駆り立てる資本主義社会には、修理を阻む巧妙なカラクリが隠されていた。そうしたなか、いま米国やヨーロッパで「修理する権利」運動が巻き起こっている。その現状を縦横無尽に分析した決定的入門書。
著者
アーロン・パーザナウスキー(著者)
ケニオン大学卒業後、カリフォルニア大学バークレー校法科大学院を修了。現在はミシガン大学教授として著作権や商標、財産法などについて教鞭をとる。専門はデジタル経済圏における知的財産法や物権法について。これまでの著作として『所有の終焉(The End of Ownership)』や、共編著『法なきクリエイティビティ(Creativity without Law)』がある。
西村伸泰(訳者)
法政大学法学部卒。雑誌記者、広告プランナーを経て翻訳業に従事。
発売日
2025/4/28
版元
青土社
13.生活保障システムの転換
概要(版元ウェブサイトより引用)
この国の生活保障システムは人びとの命と暮らしを脅かしている。所得再分配後に貧困が深まるという〈逆機能〉の存在を指摘してきた著者が、歴史の検討と各国との比較を通じて「男性稼ぎ主」型システムの問題点をあぶり出し、社会のしくみを歪めたアベノミクスとコロナ対策を徹底批判。転換の方途を提言する。
著者
大沢 真理(著)
1953年生まれ.東京大学名誉教授.社会政策研究者.経済学博士.『イギリス社会政策史――救貧法と福祉国家』(東京大学出版会),『男女共同参画社会をつくる』(NHKブックス),『現代日本の生活保障システム――座標とゆくえ』,『いまこそ考えたい 生活保障のしくみ』(以上,岩波書店),『企業中心社会を超えて――現代日本を〈ジェンダー〉で読む』(時事通信社,第13回山川菊栄賞受賞,のち岩波現代文庫),『生活保障のガバナンス――ジェンダーとお金の流れで読み解く』(有斐閣,第6回昭和女子大学女性文化研究賞受賞)のほか編著書多数.訳書にG.エスピン=アンデルセン『平等と効率の福祉革命――新しい女性の役割』(監訳,岩波現代文庫)がある.
発売日
2025/4/28
版元
岩波書店
14.感情がつくられるものだとしたら 世界はどうなるのか: バレットの構成主義的情動理論をめぐる、さまざまな領域からの考察
概要(版元ウェブサイトより引用)
医学分野では、感情は生物学的な実体があるものとされてきました。その見解によって、例えばうつ病(不安障害)の薬物療法などが行われ、一方で同じうつ病でも社会的な影響によって生じているとされる部分は心理療法による治療が行われてきました。ただ、心理学者リサ・フェルドマン・バレットの主張するように、「感情とは根本的に社会的に構成されたものである」とすると、それは従来の見解をどのように変更したらいいのか、さらには実際の治療を変更しないといけないのか、という問いが生じます。これは精神科医に限らず、医療者全般、心理職の関心だけでなく、精神鑑定など社会制度にまで影響が及ぶ可能性があるでしょう。とはいえ、「社会的に構成されている」という言葉が指す内容は理解が難しいものです。そこで、哲学者・心理学者・神経学者によるバレット理論の解説を踏まえ、「感情が社会的に構成されている」という論に対する論説を並べました。
著者
植野仙経(編集)
京都大学医学部附属病院精神科神経科
佐藤弥(編集)
理化学研究所ガーディアンロボットプロジェクト心理プロセス研究チーム
鈴木貴之(編集)
東京大学大学院総合文化研究科
村井俊哉(編集)
京都大学大学院医学研究科精神医学
発売日
2025/4/28
版元
金芳堂
15.ELSI入門: 先端科学技術と社会の諸相
概要(版元ウェブサイトより引用)
ELSIとは倫理的・法的・社会的課題(Ethical, Legal and Social Issues)の頭文字をとったもので、「エルシー」と読まれている。新規科学技術を研究開発し、社会実装する際に生じうる、技術的課題以外のあらゆる課題を含む。ELSIは新規科学技術を社会や政策に橋渡しするために有用な概念である。人文社会科学系の研究者らに一定の研究費が継続的に投じられたことは、先駆的であり、データサイエンスとAIの適用に倫理原則や社会受容性が求められる現在に多くの示唆を与えるものであった。本書は、オープンに議論を展開し、相互に学びあい、問題解決に資する社会制度を創り上げていくという考えのもととなっているELSIの現在の動向を紹介する。
著者
カテライ アメリア (編集)
鹿野 祐介 (編集)
標葉 隆馬 (編集)
発売日
2025/4/30
版元
丸善出版
16.日本社会と継承語教育──多文化・多言語環境に育つ子どもたち
概要(版元ウェブサイトより引用)
本書のねらいは、継承語や母語・母文化が当事者やその家族、民族にとってのみならず、日本社会にとっても重要かつ必要な文化資源・言語資源であることを様々な事例をもとにひも解いていくことである。このため、本書では、継承語と継承語教育について、法制度・政策、文学・心理学、言語習得・学習動機、異文化コミュニケーション、継承語教育理論、教育実践、人権といった様々な領域から切り込んでいく。
著者
松永 典子(編)
九州大学名誉教授。九州大学・博士(比較社会文化)。高校教諭時代の青年海外協力隊(マレーシア・日本語教師)参加が多文化・多様性の豊かさや楽しさを知る原点となり、日本語教育、多文化共生教育に携わる。地域社会との連携活動を通して日本語指導が必要な児童生徒対象の教育研究会に参加する機会を得、子どもの日本語教育、継承語教育について学ぶ。それが縁で、「児童生徒等に対する日本語教師研修」(文化庁・現文部科学省)の運営委員やコーディネーター等、子どもの日本語支援者養成に関わる。日本社会の将来を支える子どもの教育、とりわけ日本社会の包摂性を高めるためには継承語教育が重要であると考える。
郭俊海(編)
九州大学留学生センター教授。シンガポール国立大学・Ph.D(応用言語学)。二人の子どもはシンガポール生まれ、家族とともに多様な言語や文化に囲まれた生活を送る中で、多様な言語や文化への関心を深めた。家族と来日後、家庭では母語と日本語のバイリンガル教育を実践しながら、福岡市中国人コミュニテイの週末母語学校の運営にも関わるなど母語・継承語教育の実施に取り組むが、その難しさや重要さを痛感。大学院の授業では、この課題が日本社会全体にとって重要であることを認識し、院生たちとともに多言語教育や継承語教育に関する議論を深めている。
柳瀬 千惠美(編)
元九州大学大学院比較社会文化研究院特別研究者。九州大学・博士(学術)。津田塾大学学芸学部国際関係学科卒後、教職等を経て、1992年から20年あまり中国北京市在住。中国人元夫との間に生まれた2人の子どもの育児で国際結婚家庭特有の問題に悩むが、「中国人男性と結婚した日本人女性の会」と出会い、同じ悩みを抱えた人たちとの交流が始まる。そこで子どもに日本語や日本文化を伝えたいという母親が集まり子ども会活動を始め、現在もその活動は健在である。自身の子育てを振り返る中で「継承語」という言葉を知り、継承語に関わる母親たちの経験を役立てたいと考え、九州大学大学院に進学。学位取得後も継承語の研究に専念するため特別研究者として在籍、現在に至る。
発売日
2025/4/30
版元
九州大学出版会
17.地域資源としての企業博物館―観光・文化への貢献の視点から考える
概要(版元ウェブサイトより引用)
「観光の場」としての企業博物館が現れる
企業博物館は企業の資料保存・公開やブランド力向上のために設置されるが、地域の観光コンテンツや生涯学習の場ともなり得る。
トヨタ博物館、中日新聞社、名古屋版アーツカウンシルなど、長年文化活動実践の現場に携わる著者が博物館法の改正により注目を浴びる「博物館と観光」の可能性を、企業博物館と産業観光の関係から問う。
著者
佐藤友美(著)
発売日
2025/4/30
版元
晃洋書房
デサイロでは、ニュースレターやX、Instagramなどを利用して、プロジェクトに関わる情報を継続的に発信中。ご興味のある方はニュースレターの登録や各SNSのフォローをお願いいたします。
■X:https://x.com/desilo_jp
■Instagram:https://www.instagram.com/desilo_jp/
■バックナンバー: