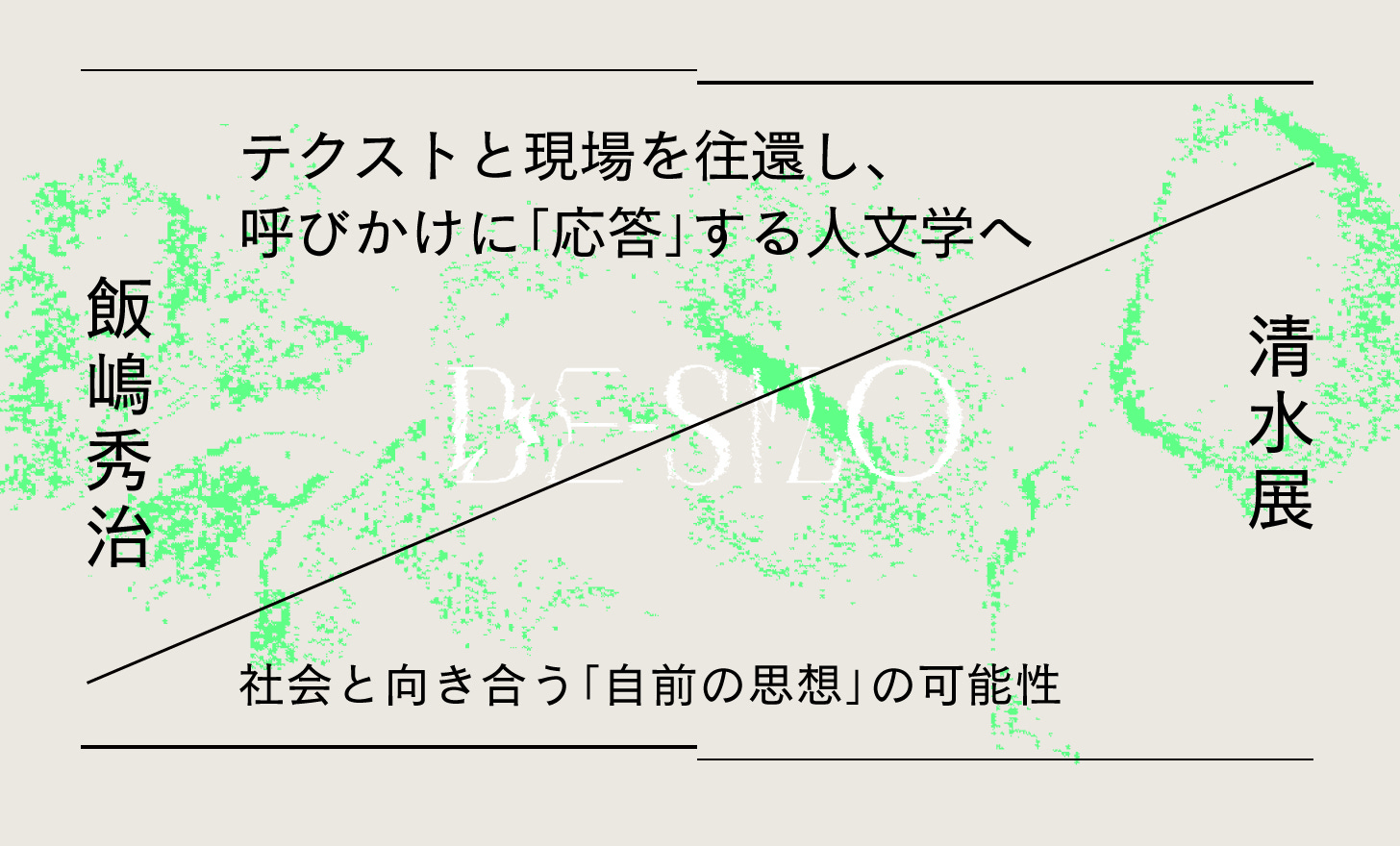テクストと現場を往還し、呼びかけに「応答」する人文学へ。社会と向き合う「自前の思想」の可能性──人類学者・飯嶋秀治、清水展
“いま学問や科学は、社会と本当に向き合っているだろうか?社会を解釈するに止まってはいないだろうか?”
そんな問いを出発点に、課題が発生する現場に身を置き、思索や行動をする“フィールドワーカー”たちの仕事や作法、技法をまとめた書籍が、『自前の思想: 時代と社会に応答するフィールドワーク』です。
本書で“フィールドワーカー”として取り上げられている10人の先人たちは、いわゆる「文化人類学者」にとどまらず、医師やジャーナリスト、作家まで多様です。そして、それぞれが異なる現場に向き合い、フィールドワークを通じて得られた体験や知見にもとづいた「自前の思想」を紡ぎあげています。
「自前の思想」はいかにして生まれるのか。「時代と社会に応答する」ことはいかにして可能なのか──人文・社会科学分野において「概念の社会化」を目指すデサイロとしても道標としている「自前の思想」(「自前の思想」が立ち現れていく学際的な場を目指して──2023年、デサイロの展望)。その可能性に迫るべく、本記事では『自前の思想: 時代と社会に応答するフィールドワーク』の編著者であり、自身も文化人類学者としてフィールドワークを基盤とした研究を重ねてきた飯嶋秀治さんと清水展さんにインタビューします。
本書の背景に込められた問題意識、そして「自前の思想」を編み上げるために必要な“フィールドワーカー”としての姿勢や信条とは?
飯嶋 秀治 (いいじま しゅうじ)
1969年,埼玉県本庄市生まれ。九州大学教授。主な論文には「暴力問題にまきこまれる―オーストラリア先住民の『トラブルメイカー』たち」(『アクション別フィールドワーク入門』),「施設の暴力と人類学」(『現実に介入しつつ心に関わる』),「癒しの力としての宗教・水俣」(『模索する現代』近代日本宗教史第6巻巻)など。
清水 展 (しみず ひろむ)
1951年,横須賀市生まれ。東京大学助手,九州大学助教授・教授,京都大学教授を経て,関西大学客員教授。主な著書に『噴火のこだま』『草の根グローバリゼーション』など。第11回日本文化人類学会賞(2016)や第107回日本学士院賞(2017)を受賞。
現場に「巻き込まれ」立ち上がる思想
──そもそも『自前の思想』はどのような経緯で生まれた本なのでしょうか?
飯嶋 元を辿れば、2012年頃から約5年間にわたって日本文化人類学会の中で課題研究懇談会として開催していた「応答の人類学」という研究会が発端です。そこでは「社会の喫緊の課題に応える人類学を構築できないか」という議論をしていて、2016年から「応答の人類学 フィールド、ホーム、エデュケーションにおける学理と技法の探求」という科研のプロジェクトになりました。当時「応答の人類学」シリーズとして数冊に分けて書籍化する構想があり、『自前の思想』は、そのいわば「思想篇・歴史篇」として位置付けられていた企画が結実したものです。
──「時代と社会に応答するフィールドワーク」という副題は、「応答の人類学」から来ていたのですね。ここで言う「応答」には、どのような意味が込められているのでしょう?
清水 人類学者には、現場から「呼びかけられている」と感じる時があると思うんです。「もしもし」「はいどうぞ」「応答せよ、応答せよ」といった、トランシーバーを使ったやり取りの際の呼びかけをイメージするとわかりやすいでしょうか。あるいはゴスペルの歌唱や演奏などにおける掛け合い、いわゆる“Call and Responce”にもたとえることができるでしょう、呼びかけられたら応えるという意味で。
フィールドワークは一方的に見たり聞いたり観察したりするのではなく、同時に相手からも見られ聞かれ観察されています。そうした互いの濃密なやりとりをとおして相互の理解が深まる。その際に大事なことは、フィールドワーカーの側が相手から呼びけられていることです。それを聞き流したり、聞き捨てにしたりせずに、ちゃんと応えましょうということ。そうした「呼びかけ」を自覚して、レスポンスとして具体的な発言や行動を起こす。フィールドワークという調査が終わった後も、お世話になった現場の人々と関係を続けて、さまざまなかたちで関与していく……「応答」にはそんな意味合いを込めています。
飯嶋 重要なのは、「応答」が状況に「巻き込まれる」ことで始まるという点です。現場の要請とたまたま出会い、逃げられなくなってしまうこと。その出会いが「自前の思想」を実践するフィールドワーカー、現場に応えてゆく人に共通して見られると思うんです。
──「巻き込まれる」ことで「応答」が始まる。その具体例も教えていただけますか?
清水 代表的な例は、『自前の思想』の第一章で僕が取り上げた中村哲さんでしょう。中村さんは医師であって、いわゆる人類学者ではないけれど、「自前の思想」、ひいては自前の「技術」や「知識」のエッセンスを体現している人です。
中村さんは幼少期から蝶が好きで、「珍しい蝶がいる」と聞いて憧れていたヒマラヤ山脈の登山隊に参加しました。その途中の村で、ハンセン病に感染し、手当てを受けられない村人たちに出会ってしまった。「何か薬を持っていないか」と懇願されても、「隊員のための薬だから出せない」と断るしかない。そして、その場から逃げるように立ち去った。
しかし、中村さんは後日、そのヒマラヤの村に戻ってきます。「見てしまった、出会ってしまったからには、もう目は瞑れないんだ」と。そして、1985年から現地で医療活動を始めます。しかし2000年になると地球温暖化の影響を受けてアフガニスタンは大旱魃に襲われます。それで中村さんは、大事なのは生き延びること、そのために必要なのは医療よりもまずは水だと判断し、井戸掘りプロジェクトを始めます。彼の活動を支援するNGOのペシャワール会の資金で1,600本の井戸を掘りますが、それではとても足りません。それで灌漑用水路を建設するプロジェクトを2003年から始めたというわけです。高校生の娘さんの数II数IIIの教科書を借りて復習し、独学で水路設計をして26キロにおよぶ灌漑用水路を現地の村人らとともに2010年に完成させました。
──ヒマラヤの村からの「呼びかけ」に巻き込まれ、「自前」のやり方で支援活動に従事するようになったと。
清水 そうです。僕自身にも、まさに「応答せよ」と呼びかけられていると感じた瞬間がありました。1991年にフィリピン・ルソン島でピナトゥボ火山大噴火が発生した時、僕はちょうど1年間のサバティカル休暇でフィリピンにいました。噴火の規模はその1週間ほど前に起きた雲仙・普賢岳の噴火の6〜700倍ほど、20世紀最大の規模でした。その噴火で被災して、故郷を追われて難民となったアエタ族は、その10年ちょっと前に僕が20ヶ月間のフィールドワークしていた地域の人々だったんです。
フィールドワークでお世話になったアエタの人たちは私の庇護者であり山での暮らし方を教えてくれる先生であり、また仲の良い友達でもありました。「友達がこんなに大変な思いをしているのに、見て見ぬフリをできるはずがない」と、それ以来人類学の研究はしばらく傍に置いて、 5年ほどは支援活動を優先し、長期の休みのたびに出かけてゆきました。当時はただ「まっとうな人間なら恩返しをするのが当然だろうな」と思っての行動でした。
その後、アエタの友人らは大変な時期を乗り越えて別の場所に定住し、創造的な復興を成し遂げていきます。その過程を見ていて、「これについて書かなければならない」「自分はいま何をなすべきか問いかけられているんじゃないか」と思ったんです。自分が“行きがかり”のなりゆきでやってきたことを、開き直って人類学者として考え直そうと思いました。そうして記録を残していったことが、「応答の人類学」の原体験になったんです。
ピナトゥボ火山大噴火(1991年6月15日)の後、一時避難センターを訪れ、カキリガン・グループのリーダーのビクター・ビリヤ氏に話を聞く清水さん。彼には1977年10月から1979年5月までのフィールドワークの際に調査を助けてもらったという(1991年11月)
「花開いた」からこそ、社会と乖離してしまった人文学
──学問と現場をつなぐなかだちとして「応答」があるように感じました。一方、日本ではとりわけ人文系の学問において、そうした社会との接続が十分になされていないといえる側面もあるのではないでしょうか。
清水 そうですね、それは人文系の学問が、1980年代に大きく花開いたことと関係があったように思います。とりわけ人類学では、アメリカではクリフォード・ギアツやヴィクター・ターナー、日本では山口昌男さんの大活躍もあって広く人文系の研究者の関心を集めました。バブル経済のピークに差し掛かる時でしたから、時代の気分をうまく掬い取るような評論や解説が求められていたのでしょう。
もちろん人類学はフィールドワークから始まり、それが学の基盤となります。山口昌男さんの超人的な読書量と博覧強記が生み出す作品は眩しいくらいに魅力的で、私も大好きでたくさん読み影響を受けました。
でも山口さんだからこそできる仕事であって、不勉強な自分にはとうてい真似できないと思っていました。その点、本書の第1章で取り上げた波平恵美子さんは日本でのフィールドワークを地道に続け、他方で脳死や臓器移植などのトピックにも積極的に発言し社会と応答してゆきました。
山口さんや波平さんらの先人たちの活躍のおかげで人類学も学問としての認知と評価が高まり、学会員も増えてゆきました。すると学会がひとつの組織や制度として整備され、より学問的な装いをとった研究が好まれるようになります。
それとは逆に自前の思想というのは、いわば素手で無手勝流に現場や当事者と向き合い、応答し、産みの苦しみを伴いながら鍛え上げてゆくものだと言えます。茶道や華道のように師匠から所作を学び、真似して上達してゆくのとはかなり違っています。もちろん先行研究や関連研究の勉強も大事ですが。
飯嶋 学会のシステムが整ってきたことが、結果的に研究者の社会性を見えにくくしてきたのかもしれません。学会は職能集団というか、ギルドのようなところがあって、その内部での常識や前提のなかで論文が生産されます。それが繰り返されるうちに、論文のテーマが社会ではなく学会の方を向くようになり、社会の課題から離れて届きにくくなってしまった面もあるのではないかと。
人類学の学会の内部で、外部の人にとっては分かりづらい用語が流通してしまう。あるいは、とにかく読まなければいけない先行研究が多すぎて、若手研究者が記号の中で溺れてしまう。学会という世界の中で、効率的に論文生産をしようとすると、論文を通しやすいパターンに沿って競い合ってしまう。
そして興味深いことに、最近の若手研究者にこそ、ものすごく調査能力は上がっているのだけれど、最後のタイトル付けなどのプロデュース段階で、「社会にいかなるメッセージとして発信するべきか」に迷ってしまう人が多いとも聞きます。それは、テーマが学会向けに育っていて、社会の喫緊の課題から離れてしまうという傾向につながってしまうようにも思うんです。
しかし先述したように、世の中には応答すべきテーマや事態が、ゴロゴロと存在しています。それらに対して「自分がやらざるを得ない」と、人類学者としての責務を感じて応答していくことで、既存のシステムの中で社会性を取り戻してゆく状況へと解きほぐしていけるはず。そうした試みを既に行ってきた先人として、「自前の思想」という言葉を投げかけたわけです。
責任(responsibility)を「応答」に解きほぐす
──「自前の思想」は、学問と社会が乖離する状況に対する、一つの抵抗としても捉えられるかもしれません。
飯嶋 「自前の思想(応答の人類学)」とは、「責任」という言葉を「応答」に解きほぐすことで、現場で生じた事態に学問を対応させようとする試みともいえます。
「責任」という言葉は、英語で“responsibility”です。しかし、「責任」という日本語にすると、法律などの固い枠組みの中にある概念に聞こえてしまう。ですが現場で生じてくる事態は、既に機能している学問の枠組みの外側で発生するので、「責任」という言葉では対応できないことも多いんです。
世の中には「放っておいていいわけがない」事態がゴロゴロと存在しますよね。僕が取り扱っている「児童福祉施設での暴力問題」もその一つです。「責任」という言葉で考え出すと、暴力問題に責任を持つ学問なんてないじゃないですか。別に文化人類学だからやらなければならないとか、臨床心理学だからやらなければならない、なんて必然性はないわけです。しかし、事態は目前で生じていて、放っておくわけにはいかない。
学問的な必然性がないので、最初にこのテーマで学会発表をした際には、「そんなのは人類学じゃない」とよく批判も受けました。まぁ私の問題提起の未熟さもあったのだろうと思いますが、その時、「この研究テーマが人類学かどうかという問題は、そんなに第一優先で考えるべきことなのか?」と疑問を感じたんです。人類学だけでなく、例えば社会学、政治学、歴史学、心理学、哲学などの学問の研究者も、こうした「放っておいていいわけがない」事態に対応する「責任」というと、そうした言葉からは逸れたり、漏れたり、零れ落ちてしまう事態が、「やらざるを得ない」と思わされてしまう瞬間がたしかにあるはずです。
私が『自前の思想』で取り上げた、水俣の石牟礼道子さんもそうした方だったと思ったわけです。目前で、当時「奇病」と呼ばれるような事態が生じてきたときに、それを詩や文学として取り上げる「責任」なんてなかった。けれどもそこで、好むと好まざるとに関わらず猫のことが気になって出かけて行ったら、そこで問題と出会ってしまった。出会って、巻き込まれて、応答した結果が、『苦海浄土-わが水俣病』となったり、その後の石牟礼文学として結実したりしてゆくわけですが、何も最初から現在のように環境人文学なんて枠組みがあったわけではないのです。
ジャンルはそうした応答の結果として、事後的に生成してきた。ところがそうして評価が定まってくると、最初からそういう人物だったかのように描かれてしまう。私が『自前の思想』で石牟礼さんを描き直したのは、生成的に見ればそんな風にはなっていない、ということでした。
清水 世の中に役立つことを直接的に目指す人類学の形は、これまでにもありました。例えば、2014年に山下晋司さんが編著し僕も論考を執筆している『公共人類学』という本があります。アメリカを中心に確立している“public anthropology”を取り上げていますが、人権・教育・医療・災害などの分野で人類学を直接的に役立てようとする試みです。
しかしそのことを遠くから眺めていると、アメリカでは社会に直接役立たない学問は評価されず、学生の関心や人気が集まらず、学術予算が削られるなどの不利益を被りやすい。だから、人類学を延命させるために表面的なモデルチェンジを行っているように僕には見えてしまいます。
人類学はフィールドワークの現場から始まります。ですから応答の人類学では、切実なリアリテイを感じる現地現場からの友人知人の呼びかけに応える「応答性」や「応答力」という概念を人類学に導入することで、それとは異なる新たな人類学のやり方にチャレンジしたかったんです。
飯嶋さんも言っていたように、応答の人類学とは、責任という強い言葉ではなく「受け応え」や「やりとり」という意味で「応答」という語を用いる。つまりresponsibility を “Responce-ability”──「現実に応える能力」ーに読み替えること。社会的責任や責務としては一般化できなくとも、個別具体的な現場に向き合い、誰かの問題を一緒に考えたり、当事者が気づかない外部の視点を提示したり、余計なおせっかいと嫌がられたり……そうした行動を起こすことが大切だと思うんです。
そもそも人類学者は招待されてフィールドワークを始めるわけでありません。いろいろな伝手を頼って勝手に押しかけてゆくわけです。「招かれていない」「招かれざる」客として、居候のような負い目や後ろめたさを誰でも感じていると思います。そのことについての落とし前の付け方というか仁義の切り方があるだろうと個人的に思っています。
北ルソン・コルディリエラ山地のイフガオ州バナウエ郡ウハ村で新年を祝い、地酒を飲みながら歓談する清水さん。住民主導の植林・文化復興のリーダーのロペス・ナウヤック氏(右)と、彼の運動と言動をドキュメンタリー映画で20年あまりにわたって記録し続けるキッドラット・タヒミック氏(中)。キッドラットはナショナル・アーティストで、「500年の航海」で第65回(2015)ベルリン国際映画祭カリガリ賞受賞(2016年1月2日)
身の回りにも、テクストにも「現場」はある
──責任を「応答」に読み替えることで、人類学と社会の接点が生まれるのですね。
清水 そうですね、そもそも人類学は、欧州や米国からの輸入品です。日本ではもともと「民俗学」が存在していましたし、戦前からドイツの「民族学」が紹介され、本書で取り上げている岡正雄さんはドイツに長く留学しています。
戦後に文化人類学という学問が入ってきて東大に学科が設置されたのは、米軍の意向があったと聞いたことがあります。日本が戦争に突き進んだのは文化相対主義の考え方や異文化理解の仕方をよく知らなかったからだ、自文化中心の狭い思考に絡めとられていたからだ、と考えたようです。文化人類学が日本に紹介されたのは、敗戦とアメリカの力ゆえと言えそうです。
けれどもそれは実は、明治の文明開花の頃からの、舶来の物品と思想をありがたがる伝統に根ざしてもいると思います。日本の多くの知識人は、「虎の威を借る狐」的に、欧米で流行している理論や先端研究を「どうだ」と紹介して自分の知識や頭脳を誇ることを繰り返してきたわけです。借り物ではなく自分の足で立って自分の頭で考える。“自前の”という言葉には、そんな自己批判の意味も込められています。
──「自前の思想」は、学問としての伝統を重視しがちな人類学に「現場」を取り戻そうとする営み、といえるかもしれません。
飯嶋 そうですね。僕たちは狭い意味での人類学のフィールドワークという言葉の意味とは区別するため、意図的に「現場」という言葉を使っています。
清水 そのとおりです。「現場」という言葉は、そこに対処すべき問題があるところということです。そして僕のフィリピンでの調査のように、仕事や研究だけでなく、個人的な関わりや体験、思い出まで含めて考えることも大事でしょうね。従来それは調査の余白や外部として考えられてきましたが、それは客観的で実証的な報告であることを装うことを邪魔するノイズとされていたからでしょう。けれども、そうした個人的な関わりや経験も含めてフィールドワークだと捉えることができるし、すべきだと思います。
どんなコミュニティーでも、家族・親族ネットワークや政治的利害に沿った派閥があります。その中のどのネットワークやグループの近くに身を置いて当該社会を見ていたか、手の内を明らかにしたほうがより「客観的」な報告になると思います。何らかの問題がある現場で、当事者たちがそれに関わり立ち向かっている日常を、外からの調査者も巻き込まれながら一緒になって考え行動してゆく。そんなフィールドワークもありなんだと考えればいいし、その際に嘘や隠しごとはしないほうがいいに決まっています。
飯嶋 大学での文化人類学の伝統的な手順では、調査地としてのフィールドがあり、ホームに帰ってきたら学会で発表し、それらをエスノグラフィーとして刊行することになっています。しかし、本来は伝統的に「調査地」と呼ばれる場所だけではなく、戻ってきた自分たちが住んでいる身の回りも現場という意味でのフィールドになりうるはず。極端な話、対話が起こる場所はどこでも「現場」になりうるとすら言えるでしょう。『自前の思想』で、中根千枝さんの行政とのやり取りを取り上げたり、川喜田二郎の発想法(KJ法)や移動大学のやり方、宮本常一さんの観光文化研究所での若者の育て方を取り上げてもらったりしたのには、そういう意味もあるんです。
どこでも「現場」になりうると考えられないのは、大学や学会が人類学者を教育として再生産しようと思っているからではないでしょうか。アフリカやアジア、南米、太平洋の島々などは、研究者がフィールドを共有し、徒弟関係を作りながら調査を進めていきます。それが学派とか学会という営みになるわけです。こうした仕組みは人類学者を生み出すための教育制度という側面も大きい。ですがそれよりも、もっと身近な、僕たちが直面する「現場」に目を向けるべきではないかと思ったわけです。
──人類学のようにわかりやすい「現場」が存在しない学問、たとえばテクストや史料を読み解くことが主務である哲学や歴史学においても、「自前の思想」は立ち上がるのでしょうか?
飯嶋 全てのテクストには、それが生まれるに至った「現場」があるはずですよね。テクストだって、人間が生きる過程の一部が固着したものであるわけですから。人文学という世界では、テクストばかりが研究対象に見えてしまうかもしれませんが、あらゆるテクストにはそれが生まれた「現場」があるし、テクストへの対峙の仕方が「現場」にすることもあるわけで、実際の現場は、人間が生きる所に、至る所にある。
清水 人類学においても、テクストと現場は相互参照的になるんですよね。まずは先行研究や理論、概念を文献で調べて事前に知識を得ておく。そして、フィールドワークではその理論や概念の適用を試みて、うまく理解が深まったり、逆に理論や定説が当てはまらない現実が見えてきたりします。テクストと現場とがお互いを照らし出すことで、細部がよく見えるようになり、深く理解できるようになるのです。
大切なのは、テクストと現場を往還すること。そう考えれば、どんな学問分野においても、「自前の思想」を立ち上げていけるはずです。
研究者は「呼ばれればどこでも踊る芸者」にならなければいけない
──「現場」から立ち上がる「自前の思想」を、より多くの人々が実践していけるようにするためには、どうすればいいでしょうか?
飯嶋 まずは「学会で既に存在する用語を追うゲームに終わりはない」という意識を持つことでしょうか。文献をいくら追ってもゴールには達しない。複雑な時代を掴んで語る言葉は、どこまで勉強したって見つからないんです。そのときに、僕たちは「大切なのは目の前にある現場だ」と考えて、腹をくくって居直らなくちゃいけない瞬間が来るのだと思います。
その参考になる先人は既にたくさんいます。自前の思想は“鎖国の思想”ではないので、もし自前の思想の海外篇ができれば取り上げたいと思っていた人物も多く、グレゴリー・ベイトソンやユージン・ジェンドリンらの実践と並び、アラン・トゥレーヌの研究実践もその1つでした。彼は「新しい社会運動」の概念で有名で、1960〜80年代にフランスなどで起こっていたフェミニズムやエコロジー運動のリーダーを自分のゼミに呼んで議論をしていました。自分たちはこの時代にいかなる問題に直面しているのか、どうすれば変えられるか。ゼミではそうした実際の問題について、現場の第一線に立つ人と探っていく。これはすごい知恵ですし、現代でこそやるべきプロジェクトかもしれません。九州大学の清水ゼミは、そんな雰囲気だったとも聞いています。
また、創造的な退却も重要だと思います。僕は1969年生まれで、バブル全盛期を20歳頃に東京で過ごしています。そこで感じたのは、「右から左に情報を流すだけの作業に一生追われてしまう」という感覚です。他の人よりも少し早く情報を仕入れられたかどうかで評価が決まる環境だと、ずっと情報を追ってしまう。でも、そうしていると流され続けてしまうので、まずは自分の足場をつくらなくてはと感じて、そうした情報の洪水状態から意識的に距離をおける環境に身を置いたんです。そうした経験があったので、石牟礼さんが『苦海浄土』を執筆する過程で、水俣から離れた仕事をしていたことの意味にも着目できたわけです。
清水 産業革命後の社会の進歩や成長は、やはり効率と生産性の追求によって生まれています。それに流されてしまうと、地に足がついた真っ当な暮らしにはならない。もっと意識して自分の身の丈に合った暮らしを営まなければ、現場に応答できる思想は育まれないと思います。
実は『自前の思想』には、山口昌男さんが知識人や文筆業の責務について書き下ろした原稿が掲載されるはずでした。残念ながら事情により掲載ができなかったのですが、これは彼の後期作品である『「敗者」の精神史』と『「挫折」の昭和史』を読み解き、彼の思想を学びなおす試みでもありました。この二つの書籍は、メインストリームにならなかった昭和の知識人や運動家を掘り起こして、彼らが夢見たもう一つの可能な社会のあり方に光を当てようとしたものです。高度経済成長やバブル経済のような大量生産・大量消費型社会の延長ではない、別の日本の姿がありえたかもしれないし、これから作ってゆくことができるのかもしれません。そんな可能性を、人類学やフィールドワークは提示できるのだと思います。そうしたことを含めて「自前の思想」という次第です。
飯嶋 清水さんはこれまで何度も「教育は金のため、研究は見栄のため。呼ばれれば、我々はどこでも踊る芸者にならなければいけない」とおっしゃってきましたよね。「教育は金」というのは、教育をしてお給料をもらっているのだから、その給料分はしっかり教育で頑張る、という意味ですよね。先ほど、私が教育制度を相対化するようなことを言いましたが、教室での教育も対峙の仕方次第では、まさに現場ということになるんですよね。
つまり、研究者である我々がすべきことはシンプルです。いま自分が出会ってしまって、最初は巻き込まれただけのように感じるかもしれないけれど、自分の目の前にある「現場」を捉えて、そこから時代を考えていけばいい。いま目の前にいる相手に、自分がどうすれば寄与できるかを考え続けていればいい。あるいは、社会の急速な流れから一度退却したとしても、応答し続けていければいい。それこそが、「自前の思想」を実践するということなのだと思います。
Text by Tetsuhiro Ishida, Interview&Edit by Masaki Koike
デサイロでは、ニュースレターやTwitter、Instagramなどを利用して、プロジェクトに関わる情報を継続的に発信中。Discordを用いて研究者の方々が集うコミュニティも運営しています。ご興味のある方はニュースレターの登録や各SNSのフォロー、あるいはDiscordにぜひご参加ください。
■Discord:https://discord.gg/ebvYmtcm5P
■Twitter:https://twitter.com/desilo_jp
■Instagram:https://www.instagram.com/desilo_jp/
■バックナンバー:
「自前の思想」が立ち現れていく学際的な場を目指して──2023年、デサイロの展望
人文・社会科学の研究者に「大学の常勤職員」以外の選択肢を。アカデミア外にも広がるキャリアの可能性を考える:磯野真穂 × 藤嶋陽子 × 岡原正幸