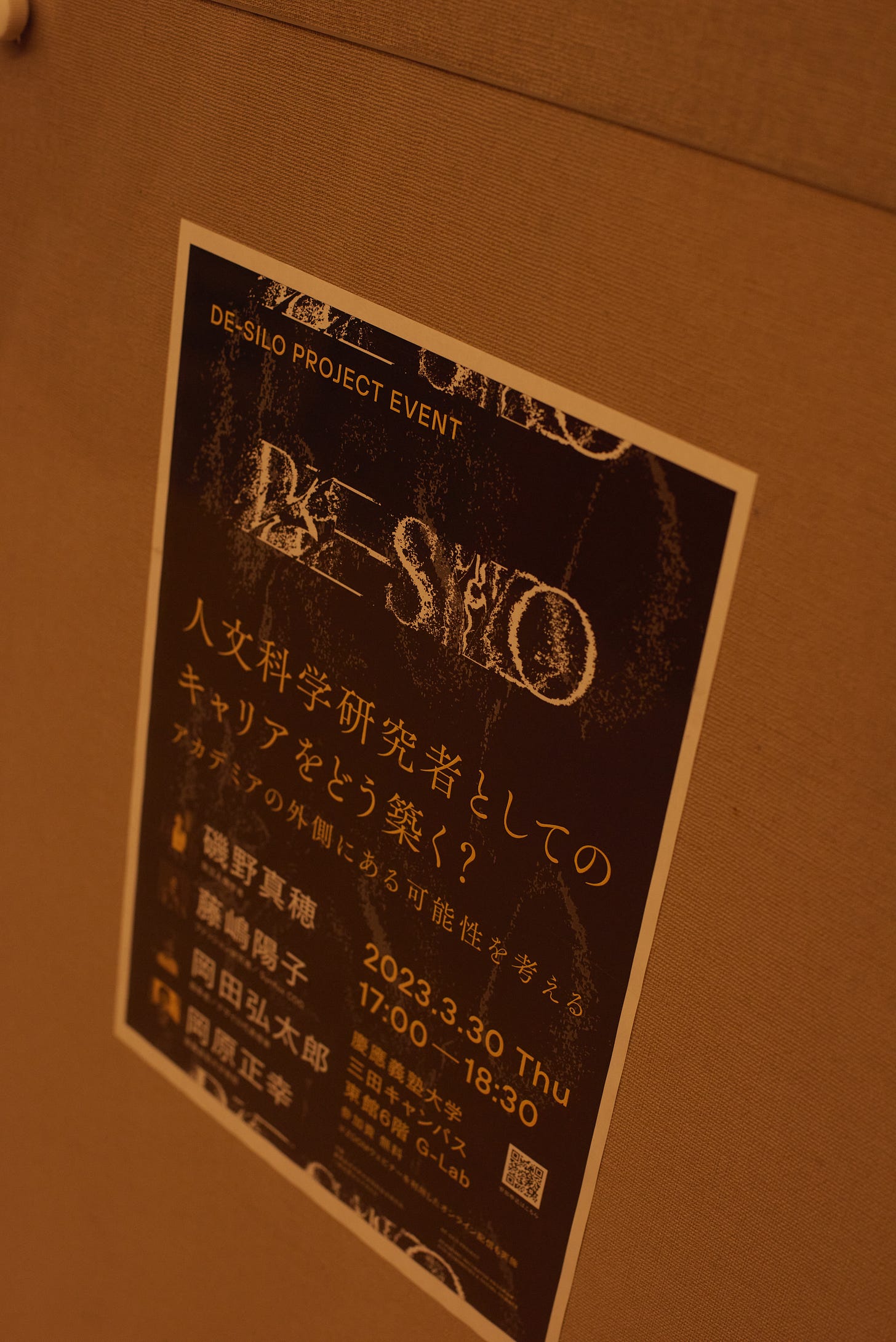人文・社会科学の研究者に「大学の常勤職員」以外の選択肢を。アカデミア外にも広がるキャリアの可能性を考える:磯野真穂 × 藤嶋陽子 × 岡原正幸
「アカデミア、特に人文・社会科学の世界は、研究者が大学の常勤職員であることが前提となってデザインされています。常勤職になると生活は安定し、研究費も取りやすくなるけれど、そのトラックに乗れないと生活自体が不安定になる──ずいぶんな格差社会です」
独立研究者として活動する人類学者であり、デサイロの理事も務める磯野真穂さんは、人文・社会科学の現状をこう表現しました。
昨今は人文・社会科学の知を活かした事業を展開する企業や、大学から独立した在野での研究など、大学のポストにとらわれない実践が増えています。とはいえ、大学外で活動する研究者のキャリアを支える新しい仕組みやビジネスモデルは、いまなお模索中と言えるでしょう。
これからの人文・社会科学領域の研究者のキャリアデザインについて考えるべく、慶應義塾大学大学院社会学研究科と、人文・社会科学領域の研究者を支援するアカデミックインキュベーターとして活動する一般社団法人デサイロの共催でトークイベントを開催。
登壇したのは、先に発言を紹介した人類学者の磯野さん、立命館大学産業社会学部准教授として教鞭をとりながら、スペキュラティブファッションラボラトリーであるSynflux株式会社で執行役員COOも務めるファッション研究者の藤嶋陽子さん、慶應義塾大学教授/大学院社会学研究科委員長を務めていた(2023年3月31日退任)社会学者の岡原正幸さんです。モデレーターは、デサイロ代表理事/編集者の岡田弘太郎が務めました。
研究者が生み出す価値の出力先を、大学や学会の外にもひらいていくことで、人文・社会科学の研究者のキャリアの選択肢はいかにして広がっていくのでしょうか?
「独立研究者」という選択
イベントに登壇した3名の研究者はそれぞれ、研究を通じて見えてきた知を、大学の外にもひらく活動を行ってきました。
まず1人目は、大学教員を経て、現在は独立研究者として活動する磯野真穂さん。オンライン講座や一般向けワークショップを通じて、医療人類学を軸に、摂食障害、医療パニックといった研究領域の知を社会に広くひらく活動を重ねています。
磯野「私自身は大学での就職がうまくいかず、本当に苦労して、結局はそれを諦めた人間です。大学でのポストが得られない、あるいは得られるかどうか不安に思っていらっしゃる方に、私のお話が参考になれば良いなと思っています」
磯野真穂(いその・まほ)
人類学者。専門は文化人類学・医療人類学。博士(文学)。早稲田大学文化構想学部助教、国際医療福祉大学大学院准教授を経て2020年より独立。身体と社会の繋がりを考えるメディア「からだのシューレ」にてワークショップ、読書会、新しい学びの可能性を探るメディア「FILTR」にて人類学のオンライン講座を開講。著書に『他者と生きるーリスク・病い・死をめぐる人類学』(集英社新書)『なぜふつうに食べられないのか――拒食と過食の文化人類学』(春秋社)、『医療者が語る答えなき世界――「いのちの守り人」の人類学』(ちくま新書)、『ダイエット幻想――やせること、愛されること』(ちくまプリマ―新書)、宮野真生子との共著に『急に具合が悪くなる』(晶文社)などがある。(オフィシャルサイト:www.mahoisono.com )
「公募」または「コネクション(人脈)」で得られることが多いという、大学の教員ポジション。「10年教員をやってきて、自分はコネクションで引っ張られる人間ではないとわかった」と語る磯野さんは、国際医療福祉大学大学院での准教授としての任期が終了した2020年春、公募に絞ってポジションを探していたといいます。
磯野「求められるポジションと自身の研究してきたものがしっかり重なっていて、(合格の)確度が高いと思えた公募に申し込んでも、採用してもらえませんでした。そして受かった方を見ると、研究テーマより、コネクションが重視されたことが明白。そういったことが何回かありました。
そのとき、思ったんです。誰だって働きたい人と働きたいだろうから、コネクションで採用することは否定しない。でもそれだったら、段ボール一箱になるような書類を出させたり、模擬授業させたりする公募スタイルはやめてよ、と。例えば、一次選考では、これが非常に厄介なのですが、 "個々の大学指定のフォーマット”に沿った履歴書と業績書、さらに抱負を書いたエッセイに、想定シラバス2つ──これもまた大学指定のフォーマット──などをそれぞれ10部刷って提出し、二次選考では朝5時半に家を出て模擬授業をして……といったように、公募に申し込むことには、多大な労力がかかるんです。
『多様性』を称揚し、『自分で考える人材を作ろう』と謳う大学がその有様で、同世代の研究者の中にも、この公募プロセスに価値を見出している人がいる。そうした状況を改めて目の当たりにしたとき、『この書類作りを一生懸命やるのは、もう無理だな』と思ってしまいました」
そうして独立研究者となることを決めた磯野さん。独立してからは、「授業」を外にひらくことに積極的に取り組みました。
磯野「人類学はすごく面白い、みんなもっと興味を持ってくれるはず……そう思ってやっていた大学の授業を、オンライン講座という形で外に出したら、年間約300の人が来てくれるようになったんです。
そこから得られる収入が生活のベースになっているのはもちろん、講座での縁がきっかけで、さまざまな方に声をかけていただけるようにもなりました。大学の外にも人類学に関心を持っている人はたくさんいて、そういう人たち繋がることができたからこそ、独立研究者としてなんとかやれているのだと思います」
「大学」と「テクノロジー企業」という二足のわらじ
2人目は、ファッション研究者の藤嶋陽子さん。彼女はアカデミアと民間、2つのフィールドで、実務と研究を両立する道を模索してきました。
学部卒業後、「ファッションデザイナーになりたい」という夢を持って英国でファッションデザインを学んだという藤嶋さん。帰国後に「ファッションが個人や社会に対して生み出す価値」の研究をしたいと考え、東京大学大学院に進学しました。
当時、研究者以外の道のキャリアを切りひらくことを大きく掲げていた、博士課程教育リーディングプログラムに参加。学際的な学び、生活費となる助成金の提供、大学と民間企業それぞれからのメンターアサイン、インターンへの参加機会の提供……このプログラムが提供してくれたものが、現在のキャリアの土台になったといます。
藤嶋陽子(ふじしま・ようこ)
1988年生まれ。ファッション研究者。東京大学大学院学際情報学府博士課程満期退学。University of the Arts London(Central Saint Martins)にてファッションデザインを学んだ後、ファッションとメディア、日本のファッション産業史を専門に研究。 2019年に株式会社ZOZOテクノロジーズ入社。ZOZO研究所リサーチサイエンティストを経て、「Fashion Tech News」編集長に就任。経済産業省「これからのファッションを考える研究会 ファッション未来研究会」委員。2022年よりSynfluxに参画、明治大学商学部特任講師、理化学研究所革新知能統合研究センター客員研究員を兼務。編著に『クリティカル・ワード ファッションスタディーズ』(フィルムアート社、2022)、共著に『ソーシャルメディア・スタディーズ』(北樹出版、2021)、共訳に『ファッションと哲学』(フィルムアート、2018)など。
そんな藤嶋さんが民間のキャリアに足を踏み入れたのは、模索し悩み続けていた就職活動の時期でした。
藤嶋「日本学術振興会の特別研究員の身分の終わりを迎え、強く思い悩んでいた時期がありました。そんな折、Twitterで『ZOZO研究所さん、文系の研究者も雇ってください……』とつぶやいたところ、なんとZOZO研究所のメンバーの方からリプライをいただいたんです。それでオフィス見学に誘われたのが、人生の転機となりました」
そうしてZOZOテクノロジーズ(現:ZOZO NEXT)のZOZO研究所に参画したのが、2019年。ファッションテックという領域を社会に発信し、共に未来を考える仲間を増やすべく、主にメディアの立ち上げや編集・発信を手がけました。
また若手研究者として大学での教育や、同分野の研究者との繋がりを重視する藤嶋さんにとっては、何かしらのかたちで大学でのポジションを持ち続けることも重要だったといいます。
藤嶋「私は研究者であり続けたいと思っていたので、実務で編集やメディアの仕事が多くなっていく中での焦りもありました。ですから業務時間外を使って、意識的に論文を書いたり非常勤講師をしたりして、研究者としての活動も行っていました。
次世代の研究者を育成したり、一緒に研究する人を見つけたり、あるいは研究のコミュニティを広げたり……これらは民間での活動だけでは難しいということもあり、大学に何らかの形で関わることは大切にしたいとずっと思っていました」
2022年にはZOZO NEXTを退職し、スペキュラティブファッションラボラトリー・SynfluxにResearch Leadとして参画、その後COO(最高執行責任者)にも就任ました。主にバーチャルファッションやサステナブルファッションに関連したリサーチ、批評や言論の場としてのイベントやメディアの企画などを手がけています。
その傍ら、明治大学での特任講師なども経て、2023年春には立命館大学産業社会学部准教授に就任。実務と研究をつなげていく道を模索しつつも、大学教員として、大学と民間の両方で活動を続けています。
アートを通じて、論文“以外”のアウトプットを模索
3人目は、2023年3月まで慶應義塾大学教授/大学院社会学研究科委員長を務めていた社会学者の岡原正幸さん。岡原さんは研究者としてのキャリアの中で、アカデミアの外に対するさまざまな活動を重ねてきました。
三田キャンパスの近くの一軒家を借りて独自に運営したフリースペース「三田の家」では、大人から子どもまで、学内外のさまざまなバックグラウンドの人々と共にワークショップや講演会を実施。2013年には三田の家で、日本社会学会と同時開催で「オルタナティブ社会学会」という実験的なイベントも開催しました。
また岡原さんは、「アートベース・リサーチ」(ABR)と呼ばれる、論文ではなく演劇やダンスなどのアート・パフォーマンスとして社会科学のアウトプットを発表する活動にも、10年以上取り組んでいます。パフォーマンスを学会に持ち込んだり、海外の大学と連携したパフォーマンスを実施したりと、アカデミズムをより開放的にすることを目指して活動に取り組んできました。
岡原「アートという表現手法には、複数性のある解釈を許し、ただ一つの真理に局限されない点に、社会学との親和性の高さがあると思っています。特に質的な研究を行う人文・社会科学の知は、自然科学の実証的な知とは性質が異なるということも背景にあるでしょう。
1980年代のポストモダニズム以降、人文学の前には、いかにして自身の“知の確からしさ”を普遍的な真理として語れるのかという課題が立ちはだかってきました。その中でアートというのは、さまざまな解釈をフラットに議論する──たとえるならば、ソクラテス・プラトン的な対話・戯曲的なものを取り戻す試みでもあると考えています」
岡原正幸(おかはら・まさゆき)
1957年生まれ。慶應義塾大学文学部教授、大学院社会学研究科委員長、3月31日に慶應義塾大学を定年退職。専門は、感情社会学、障害学、アートベース・リサーチで、パフォーマンスアーティストとしても活動。2006-2013年には「三田の家」というコモンハウスを三田キャンパス付近で運営、2015年からはKeio ABRというラボを大学院研究室で主宰、2021年からは博士人材育成プログラム(Keio Spring)としてアート、コミュニティデザイン、映像制作のワークショップを13研究科博士院生に提供、2022年からは「協生カフェ(三田キャンパスにLGBTQの人も安心できる居場所)」WGとしても活動。退職後はABRによるレジリエンス、エンパワーメントをゴールにする社会実装系の法人(合同会社岡原ゼミ)を設立。著書として『生の技法 家と施設を出て暮らす障害者の社会学』『ホモ・アフェクトス』『黒板とワイン もうひとつの学び場〈三田の家〉』『感情資本主義に生まれて』『アート・ライフ・社会学』などがある。
“非常勤頼み”の構造が生み出す歪み
イベントの後半では、それぞれの研究や活動を踏まえたディスカッションが行われました。まず議題にのぼったのが、人文・社会科学系の研究者が“食べていく”ことを難しくさせる、既存のアカデミアの構造的課題です。
1990年代の後半、文科省の「大学院重点化」の呼び声のもとで大学院生・研究者を増やす施策が実施された一方、大学院生にとっての「出口」に対する施策や、若手研究者の研究を持続的なものにするための対策は十分に取られてきていないと岡原さんは指摘します。
2021年にはJST(国立研究開発法人 科学技術振興機構)による取り組みとして、博士過程の学生の生活を支えるために、院生に毎月20万円強の生活費、30万円から100万円の研究費を助成する「次世代研究者挑戦的研究プログラム(SPRING)」も開始されましたが、まだまだ課題は山積みだと言います。
岡原「(SPRINGを)実際にやってみて、3年間だけの支援では、院生の不安を打ち消すのには不十分だとわかりました。たとえばシンクタンクをつくって院生をインターンとして雇用するなど、アカデミックポストに就くまで食いつなげるようなシステムを構築しなければ、優秀な人材は大学外に出ていってしまうでしょう」
さらに磯野さんからは、大学の授業の多くは非常勤講師で成り立っており、その給与・報酬が非常に低いことが、構造的な問題を生み出しているという指摘もありました。
磯野「私のオンライン講座と同じ内容を大学の非常勤講師として授業にしたら、そこから得られる収入は総額50万程度になってしまい、一気に生活が困窮するでしょう。大学はものすごく安い給料の非常勤講師に依存することで、組織を成り立たせている側面がある。
多くの非常勤は待遇の悪さを感じていると思いますが、表立って声は上げられません。そこに文句を言ったら、就職できなくなる可能性が高いでしょう。また私も任期付きながら専任教員側だったからわかりますが、実際教員になると、非常勤の待遇の悪さというところに目が行かなくなって、他のことに追われてしまう。しかし本当は、非常勤講師の給与を、たとえば今の3倍ほどにする必要があると思います」
大学の外で芽吹く、人文系研究者の活路
膨大な書類を提出させながら実際は形ばかりの公募や、非常勤などの構造的問題に疲れてしまった磯野さんは、大学の外で生きる可能性に思い切って賭けてみることにしました。
そもそも磯野さんは大学に勤めていた頃から、大学外の活動にチャレンジしていたといいます。その代表例が、2016年から開催してきた「からだのシューレ」というイベント。摂食障害について研究していたバックグラウンドを活かし、食べ物と身体について医学や心理学以外の視点から考える活動として始めたもので、これまでの参加者は800人にもなるといいます。
こうした基盤が独立後も活きたからか、記事前半でも少し触れたように、「FILTR(フィルター)」というプラットフォームで開講しているオンライン講座では、最初に開催した文化人類学の入門講座『他者と関わる』という講座や、次に開いたエスノグラフィーのインタビュー手法を伝える『聞く力を伸ばす』という講座にそれぞれ300人近い申し込みが集まりました。
磯野「自分が大学でやっていたことをそのまま外に開放すれば、人が来てくれる。その実感をこの3年間で得られたのは大きな収穫でした。研究を大学の外側の人に面白いと思ってもらえる形に整形したら、意外と反応がある。
とはいえ大学の組織は硬直化してしまっているので、すぐに大きく変わることはなかなか難しいでしょう。ですから大学の教員が唯一の生存方法であるというある種の固定観念を揺るがし、大学にいてもいなくても、人文知を使って面白い人生を生きられるという一つのモデルを示せたら良いなと思っています」
重ねて岡原さんも、人文学の研究を「売ってはいけないもの」とする風潮に異を唱えます。
岡原「下手をすると、人文系の知は売れない、という風に思わされています。学生からも『ゼミでお金儲けをしてもいいんですか?』という質問が出るほどに、『売ってはいけない』という規範がなぜか作られている。しかし、この文化は断ち切る必要があると思います」
岡原さん自身も、定年退職を迎える2023年3月以降は、これまでの研究と実践を活かして、社会学を社会実装するための法人を設立するといいます。
岡原「研究としてやってきた『ライフヒストリーの聞き取り』をABRとして作品化する中で、その行為が持つ力が社会に対して大きな影響を持つことに気付き、法人を設立することにしたんです。人文系の学問の知の中にもお金になるものはたくさんあり、売り方一つだと思っています。売り方をサポートできるプラットフォームを大学が作ってあげれば、若手の研究者の面白いものがもっと売れるかもしれない。
若手研究者をちゃんと雇用してサポートし、彼らの創った知を大学の資産としても蓄積していく。若手研究者のキャリアを持続的なものにするためには、そのように大学組織の構造ごと変える必要があると思っています」
企業に眠る、人文知が求められる余地
一方で、「査読つき論文」や「理論的な貢献」といったアカデミア内での業績づくりと、社会に知をひらいていく活動との間に乖離がある、という難しさも指摘されました。
藤嶋「研究論文を書くときと、より広い読者に向けた柔らかい文章を書くときとでは、モードが全然違います。院生時代に『ライトな書き物を始めると論文を書けなくなるよ』と言われたこともありますが、自身の研究を深めてアカデミアでの業績を上げていくことと、その知を社会へひらくこととの両立は、ずっと自分の課題としてありますね」
磯野「確かに、両方を書くのは時間的に難しい部分はありますが、それは大学にいても色々な業務に追われたりもするのであまり変わらないような気がします。また、一般の人にわかりやすいものを書いても学問としての貢献がない、という批判が来ることもありますよね。あくまでも、何をゴールとするかという方向性の違いの問題でしかないと思うのですが」
ただ藤嶋さんは、企業内で研究者として活動する中で、さまざまなフェーズで「人文系のバックグラウンドの人が入り込む余地がある」と感じた場面があったと言います。
藤嶋「組織運営や人材開発、リサーチや新規開発など、企業でも人文・社会科学系の知が必要とされる場面は多々あります。ただ、現状の企業の雇用システムだと、それがポジションとなって現れない。私は、ファッションというわかりやすいドメインがあったために入り込めた部分がありますが、こういったポジションの多くはパッケージ化されていないんです。
ですから今後は研究と同時に、研究の延長線上で実践に入り込んでいけるような活動やパッケージ化されたサービスが作られていくと、大学も企業も相互により豊かになるのではないでしょうか」
磯野さんも、さまざまな民間企業と関わる中で、人文知とビジネスとのシナジーを感じる場面が多々あったといいます。
磯野「NPOや企業の方から、(新サービスの創出時など)一番最初のところで相談されることが時々あります。意外かもしれませんが、墓石や遊具に関する相談を受けたり。特に墓石は、人類学が『死』という概念を扱う学問なので、大きなシナジーを感じました。
オンライン講座についても、コンサル、デザイナー、メディア、医療関係の方といったさまざまな職業の方から、『授業で得たものが仕事に活きている』と言われることは多いですね」
実際、世界的なデザイン・ファームのIDEOのゼネラル・マネジャーであるトム・ケリーらによって書かれた『イノベーションの達人!―発想する会社をつくる10の人材』(早川書房, 2006)では、イノベーションを生み出す組織に必要な10の人材の一つに人類学者が挙げられています。また、デンマークのReD Associatesのように人文学の知見を起点にしたコンサルティングファームが出てきているほか、応用人類学など一部の人文系大学院では企業内でのインターンをフィールドワークの一環として取り入れるなど(参考)アカデミアと民間の協業も活発に起こっています。
3名によるトークからは、一般向け講座からアート、企業内研究者まで、人文・社会科学の知が社会と接続していくさまざまな選択肢が提示されました。「大学の常勤職員」以外の選択肢が出てくることが、研究者としてのキャリアデザインの柔軟性や多様性につながるのではないか──。そんな考えのもと、デサイロでは今後も引き続き、研究者のキャリアデザインを探求するためのリサーチやイベントを続けていきますので、ご関心のある方はニュースレターやSNSをフォローいただければ幸いです。
Text by Rina Horisawa, Photo by Shunsuke Imai, Edit by Masaki Koike
デサイロでは、ニュースレターやTwitter、Instagramなどを利用して、プロジェクトに関わる情報を継続的に発信中。Discordを用いて研究者の方々が集うコミュニティも運営しています。ご興味のある方はニュースレターの登録や各SNSのフォロー、あるいはDiscordにぜひご参加ください。
■ Discord:https://discord.gg/ebvYmtcm5P
■ Twitter:https://twitter.com/desilo_jp
■ Instagram:https://www.instagram.com/desilo_jp/
■バックナンバー: