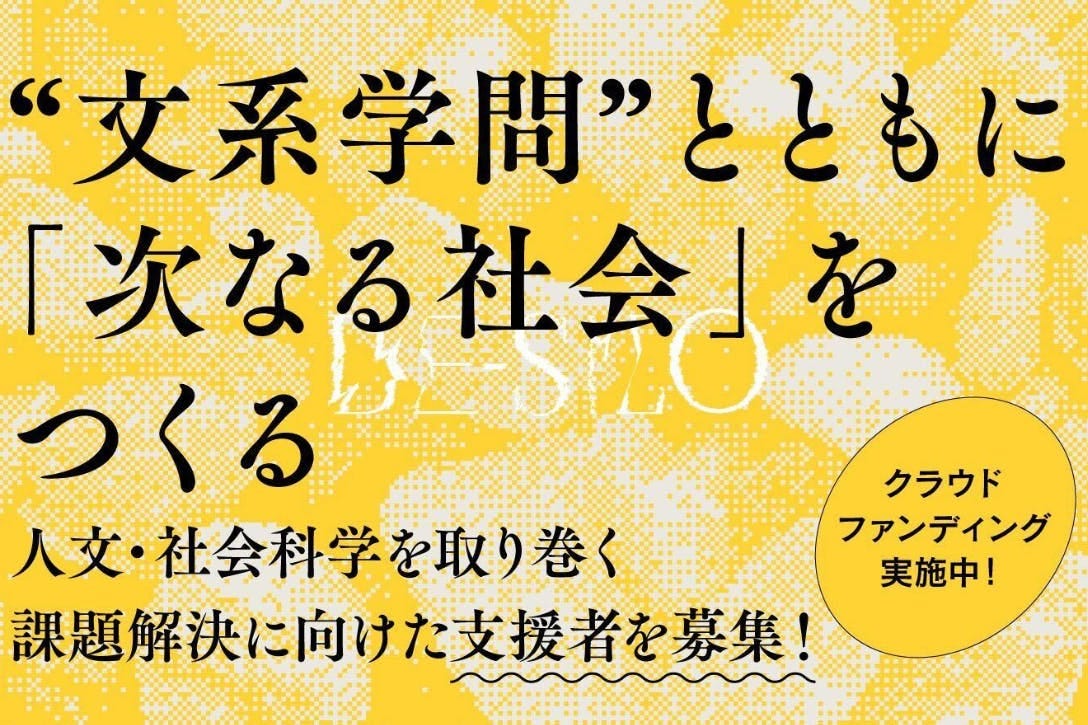人文・社会科学系研究の「産官学連携」はいかにして可能か?──研究者のキャリアデザインを"統合型モデル"から考える(前編)
人文・社会科学領域のキャリアは、研究者が大学の常勤職員であることが前提となっており、アカデミックポストに就けなければ、研究者としてのキャリアを持続可能にすることが難しい側面があります。
一方で、いま人文・社会科学系研究者のなかでも、新しい実践を始める方々が現れています。研究知を活かした起業や、大学から独立した在野研究など、大学のポストにとらわれない実践が増加。しかしながら、そうした大学外で活動する研究者のキャリアを支える新しい仕組みやビジネスモデルは、いまなお模索中だと言えるでしょう。
このようなアカデミアを取り巻く背景の中で、人文・社会科学領域の「産官学連携」という領域にいち早く着目し、研究と社会の往還の実践してきたのが南了太さんです。
2023年2月、南さんは文系学問の「産官学連携」について、6つの大学で15年以上実務に携わってきた知見をもとに体系化した著書『人文社会系産官学連携 社会に価値をもたらす知』を上梓。これまで理工・生物系の学問を中心に進められてきた産官学連携が、人文・社会科学領域でも十分に価値発揮できることを明示しています。
「何の役に立つのかわかりづらい」……そう言われつづけてきた人文・社会科学分野の“有用性”を明確化することで研究を社会に活かし、研究者がキャリアデザインを考える礎となる「人文社会系産官学連携」モデル。前編では、産官学連携の歴史から、理工・生物系産官学連携モデルが主流になった背景、人文社会系産官学連携を普及させる障壁となってきた実践の難しさについて南さんに論じていただきました。
南了太(みなみ・りょうた)
京都精華大学国際文化学部准教授。1980年、京都市生まれ。同志社大学大学院総合政策科学研究科 技術・革新的経営専攻修了。博士(技術・革新的経営)(博士論文「人文社会系産官学連携の普及と定着」)。
大学院博士前期課程修了後、経済産業省の外郭団体NEDO技術開発機構に入社、NEDOフェロー(若手産官学連携養成者)として同志社大学リエゾンオフィス・知的財産センターへ出向、産官学連携の推進に従事する。その後、金沢大学ティー・エル・オーで知財管理や特許ライセンス業務、京都大学産官学連携本部では組織対組織の産学連携や全学的な共同研究の推進、子会社「京大オリジナル株式会社」や複数大学の共同による「京都アカデミアフォーラムin丸の内」の企画・立ち上げ・運営および各種地域連携業務に携わる。2021年4月より現職。
研究・イノベーション学会広報担当理事。京都大学産官学連携本部研究員。金沢大学ティー・エル・オー技術移転コーディネーター。専門は産学連携論、公共政策、技術経営、地域社会学。
デサイロでは、人文・社会科学系の研究者がより持続的に活動できるエコシステムを生み出すために、「リサーチレポート」の制作を進めています。それに伴ってクラウドファンディングを実施しておりますので、ご興味のある方はぜひご支援ください。
※本寄稿を執筆した南了太さんにも、「人文・社会科学を取り巻く課題マップ」の制作に監修協力としてお力添えいただきました。
はじめに
好きなことを生業としている職業の人は社会的に報われない可能性が高い。芸術家や小説家、芸人、ミュージシャン、スポーツ選手、そして学者もそうである。一発逆転でベストセラーや世界初の発明などの可能性はあるが、稀である。
自らの喜びを得ることを仕事した以上、それ以外の社会的成功や資産の形成は、あれば望外の僥倖であり、当然のように望むことは間違っている。それが、こうした仕事について回る一種の倫理観である(村上 2000)(注1)。
それゆえこれらの人々には長年パトロンや篤志家、タニマチがサポートし、それが文化として発展してきた。例えば、ガリレオ・ガリレイはメディチ家などのパトロンに雇用してもらうために自身の能力をPRし、レオナルド・ダ・ヴィンチもミラノ公国の君主に必死に自身の研究の有用性をアピールしている。いつの時代も社会的承認からは逃れることができない。
今回のエッセーの問いは「人文社会系分野の知は、社会でどのように活用可能か」である。価値中立的な態度で真理の探究や現象の解明を求め、研究者自身が興味関心で学問を追究することを科学という。その行為自体何ら否定される訳ではない。ただ、この自己充足的な科学研究を維持することが難しい時代になっており、社会も寛容でなくなりつつある。知識が、ある特権者のものでなく、いつでもアクセス可能な中で、人文社会系分野の学者も自身の科学的関心のみならず、社会の中で、生み出された知がどのように活用可能かを考える時期にきていると考える。このことは外部と接触の少なかった大学の自治を見直す機会にもつながる。また、人文社会系研究者のキャリアデザインを考える際にも参考になるものである。
既に理工・生物系分野は産業界と連携を果たし様々な連携をしている。人文社会系分野もこれまでは書籍や新聞などのメディアを介して不特定多数の人々に新しい気づきを届けたり、一部では地域連携を通じて知の還元を行ってきた。さらに踏み込んで、これからは産業界との「連携」に着目し、新たな視点から人文社会系分野を切り拓いてみてはどうかというのが今回の提案である。
1.科学技術が支配する社会
連携について議論をする前に、科学技術について少しだけ触れておく。我々は科学と技術を一緒に捉えることが多いが、歴史的に振り返ると科学と技術は異なる概念である。科学は上記の通りだが、技術は役に立つことを価値とする。科学は価値中立的であるがゆえ本来役には立たない。性質の異なる両概念が産業革命以降結びつき、宗教を否定して科学技術として発展するのである。
科学が職業化されたのは1840年にイギリスのヒューエルが「scientist」という語を作ったことまで遡る。それまでは自然哲学者という用語であった。基本的に金持ち貴族が余暇の一環で様々な想像を巡らせ、宗教的解釈を知的活動へとつなげメタの視点で社会を認識していた。それが近代革命により、科学者が社会で役割を担うようになり狭い領域の職業団体を構成し、学会を作り、その団体特有の用語を使い、論文を生産し、閉鎖的になっていく。村上(2000)によると、知識の生産、蓄積、流通、消費、評価がすべて科学者の共同体専門家集団の内部で行われることになり、科学活動は集団の外部とほとんど一切繋がりがないままに進めることのできる営みであったのである。すなわちクライアントのいない状況が続いてきた。自己充足的な趣味(科学)が仕事につながる稀有な仕組みの中で、さらに大学自治に庇護され学者は存在してきた。
そして産業革命以後、科学と技術が急接近する。紡績や蒸気機関車の発展に伴い、差別されていた技術者もそれなりの地位を獲得していき、科学との結びつきはさらに強固になっていく。ここに19世紀から現在まで我々を拘束する科学技術中心の視点を見ることができる。やがてアメリカでは、科学と技術が国防の中でさらに強固に結びつき、マンハッタン計画で大学の研究が国策として重要性を増し、産官学連携が促進され、冷戦に対峙する道具として科学技術が重宝されて、科学技術が支配する世の中になっていく。
他方、日本では、明治以前支配していた概念は儒教の影響もあり「道」であった。それが明治時代以降、西周が「科学」という概念を西欧より持ち込み、科学と技術が一緒に導入され、西欧列強に抗うために文明開化・殖産興業・富国強兵がスローガンとなり、科学技術振興がなされた。その時代に活躍した人物として工部大学校を推進した工学教育の父スコットランド出身のヘンリー・ダイア―と山尾庸三がいる。彼らの推進の元、工学重視の教育がなされた。即戦力を育成するために、サンドイッチ方式によるインターンシップが推進された。最初の2年間は予備的な基礎教育に当て、次の2年間を専門教育として講義と多少の実地的応用、そして最後の2年間は実地での訓練という三段階構造であった。このような6年制教育課程を採用し、土木・機械・造家・電信・化学・冶金・採鉱の7学科からなる総合的な教育体制を整え、それが日本の工学の起源となる。これが教育面から見た日本の産官学連携の源流となる。工部大学校は東京大学工学部へ引き継がれ、世界初の工学部の誕生に至る。
こうして科学と技術は一貫のものとして捉えられるようになり、戦時中は国家総動員法が制定され、理工系人材の需要は急増した。その際に培われた軍事技術が戦後も引き継がれ、戦後は高度経済成長、「ジャパン・アズ・ナンバーワン」の時代を経て、1995年以降は科学技術基本法を契機にイノベーション政策へとつながる。いずれの時代も科学技術が存在感を示しこれまで日本を牽引してきた。それゆえ科学技術に裏付けられたモノづくり神話から脱却できていない点はあるものの、科学技術の成果の恩恵に我々は浴している。戦後から1970年まで人文社会系分野が時代をリードし、その夢を科学技術の専門家が実現してくれていたことや「思想の科学」や社会運動で存在感を示した時期もあったが、基本的には人文社会系・理系は異なる道を辿ったように思われる。
理工・生物系分野の場合は科学が技術と結びつき、産業利用や国策としての研究が存在感を増し、utilityな価値を発信しつつ、政府や企業に対して市民権を得ていった。こうしてクライアントの意向を踏まえた諸活動がなされてきた。それに対して人文社会系分野は出版やメディア等を介して人々に様々な気づきを与えることもあるが、現在ではSNSやYouTubeなど様々なメディアの出現に伴い、ただただ消費されるコンテンツになり果てた。大学進学率の向上に伴い、知識はある特権を有した人のものではなく、消費されるコンテンツとなっている。また、コンテンツの次は「デザイン思考」や「アート思考」などの思考法への関心が中心となり、巷には「・・・思考」といったものが大量に紹介されている。社会と積極的に関わり、クライアントの視線を意識した学者は常に開かれた知識を有し、クライアントと関わらない学者との差は大きく広がっているように思われる。最先端の知を生産しているかと思いきや、一昔前の情報しか持ち合わせていない場合も少なくない。
これが「いま私たちはどんな時代を生きているのか」に対する私の社会観である。
もちろんパトロンがいて、興味関心で研究できれば良いが、様々な知が複雑に絡まりながら、大きな物語も大きな理論も見当たらない中で、他に社会現象を理解し、人文社会系分野の知を捉え直す機会はないのか。大学の自治という言葉に安住し、外と関わりを持たないことが習慣化していないか。
このような背景から産官学連携の現象に着目をし、社会、経済、経営、科学技術などを構成要素とした複合体としての社会システムと、産業界・大学・政府・行政機関・地域の「連携」活動にも着目し、その相互作用も含めることで静的・動的な双方の視点から社会を考察することを目指すのが私の研究である。特に実践活動で様々なクライアントの考え方を知ることが、他者理解にもつながるものだと考える。
2.産官学連携とは
先ず、「連携」について定義をする。
辞書によると、連携は「互いに連絡をとり協力して物事を行うこと」である(大辞林)(注2)。さらに踏み込むと、「連携」は筆者の経験より以下の特徴があるように思われる。
(1)他者を必要とする。ゆえに一人でできる座学とは異なる。
(2)不特定多数の他者や世論ではなく、具体的な他者を必要とする。
(3)フィールドワークなどにみられる現象を記述する観察以外に、実践的な活動が求められる。
(4)クライアントとの相互作用が発生するためコミニケーション能力が欠かせない。
(5)クライアントの意向に沿ったアウトプットが求められるケースもある。
このように連携する際には、上記の科学者の共同体専門集団とは異なる姿勢が望まれる。
次に、産官学連携とは文字通り、異なるステークホルダーが連携を通じて様々な相乗効果を生み出すことである。産官学連携の現象は明治時代からあった。例えば、東芝もヤクルトも味の素も大学発の研究を活用し、スピンアウトした例である。大正時代も昭和時代も個別には事例が見られたが、制度的に大規模に推進されるようになったのは「科学技術基本法」(1995年成立・施行)以降である。5年毎に「科学技術基本計画」が制定され、重点分野に多額の投資がなされ、その枠組みの中で科学技術政策も文教政策も推進され、個々の大学の方向性も科研費などの公的資金も、教育制度も含まれ、実に巧妙なシステムが大学をはじめ社会を規定している。2006年に大学は教育、研究に加え社会貢献が使命として明記され、産官学連携や地域連携が大幅に推進され、体制整備に多くの資金が投入されるようになった。しっかりと準備してきた大学は現在の競争に打ち勝ち、感度の鈍い大学は衰退を辿る一方である。補助金を申請する際にも連携体制が整っているかを問われ、その体制にない大学は最初のゲートで振るい落とされる。さらに大学間のランキングもされ、優秀な研究者はより研究環境の良いところを望む。既に拙著(2023)(注3)では、平成時代の各種政策により大学が序列化され、大学運営が産官学連携活動に依存する形態を「産官学連携の体制化」と呼び、その変遷を明治時代から振り返った。
産官学連携は長らく科学技術振興の下、理工・生物系の尺度や思想のもとで推進されてきた。共同研究や受託研究、知的財産、ベンチャーなどである。理工・生物系分野の大学の科学研究が技術と結びつき、企業が開発し、イノベーションに繋がるというアメリカ発の思想が日本にも取り入れられ、この考え方が現在の産官学連携のみならず産業政策を支配している。産官学連携が発展する以前は、米国や日本の企業は、製造業を中心に長年リニアモデルを採用してきた。リニアモデルとは図表1「産官学連携の線形モデル」に示した通り、自前で基礎研究から応用研究、開発、生産、販売までの全工程を社内で完結するビジネスモデルである。
図表1 産官学連携の線形モデル
それが2000年代初頭からオープン・イノベ―ションの高まりを受け、大学やベンチャー企業と共同研究や技術移転、ベンチャーを通じて連携するなど、自前主義からの脱却がはかられるようになった。自前で様々な資源を抱えるよりも、連携を通じて相乗効果が期待されるという視点で、現在の産官学連携は、概ね下記の理工・生物系産官学連携モデルで表現できる。各大学は共同研究や技術移転、ベンチャー数をこぞって競い合い、産業利用の可能性のある研究に対して多額の投資がなされる。
図表2 理工・生物系産官学連携モデル
ゆえに現在、理工・生物系産官学連携モデルが主流であることに間違いないが、モノが飽和し新興国でも同じ品質の製品を作ることができるようになった現在では、従来のモデルでは対処ができなくなっている。工業社会から知識社会への変化の中で、理工・生物系分野以外の視点も取り入れなければ、多様な価値観を有する現代社会には対応できないのだ。このような多元的な価値の社会の中で、長年価値を追求してきた人文社会系分野の視点が期待されている。
例えば、自動運転の研究が世界で推進されているが、事故が起きた際にAIは倫理的な判断ができるのかという課題に対して、人文社会系分野の知の貢献が期待されている。2019年、イギリスのオクスフォード大学の人文科学センターのAI研究にアメリカの投資会社ブラックストーン社が1億5000万ドルを寄付した事例など、世界では人文社会系分野の視点を活用する動きが広がっている。未来社会を思い描くには、「リニアモデル」や「理工・生物系産官学連携モデル」では対応できず、長年価値の追求をしてきた人文社会系分野の知見が必要となる。供給側の論理に基づく大量生産・大量消費が難しくなれば、各国現地の人々の行動様式を理解した生産が必須となる。現地の人々の心理や文化を理解するためには、文化人類学や社会学、心理学の視点が必要である。ITを駆使し大量の情報をベースにプラットフォームを築くGoogleや、人々の直観に訴えかけるデザインで覇権をとったApple、ネットワーク社会の到来を予期し人々の関係性をビジネスに変えたFacebookなどは、技術を人の内面まで踏み込んで展開したことで今日の隆盛をなし得た。そこでは経済学や心理学、社会学的な視点が価値を持つが、スティーブ・ジョブズはそれを禅から学び、Googleは経済学者を役員に迎え事業を発展させるなど、文理の知見を統合した経営戦略を行っている。しかし、日本では、技術至上主義のもとビジネスモデルが変化に対応できていないように思われる。
3.人文社会系産官学連携の推進の制約条件
人文社会系分野の知の活用が望まれる一方、その推進が困難な状況を、以下では(1)制度的制約、(2)方法的制約、(3)体制的制約の3つの観点から考える。
その後、筆者が関与してきたいくつかの人文社会系産官学連携プロジェクトの事例を紹介する。
(1)制度的制約
同じ学問だからわざわざ文理の区分をする必要はないという声が聞かれる。しかしながら、我が国で文理の区分は明確にある。例えば、大学の進路選択の際や官僚制度における文官・技官の区分などである。既に明治時代の殖産興業で土木工業は技官、法務は文官と役割分担が行われ、官僚制度は人文社会系・理系の概念に大きな影響を与えた。1910年代には、文・理と2分類する表現が見られる。中等教育について定めた第2次高等学校令の第8条の「高等学校高等科ヲ分チテ文科及理科トス」という記述である。文科は法、経済、文学、理科は理、工、医という区分で、これ以降、大学入学試験の準備段階で、人文社会系志望・理科志望に2分する方式が定着していくようになる。さらに、産官学連携では、上述の「科学技術基本法」の第1条において、「この法律は、科学技術 (人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。) の振興に関する施策の基本となる事項を定め、科学技術の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより」との記載があり、長らく科学技術振興の中で人文社会系分野は除外されてきた。四半世紀経ち法律も改正され、現在では総合知等が求められているが、産官学連携のスタートラインにようやく人文社会系分野が立てたのである。
総合知という概念を打ち出したからといって、文理の区分は想像以上に根深いのである。それは、明治時代の科学技術振興思想まで遡ることができ、我々の文化の隅々にこびり付いている。
(2)方法的制約
玉井・宮田(2007)は、①共同研究、②委託(受託研究)、③ライセンシング、④コンソーシアム、⑤寄附研究・寄附講座、⑥コンサルティング(技術指導)、⑦起業、⑧人材交流・人材育成を産学連携の形態として挙げている。産学連携はこれまで、理工・生物系分野が強みを発揮する共同研究や受託研究、技術移転、大学発ベンチャーなど研究開発の文脈で語られてきた。その成果や各大学の実績は文部科学省が平成15年から毎年公表している「大学等における産学連携等実施状況について」で知ることができる。
左記の基準をベースにした理工・生物系産官学連携モデルは、「utility」に価値を置く。理工・生物系分野のシーズが産業利用を期待され、大学内でも外部資金の獲得が期待され、連携→外部資金獲得→スタッフの雇用/研究室体制整備→論文・特許の生産→就職先の確保→研究室のプレゼンス向上→大学ランキングの向上という正の循環を可能とし、大学にとっても、研究者にとっても、学生にとっても連携することの誘因条件が働く。理工・生物系分野の場合、自身の科学研究が技術に応用されるからスムーズである。さらに、研究室内ではチームで実験する体制が整っており、先行研究も先輩から伝承され、その枠内で行われた新しい発見は新規性にも進歩性にも寄与する。結果は数値化でき、人々も納得しやすい。従来Aだったが、Bという材料を加えることでAにも勝るCが発明された。このことは産業発展に寄与するといった具合である。
一方、人文社会系分野はこの枠組みとは相性が悪い。社会や人を対象にするから変数は多数あり、多元的な現実があり解釈はそれぞれである。別に大型の装置を買う訳でもスタッフを雇用する必要もないから研究費はかからない。論文作成もじっくり時間をかけ、大量の先行研究を読み、その中で自身の研究を位置付ける。新規性や立ち位置を明確にすることは得意だが、それが社会や産業とどう関わるかまではあまり考慮されない。勿論、政策提案などはあるが補足程度で書かれる程度である。ゆえに一人で行うから研究には時間もかかり、産業利用も不確かで、ますますクライアントの視点を取り入れない状況が続く。
先述の通り知識が常に消費され、思考法も飽和しつつある中で、人文社会系分野の意義をどのように主張すべきかについては大事な視点である。
(3)体制的制約
南(2019)(注5)は、様々な資料から人文社会系分野の状況を研究した。その結果、人文社会系分野の共同研究金額件数は全体の約2%であった。日本の公的機関における研究者の内、人文社会系分野の研究者は約3%で、企業における人文社会系分野の研究者は1.3%であった。また、大学における人文社会系分野の産官学連携の研究支援者は約8%であった。理工・生物系分野に比して、人文社会系分野はリソース投入が僅かであり支援体制の在り方そのものを考える必要がある。四半世紀に渡る産官学連携推進にあたって様々な投資がなされてきたが、人文社会系分野は共同研究が少なく推進人材がいない点は解消されていない。このような構造的な問題を解決する、もしくは理工・生物系産官学連携モデルとは異なったフレームワークが望まれる。人文社会系分野が科学の域に留まらず、実践の域まで昇華した見方はないのであろうか。17年間この分野を追究してきた筆者の問いである。
参考文献
(注1)村上陽一郎(1983)『歴史としての科学』筑摩書房
(注2)小学館「デジタル大辞林」小学館ホームページ(https://dictionary.goo.ne.jp/jn/)
(注3)南了太(2023)『人文社会系産官学連携――社会に価値をもたらす知』明石書店
(注4)玉井克哉・宮田由紀夫(編)(2007)『日本の産学連携』玉川大学出版部
(注5)南了太(2019)「人文・社会系産官学連携の一考察」『産学連携学』17(1)、85-92
デサイロでは、人文・社会科学系の研究者がより持続的に活動できるエコシステムを生み出すために、「リサーチレポート」の制作を進めています。それに伴ってクラウドファンディングを実施しておりますので、ご興味のある方はぜひご支援ください。
※本寄稿を執筆した南了太さんにも、「人文・社会科学を取り巻く課題マップ」の制作に監修協力としてお力添えいただきました。
また、デサイロでは、ニュースレターやTwitter、Instagramなどを利用して、プロジェクトに関わる情報を継続的に発信中。Discordを用いて研究者の方々が集うコミュニティも運営しています。ご興味のある方はニュースレターの登録や各SNSのフォロー、あるいはDiscordにぜひご参加ください。
■Discord:https://discord.gg/ebvYmtcm5P
■Twitter:https://twitter.com/desilo_jp
■Instagram:https://www.instagram.com/desilo_jp/
■バックナンバー
文系学問と「社会」の新しい接点──生産的相互作用やELSIから考える、研究評価の現在地|標葉隆馬
テクストと現場を往還し、呼びかけに「応答」する人文学へ。社会と向き合う「自前の思想」の可能性──人類学者・飯嶋秀治、清水展