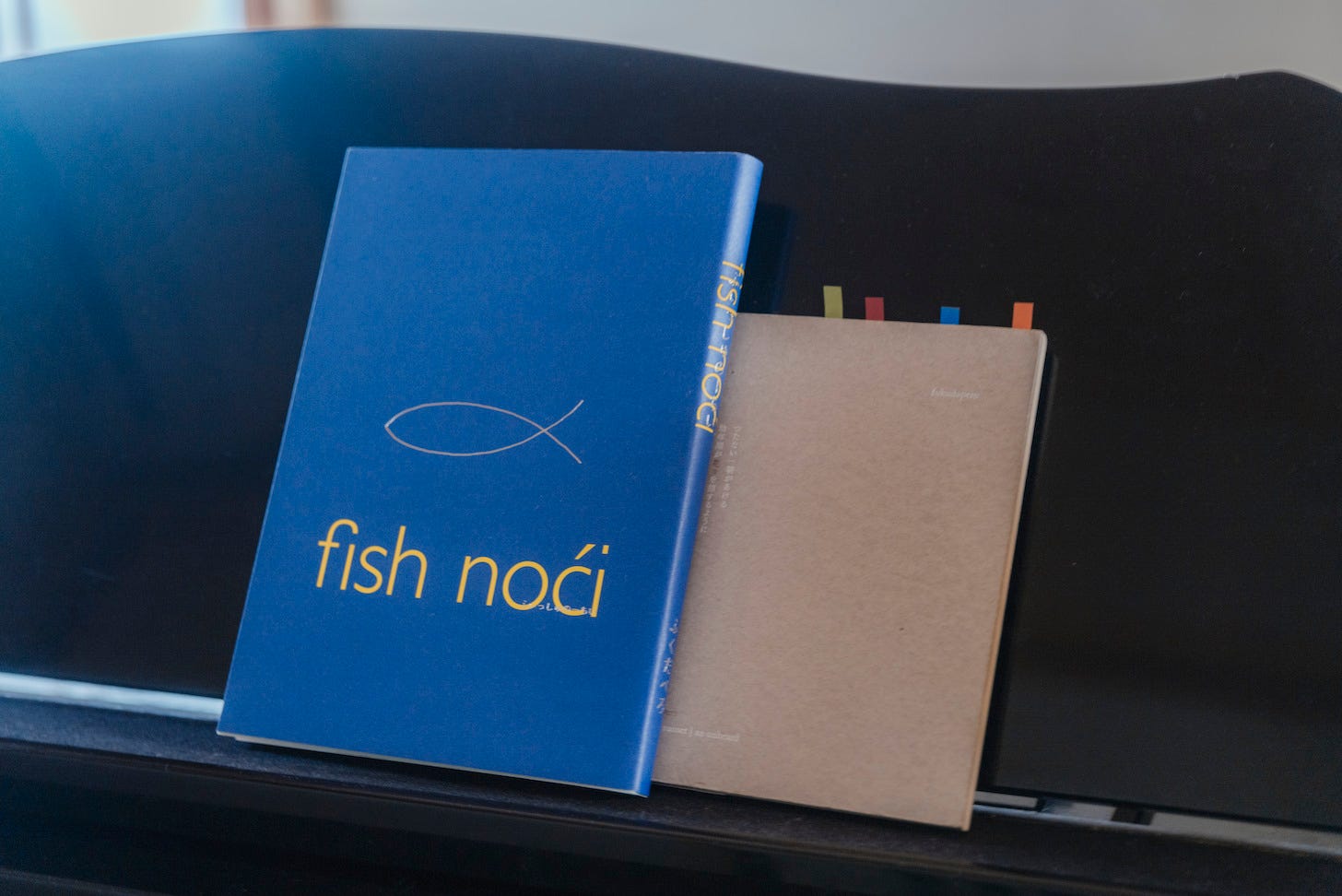体罰、“愛のムチ”、殴り合いの喧嘩……そう遠くない過去、この日本においても、日常にさまざまな「暴力」が満ち溢れていました。
現代では、そうした「暴力」の多くが、告発され、糾弾され、消えていっています。それにより多くの“被害者”が救われており、不当な暴力は今後も批判されていくべきでしょう。
一方で、暴力の極端な抑制は、個人から身体性や情動までも奪い、また別の意味での抑圧的な社会を生んでいるのではないか──。そう問題提起するのは、立命館大学先端総合学術研究科博士課程で人類学を専攻するふくだぺろさんです。
「デサイロ アカデミックインキュベーター・プログラム(以下、AIP)」第1期に採択されたふくださんは、本プロジェクトで「21世紀の暴力批判論──未来をつくる『平等主義的暴力』の可能性」をテーマに、暴力を多面的に捉え直すことができないか模索していると語ります。
現代社会において暴力は忌むべき悪である。暴力は支配と抑圧の温床であり、協調と理性的な討議によってのみ平等で平和な社会は営まれる。だから、暴力を排除して私たちはより良い社会を目指さないといけない―しかし本当にそうだろうか?
アフリカの大湖地域に住むトゥワ・ピグミーは毎日喧嘩に従事する。しかも十日に一度は流血沙汰も生じる結構ハードなやつだ。しかし近代的な常識に反して、彼らの暴力は支配や抑圧を生んでいない。むしろ彼らは優れて平等な、そして平和な社会を営んでいる。本プロジェクトでは、そうした常識を覆すようなトゥワの暴力を〈平等主義的暴力〉と名づけ、彼らの平等と平和の動力として考察する。
〈平等主義的暴力〉を考える際に忘れてはならないのは、暴力が生身の感情と身体を伴う対面行為であるという事実である。従って、本プロジェクトでは、暴力をポリティクスの問題としてだけでなく、そこにまつわる情動性・身体性を真摯に検討することで、暴力の存在論を開拓する。
「理性的でないもの」が劣位に置かれ、感情を表出させずに飲み込むことが「正しい」とみなされる現代。そうした時代において、ふくださんは「暴力」という存在をどのように捉え直そうとしているのでしょうか?
ふくだぺろ
マルチモーダル人類学者・詩人・アーティスト。
立命館大学先端総合学術研究科博士課程在籍。アフリカ大湖地域を主要なフィールドとして、テクスト、ドローイング、写真、映像、インスタレーションなど様々なモードを駆使することで、人々が「生きる」「現実」がどう個人的/集合的に作られるのかを多感覚的に探究する。代表的な作品に、映像『sitting, gazing, gazed』(2020)、詩集『flowers like blue glass』(2018)、インスタレーション「yoyo」《im/pulse: 脈動する映像》展(京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA、2018)、論文「具象のポリフォニー:音―イメージ知性の特徴とダイアローグ」(川瀬慈他編『拡張するイメージ──人類学とアートの境界なき探究』2023、所収)など。『現代詩手帖』新鋭詩集2020選出、マンチェスタ一国際映画祭2016実験映画賞受賞。
殴り合いは日常茶飯事。トゥワの人々が体現する「平等主義的暴力」
──ふくださんは、AIPの研究テーマとして「平等主義的暴力」を設定されています。ある民族の生活に暴力がごく普通に組み込まれている光景を実際に目にし、そう名づけられたそうですね。
はい。僕は東アフリカの大湖沼地域でフィールドワークをしているのですが、そこで暮らすトゥワ(ピグミー)の人々は毎日喧嘩をするんです。罵り合いも殴り合いの喧嘩も日常茶飯事なうえ、10日に一度ほどは棍棒や鉈のような道具が持ち出され、流血沙汰にもなります。
──いまの日本では信じられない光景ですね。
けれど近代的な常識に反して、トゥワの暴力は支配や抑圧を生んでいない。むしろ暴力を横行させることによって、彼らは優れて平等で平和な社会を営んでいるように、僕の目には映ります。
──暴力に溢れているのに「平等で平和」?
たとえば、近代社会のような階層性の高い社会では目上の人間が目下の人間を怒ることはあっても、その逆は基本的にタブーとされていますよね。そうして不平等に感情を管理し抑制することが求められる。しかし、トゥワの社会では誰に対してもどんな感情を表出しても自然とされます。
基本的に、トゥワの人々はオープンなコミュニティスペースで一日の長い時間を過ごします。そこではお喋りをしている人たち、歌ったり踊ったりしている人たち、そして喧嘩をしている人たちが共存しているんです。暴力が「暴力」として隔離されず、かつ誰もが平等に自己を表現することが許されることで、平等で平和な社会が形づくられる。こうした暴力のありようを、僕は「平等主義的暴力」と呼んでいます。
──しかし、大怪我をしたり、最悪の場合殺人に至ったりするケースもあるのではないでしょうか?
「殺してやる」「殺される」といった言葉はしばしば飛び交うものの、実際に殺人に至るようなケースはほぼないです。僕は関西出身ですが、関西人はすぐに「お前ほんま殺したろか」などと言うけれど実際に殺したりはしない。それと近い感覚なのかもしれません。
──近くにいる人々は、喧嘩を止めに入ろうとはしないのですか?
あまりしないですね。むしろある人たちの喧嘩が近くにいる人々にまで飛び火して、急に別の場所で喧嘩がはじまることすらあります。逆に、それまで猛烈に怒っていた人が、近くで踊っている人たちの輪に加わったかと思うと、突然怒りを忘れて楽しみだすこともある。
こういった出来事が起こる理由として、トゥワの人々は感情と身体が密接に連動しているのではないか、と考えています。現地語でアマハーネと言われる、怒りや悲しみの感情は主に「喧嘩」という身体的な表現に、喜びの感情は主に「踊り」という身体的な表現に結びつけられている。そして同じ場所にいる人々の「喧嘩」や「踊り」が相互に飛び火し、身体表現を介して感情が転換・伝染していくことで、あらゆる感情が解放されていく契機になります。
暴力の短絡的な排除は、別の社会的抑圧につながる
──日本社会では、怒りを覚えてもその場で飲み込むことがほとんどだと思います。トゥワの人々は、どのような感情もあまり抑制しないのでしょうか?
はい、そうです。その中でも、とりわけ怒りや嫉妬のようにネガティブとされる感情の表出が目立ちます。たとえば、僕は2020年から1年間、妻のユミと娘のヨーと一緒にルワンダに長期滞在していました。そして滞在が終わる帰り際に、ユミがお土産として持ってきていたピアスを一世帯にひとつずつ配ったんです。「一人ひとつではないけれど、みんなで使ってね」と。すると配り終えたあとで、ある女性がユミのことを「ドン!」と突き飛ばして、「なんで私のピアスがないの!?」とものすごく怒った。
それはとっても印象的な出来事でした。もし僕が彼女の立場だったら、自分のピアスがないことを残念だと感じても、ネガティブな感情はおそらく表明できない。このように、感情を過度に抑制・管理しようとしないことは非常に特徴的だと思います。
──こうした「平等主義的暴力」という概念を知ることで、暴力に対する人々の捉え方はいかに変化していくと思いますか?
暴力という多義的かつ価値争奪的な概念をどのように捉えるかという難しさはあると思いますが、たとえばヴァルター・ベンヤミンは『暴力批判論』の中で、暴力を「神話的暴力」「神的暴力」のふたつに分けて論じています。国家はある行為を「暴力」だと価値判断することで自身の正当性を確立し、個人から力の行使を奪っていきますが、他方で国家そのものが暴力によって成り立つことは隠蔽されている。これを「神話的暴力」とするのなら、「神話的暴力」に抵抗するものが「神的暴力」だとベンヤミンは述べています。
そして近年では「構造的暴力」「象徴暴力」など、従来は暴力として議論されてこなかった事象の権力関係が暴かれ、「これは暴力だ」として告発されるようになりました。そういう意味では、20世紀の暴力論は従来、暴力として認識されてこなかった国家や慣習、システムによる「強制」を暴力として暴く方向に進んできました。
そこから得られた知見は多いのですが、もともと暴力が身体や怒り・悲しみといった情動と深く結び付いていることや、広い意味での暴力や強制が無ければ人間社会はそもそも成り立たないことには、あまり目が向けられていないと思います。あらゆる暴力を全面的に排除しようとしても、さらに抑圧的な社会になってしまうだけではないか。
従来の暴力理解が西洋近代という認識論的前提から抜けられない一方で、平等主義的暴力は近代社会とは異なる論理で行使される暴力です。暴力が支配や抑圧を生むことなく、むしろ平等主義的な社会を形成していく。ですから、やや抽象的な言い方にはなりますが、暴力をうまく「飼い慣らしている」トゥワの人々のあり方を伝えることで、日本社会に生きる私たちがもっとうまく暴力と付き合っていく道を探ることができるのではないかと考えています。
言い方をかえれば、トゥワの人たちは個々人の自由と自律性をかなり尊重するのですが、穿った見方をするのなら、個人の自律性と他者の生命が衝突する場合もあり得る。そうした場合にはどうしたらいいのか?平等主義的暴力のネガティブな側面についても、今後はあわせて検討していきたいと思っています。
「ロゴス中心主義」を相対化する──マルチモーダル人類学が持つ可能性
──ふくださんは研究手法として、マルチモーダル人類学(編注:論文だけでなく映画、写真、展示、ハイパーテクスト、漫画、詩、小説など多感覚的なモードを調査や成果発表に用いる研究手法)を実践されていますよね。論文だけでなく映像も制作されていますが、さまざまなメディアで研究成果を発表することの意義についてもお聞きできますか?
わかりやすさを重視して「マルチモーダル」の中でも映像に焦点を絞りますが、研究者と話していると、「映像は多義的で意味が確定しないから研究には向かないのではないか」という話題が出ることがあります。言いたいことはわかりますが、言語が持つ「意味確定性」という物差しで映像を判断しようとする姿勢が、その背後に透けて見えます。
話をあえてシンプルにすると、いわゆるロゴセントリック(ロゴス中心主義的)な近代啓蒙思想においては、理性を上位に置き、理性的ではないもの……たとえば情動などを劣位に置きたがる。この二項対立はさまざまに普遍化することができて、伝統的には男性と女性、平和と暴力も、それに連動するような形で上位/劣位に位置づけられてきました。
そして、このロゴセントリックな二項対立は、テクストと映像に関しても当てはまると思います。
──「理性的なテクスト」と「そうではない映像」、という二項対立でしょうか。
はい。しかし本来、映像はテクストとはまったく違う理屈でイメージを捉えるものです。たとえば、映像編集をする際には、まったく別々のシーンに出てくる手と車の動きがリンクするから繋げよう、といった考え方をすることがある。そういった映像の思考もひとつの「知性」であると捉え直すことで、ロゴセントリックな学術を解放し、ひいては社会をさまざまな可能性に満ちたものに転換していけるのではないでしょうか。
テクストの強みや優位性は、時代と空間を超えてより遠くへ情報を飛ばすことができるメディアであること、認識の枠組みそのものを変えられることだと思います。しかし同時に、言葉を概念として抽象化するテクストだけでは、具象的な情動や身体、暴力には十分にアプローチできません。だから僕のプロジェクトでは論文や書籍だけでなく、長編映画も制作したいと思っています。そのためにこれまで、僕自身やトゥワの人たちによる撮影をしてきました。
参考映像:トゥワの宴会イギタラモ
また、オンラインに載せられるメディアは画と音が中心になるため、現状、マルチモーダルの中では映像が依然として優位です。ただし、より根本的な問題として、視聴覚に限定しないメディアの可能性も追求していくべきだと思うので、嗅覚や触覚といった感覚に焦点を当てたインスタレーション作品の展示は重要だと考えています。もちろん、論文とは異なる詩や小説、漫画といったモードでテクストを発表したりすることも欠かせません。
小説家を目指して退職。そこからマルチモーダル人類学に至るまで
──ふくださんがマルチモーダルな手法を模索しながら、「平等主義的暴力」というテーマを研究するようになった経緯についても聞きたいです。
もともと、僕は学生時代には小説家を目指していたんです。高校生の頃に小説を書き始めて、三島由紀夫の『仮面の告白』などの作品に影響を受けました。その流れで、学部時代は江戸文学を専攻しています。今でも式亭三馬や本居宣長などから受けた影響は大きいです。江戸文学の人たちはマルチモーダルですから。
その後、小説家になるためには執筆活動を続けられる地に足のついた生活をしながらのほうがいいと思い、大学卒業後は自動車メーカーを経て、JPモルガンに入社しました。
──企業で働かれていた期間があったのですね。いまのふくださんのイメージからは、かなりギャップがある選択に感じます。
そうかもしれません。スーツを着なくていい・時間がある・給料が悪くないという、自分が就職する上での3つの条件をJPモルガンは満たしていたんですよね。
しばらくは働きつつ小説を書いたりしていたのですが、何年か会社に在籍するうちに中途半端だと感じるようになり、「どちらかに振り切らなければ」と思って会社を辞めたのが20代の終わり頃です。自分はなんとなく30歳くらいで小説家デビューするのかなと思っていたのですが、「書かへんとデビューできへん」とその頃にようやく気づきまして(笑)。
──その後はすぐに小説の執筆活動に打ち込んだのでしょうか?
いえ。僕の場合は自分の殻に閉じこもっていてもうまくいかないと思って、友達の依頼で短編映画の脚本を書いたり、バックパッカーとしてユミとふたりで約1年間世界を回ったりもしました。
その旅で出会った人や物をモデルにして、帰国後に『ふぃっしゅのーちい』という小説を書き上げています。その際に、自分の書くものは散文というよりむしろ詩だなと感じたことから、本格的に詩も始めました。
──ふくださんのお話には、ご家族がよく登場する印象です。
やっぱり第一に、ユミとヨーが一緒にルワンダに来てくれたことは非常に心強かったですね。かなり環境が違うので、「ちょー日本帰りたい」と思う日もありましたから。
それに、自分が作家として余計なことに囚われなくなったのは、ユミの存在が大きいです。一時期は自分自身のアイデンティティのようなものに悩んでいた時期もあったんです。「アーティストたるもの孤独でいるべきではないか」と思って、自分が書くものにもずっと納得がいかなかった。
けれど、頭でっかちな僕とは違って、ユミは血肉の通った知識や経験を持って生きている人間だと感じたんです。いま振り返ると、ユミと出会い、彼女と愛し合えていると感じたことで、ある種の実存的な悩みから解放された。それは自分にとって、非常に大きな変化だったと思います。
──ただ、結果的に小説家ではなく文化人類学の道に進まれています。その方向転換はなぜ起きたのでしょうか?
僕はもともと、詩をつくる際に文字に限らない表現を試みたり、小説の中でもライトモチーフとして差別の問題を扱ったりと、文化人類学にも近い視座を織り込んで作品をつくっていました。そんな中で出会った、『リヴァイアサン』という映画が非常に面白くて。映画を撮った監督がルシアン・キャスティン=テイラーとヴェレナ・パラベルという人類学者たちだと知り、論文を書くだけでなく、さまざまな異なるモードで人類学的な研究をするマルチモーダル人類学のことを知りました。
そこで「自分がいままでしてきたことって、これやん。ちゃんと突き詰めてみたい」と思い立ち、映像人類学の研究科があったマンチェスター大学に進学を決めました。
──そこから、現在の研究テーマにたどり着いた経緯についても伺えますか?
ひとことで言えば偶然ですね。もともとアフリカには興味があり、修士論文のテーマもルワンダ移民についての研究だったのですが、トゥワの研究を開始したのは立命館大学の博士課程に進学してからのことでした。研究対象を西アフリカに変更しようかなとも考えていたのですが、トゥワの予備調査で改めてルワンダに行ったら「ここがマイカントリーだぜ」みたいな気分になりまして。
当初想定していた研究テーマは、「狩猟採集民のアニミズム的世界観と音楽の関係性の変容」についてでした。けれど、実際にルワンダに行ってトゥワの人々と生活を共にしてみると、一神教的世界観が強く感じられて、アニミズムなんてまるで感じなかった。
それを現在の指導教官である小川さやかさん(文化人類学者)に話したところ、「じゃあトゥワの人たちは何してるの?」と聞かれまして。「毎日歌って踊って喧嘩してるんですよ」と言ったら、「それじゃん!」と研究テーマが決まりました。それまでは喧嘩に巻き込まれたくないのでトゥワの人たちとお酒を飲んだりする場はなるべく避けていたのですが、それ以来、積極的に足を運ぶようになりました。
「情動=身体の交感様式論」を構築したい
──研究者、詩人、アーティスト……と多彩な顔を持つふくださんですが、ご自身の中では自分の職業をどのように定義されていますか?
現実的には場面によって使い分けることが多いですが、僕自身は自分のことを、第一義的には詩人だと思っています。詩人は一番、概念として応用性があるというか、何をしていてもいい存在だ、という感覚があるからそう思うのかもしれません。
それは僕が「ふくだぺろ」というペンネームで活動していることにもつながっていて。詩や小説はペンネームで発表するのに研究論文は戸籍名で書く、というのは辻褄が合わないと考えました。あくまで同じことを異なるモードで考えているだけという感覚なので、名前を使い分けるのではなく、ひとつのペンネームで活動することにしたので、研究も「ふくだぺろ」名義でやっています
──詩人であり研究者である「ふくだぺろ」として、今後どのように研究を深めていく予定かについて教えてください。
先ほどお話ししたように、トゥワの人々のコミュニティではお喋りをしている人たちと喧嘩をしている人たち、歌ったり踊ったりしている人たちがごく自然に共存していて、喧嘩や踊りは相互に転換・伝染していきます。こういった状態のことを「未決定な感情=身体群」と僕は呼んでいるのですが、こうした感情=身体群がさまざまな情動に開かれていく状態を指す「ポリエモーション=ボディ」という概念を提示することを、この先の研究として考えています。
トゥワの人々にとって自己は孤立した個ではなく、自然や他人を含めた共同性のなかで生成されるもので、自他が瞬時に入れ替わって融解していく。それによって平等性が担保され、トゥワの社会の基盤が生成されているのではないか、というのが僕の考えです。
柄谷行人は、社会のシステムを経済的な「交換」から読み解く、「交換様式」論を提唱していますが、僕はトゥワの社会における情動=身体の「交感様式」を定式化したい。そのうえで、トゥワの社会だけでなく、さまざまな異なる社会に対応する情動=身体の「交感様式」を考えていきたい。最終的には、より普遍的かつ応用性の高い「情動=身体の交感様式論」を構築することが研究目標です。
──野心的な目標ですね。マルチモーダル人類学についても展望をお聞かせいただけますか?
マルチモーダルな知をより浸透させ、研究や実践に携わる人を増やしていきたいと思っています。今年1月に映像/マルチモーダル人類学を牽引してきた日米の研究者が集うイベントが開催されたのですが、小川さやかさん、川瀬慈さん、岡原正幸さん、毛利嘉孝さんなど、実力のあるマルチモーダルな知の実践者は日本にもたくさんいます。
しかし、日本には面白いプレイヤーはいても、マネージャーやオーガナイザーのような人がなかなか生まれづらい土壌があるように感じます。そして、この課題は学問だけでなく、あらゆるジャンルに遍在して起きている。だから、ゆくゆくはマルチモーダルな知の研究や実践をする方々が集まるプラットフォームを設立して、大きな「うねり」を生み出していきたいと思っています。
従来のロゴセントリックな世界観から、社会を可能性に満ちたものに変えていく方法を、さまざまな興味関心を持つ人たちと一緒に模索していけたらいいですね。
Text by Shiho Namayuba, Photographs by Kazuho Maruo, Interview by Kotaro Okada, Edit by Tetsuhiro Ishida
デサイロでは、ニュースレターやTwitter、Instagramなどを利用して、プロジェクトに関わる情報を継続的に発信中。Discordを用いて研究者の方々が集うコミュニティも運営しています。ご興味のある方はニュースレターの登録や各SNSのフォロー、あるいはDiscordにぜひご参加ください。
■ Twitter:@desilo_jp
■ Instagram:@desjp
■ Discord:https://discord.gg/ebvYmtcm5P
■バックナンバー: