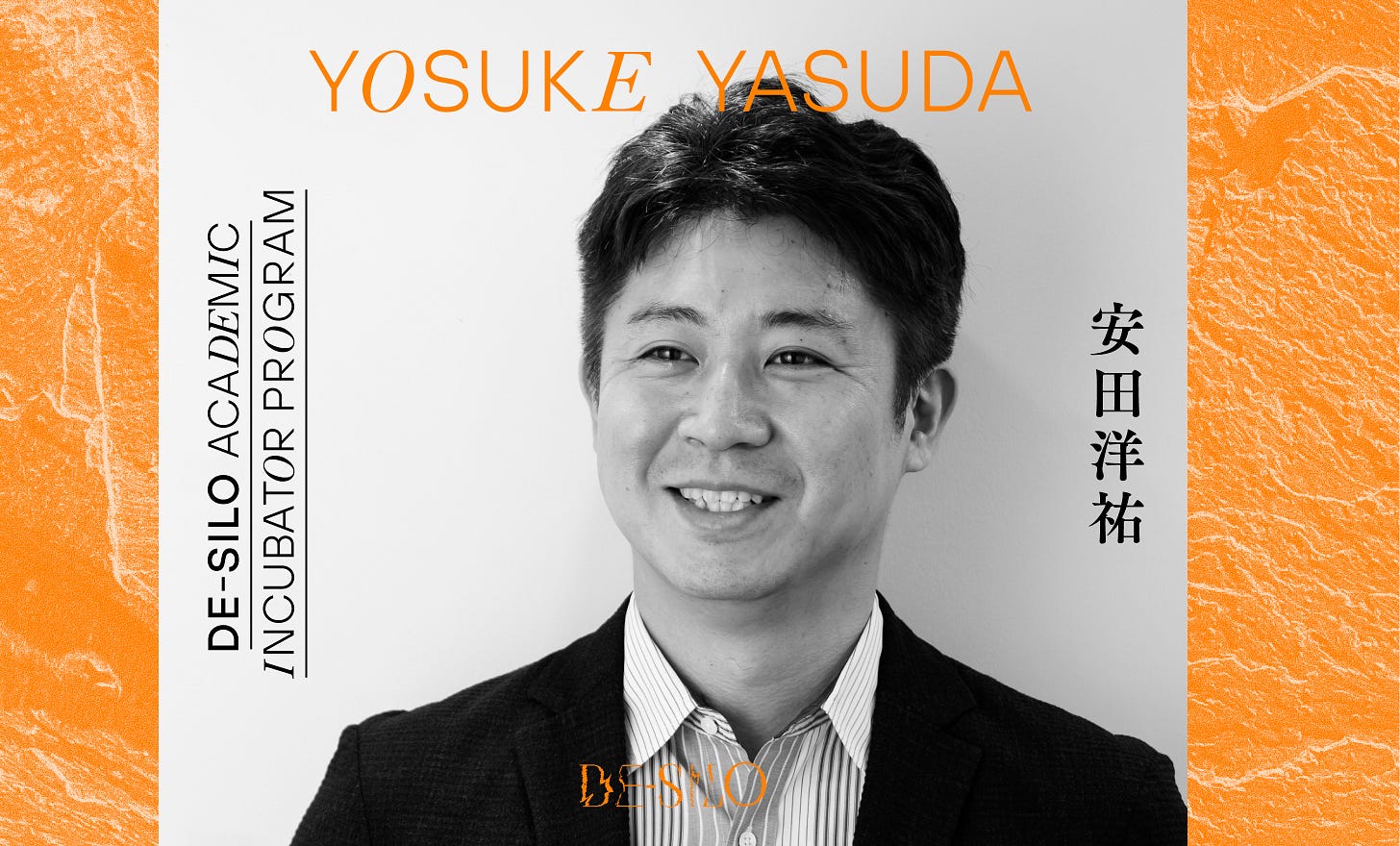いまこそ「時代」と「社会」に応答する人文・社会科学の研究を──デサイロ アカデミックインキュベーター・プログラム審査員の目線
文系学部不要論、アカデミックポストの不足、そしてポスドク問題……人文・社会科学における、研究活動を取り巻くエコシステムに関する課題は山積しています。
しかし、人文・社会科学分野の研究は「いま私たちはどんな時代を生きているのか」を読み解くうえでの大きな示唆を与えてくれるはず──そのような考えのもとで、研究のなかで立ち現れるアイデアや概念の社会化に向けた活動を行っている一般社団法人デサイロは、2023年7月4日、「デサイロ アカデミックインキュベーター・プログラム」の立ち上げを発表。①「De-Silo Publishing」での一般書の刊行 ②研究活動の社会へのアウトリーチ支援 ③研究会やイベントへの参加機会の提供の3軸に沿って、単年での研究資金の提供にとどまらず、人文・社会科学分野の研究と社会の新しい接点を模索し、研究者の持続的な活動をサポートしていきます。
詳細:一般社団法人デサイロ、人文・社会科学分野の研究者を支援する「デサイロ アカデミックインキュベーター・プログラム」を開始
本プログラムへの採択者を決定する審査基準は、①研究と社会の接続への意欲 ②時代と社会への応答 ③研究方法/計画の妥当性 ④他の学問領域への波及可能性 という4つ。プログラムを立ち上げるにあたって、審査員に就任したメンバーは以下の6名です。
・株式会社MIMIGURI代表取締役Co-CEO / 東京大学大学院情報学環特任助教 / 博士(学際情報学) 安斎勇樹
・立命館大学産業社会学部准教授 / シノドス国際社会動向研究所理事 / 博士(社会学) 富永京子
・大阪大学大学院経済学研究科教授・エコノミクスデザイン共同創業者 / Ph.D. in Economics 安田洋祐
・人類学者 / デサイロ理事 / 博士(文学)磯野真穂
・連続起業家 / 株式会社フェニクシー共同創業者 / デサイロ理事 / 博士(工学) 久能祐子
・編集者 / 一般社団法人デサイロ代表理事 岡田弘太郎
本記事では、これまで自らも研究と社会の接続に取り組んできた審査員6名の目線から、プログラム立ち上げの背景にある現在地を整理。研究者と実務家の間にある距離、新しい業績評価基準の必要性、研究における「新規性」の定義、研究者が社会とコミュニケーションする能力を獲得する方法……人文・社会科学が抱える課題について包括的に議論しました。
デサイロでは、アカデミックインキュベーター・プログラムへの参加者を募集しています。ご興味のある方は、下記リンクよりぜひご応募ください。
▶▶アカデミックインキュベーター・プログラムへの応募リンクはこちら
“死体解剖学”は実践では役立たない? 研究者と実務家の乖離を埋めるために
岡田 アカデミックインキュベーター・プログラムでは審査基準の一つに「時代と社会への応答」を置いており、さまざまなアプローチで研究と社会をつなぐ実践をされてきた皆さんに審査員に就任いただきました。
例えば、安斎さんは人の創造性を活かした経営・組織文化のデザイン論を研究するのと並行して、代表取締役を務めるMIMIGURIにおいて「Creative Cultivation Model(CCM)」という組織マネジメントの理論を構築し、それを創造的な組織づくりのコンサルティングなどの実践面でも活用していますよね。MIMIGURIは2022年に文科省に研究機関として認定され、「リーダーシップ」「チームレジリエンス」「創造的人材育成」などの研究テーマを定めていました。これらはまさしくデサイロが掲げる「概念の社会化」の好例だと思っているのですが、研究と社会の接続についての考えをお話しいただけますか?
参考:最新版「Creative Cultivation Model(CCM)」とは:組織の創造性をマネジメントするための見取り図|CULTIBASE
安斎勇樹(あんざい・ゆうき)
株式会社MIMIGURI 代表取締役Co-CEO/東京大学大学院 情報学環 特任助教
東京大学工学部卒業、東京大学大学院学際情報学府博士課程修了。博士(学際情報学)。博士号取得後、株式会社ミミクリデザイン創業。その後、株式会社DONGURIと経営統合し、株式会社MIMIGURI 代表取締役Co-CEOに就任。経営と研究を往復しながら、人と組織の創造性を高めるファシリテーションの方法論について探究している。主な著書に『問いのデザイン:創造的対話のファシリテーション』、『問いかけの作法:チームの魅力と才能を引き出す技術』、『パラドックス思考:矛盾に満ちた世界で最適な問題解決をはかる』、『リサーチ・ドリブン・イノベーション』、『ワークショップデザイン論』などがある。
安斎 僕はもともと大学院の頃は教育学や学習科学の領域に属していまして、教育の方法や学習論の論文を書いて、それを自分で授業の中で実践してみて……という具合に、そこでは実践と研究のミクロな反復が当たり前のように行われていました。
しかし、経営という領域に軸足を移して驚いたのは、教育学や学習科学に比べると実践と研究の距離が離れていて、実務家があまり経営学を参照していない傾向にあるように思えたこと。以前、経営学者と実践家の関係性について論文にまとめたこともあるのですが(※1)、経営者の中には「経営学は“死体解剖学”であり、うまくいったケースを後付けで説明しているだけで現場では役立たない」と考えている人も少なくありません。他方で研究者も、経営学に限らずアカデミア全体の傾向として、学会に所属する研究者に向けて論文を投稿することに注力するあまり、実務家まで十分に知見が届かないケースがよくあります。このように変な形で生態系が固着してしまっているのは、もったいないと思っています。
(※1)服部 泰宏, 伊達 洋駆, 福澤 光啓, 舘野 泰一, 安斎 勇樹, 経営学者と実践家との関係性の再考, 組織学会大会論文集, 2013, 2 巻, 1 号, p. 113-119
翻って、アメリカの研究者は、実務家にとって有用な理論を構築することが比較的得意なように思えます。例えば、現在主流の経営学を見ると「リーン」「アジャイル」「カイゼン」「両利きの経営」などの言葉が出てくるのですが、これらはもともと日本の経営実践がルーツだという指摘もあります。かつての日本企業が積み重ねた実践を理論化して、ローコンテクストにしたのはアメリカで、そのおかげでみんなが積極的に使えるようになった。見方によっては、いま日本は自分たちが昔実践していたことを逆輸入しているという、おかしな状況が生まれているとも言えます。さらにアメリカでは、コンサルタントなどの実務家と経営学者が共著で本を出していることも珍しくありません。
日本でも本当は、もう少しうまくやれば、学問と実務の良い関係性を構築できるはず……僕はそう考えて、経営領域でコンサルティングを行い、そこで分かってきた生々しい現場の状況を論文にしていくという往還に挑戦しているんです。とりわけ文系の産学連携の成功例は少なくて、場合によっては実務家と研究者がお互いに敬意に欠ける態度を取っているケースも見かけます。認識の齟齬はあって当然なので、お互いを理解しあったうえで、コラボレーションの機会が単純にもっと増えればいいと思っています。
「ジャーナル文化」以外にも、研究評価の選択肢を
岡田 いま「経営者が実は経営学というものを全然参照してない」という課題提起がありましたが、経済学が専門の安田さんは、この点についてどう思いますか?
安田洋祐(やすだ・ようすけ)
大阪大学大学院経済学研究科教授/エコノミクスデザイン共同創業者
1980年東京都生まれ。2002年東京大学卒業。米国プリンストン大学へ留学して07年Ph.D.(経済学)取得。政策研究大学院大学助教授、大阪大学准教授を経て、22年7月より現職。専門はゲーム理論、マーケットデザイン、産業組織論。20年6月に株式会社エコノミクスデザインを共同で創業し、コンサルタント業務やオンライン教育サービス「ナイトスクール」を運営する。主な著書に『「2030年日本」のストーリー』(共著)、『学校選択制のデザイン ゲーム理論アプローチ』(編著)、『そのビジネス課題、最新の経済学で「すでに解決」しています。』(共著)、『オークション・デザイン ものの値段はこう決める』(監修)など。
安田 これは個人的な印象なのですが、経済学者は経営学者とあまり仲が良くないように感じます。経営学者にも面白い研究者がたくさんいるのですが、それが十分に伝わっていない。経済学はどちらかといえば理系に近い、業績評価に依拠しています。経済学には国際ジャーナルで厳然たるランキングがあり、良いジャーナルに出していると評価されて、それ以外の媒体で物を書いたりしてもほとんど評価されない。他方、日本の経営学者は研究を国際的なジャーナルに出している人があまりいないので、経済学者から見ると「本当に重要な研究をしているのか?」と疑わしく見えてしまうわけですね。
もちろん、「狭義のジャーナルカルチャーで常に研究者の業績を測るのは良いことなのか?」「それは本当に社会にとってプラスなのか?」という疑問も生じますよね。僕はアカデミアの外で積極的に活動していますが、これは「時代や社会に応答する」ことが研究者にも求められていると思うからやっているわけです。そして、こうした活動の重要性に関して、異論がある研究者はほとんどいないはずです。しかし、繰り返しになりますが、昨今のアカデミアの業績評価、とりわけ経済学では「良いジャーナルにたくさん書いているか」が昇進や採用の評価指標になる一方で、それ以外の活動は考慮されず、研究者としてのキャリアにとっては意味がないという状況がある。
このように、あまりにも単一かつ極端な指標で研究者のポテンシャルが測られることに、制度疲労が起こっていると感じます。アナロジーで考えれば、いまビジネスの現場では短期的な企業価値や利潤の最大化を第一としてきた過去を反省し、SDGsやESG、サステナビリティのような新しい価値基準を取り入れる動きが起こっていますよね。それと同じように、研究の世界でも明示的な目標や審査基準として、「時代や社会に応答しているか」を狭義の研究業績と異なる尺度として掲げる必要があると思います。
ここで少し気をつけなければいけないのは、新たな価値基準を導入すると“研究しない口実”として使われてしまう危険性もあることです。「私は伝統的な業績評価で見るとアウトプットを出せていないかもしれませんが、時代や社会に応えるような情報発信や活動をしています。したがって、私は優れた研究者です」と。こういった姿勢は論文を書く力、すなわち研究者としての専門的能力の衰退につながってしまい、もちろん望ましくない。ただ、いまの若い研究者は目の前の業績を上げることに一生懸命で、視野が狭くなりやすい構造があるのも事実です。デサイロの活動などを通じて、その構造自体を変えていく必要があると思っています。
研究における「新規性」とはなにか? 学会の中だけに閉じこもらない新たな基準を
磯野真穂(いその・まほ)
人類学者。デサイロ理事。専門は文化人類学・医療人類学。博士(文学)。早稲田大学文化構想学部助教、国際医療福祉大学大学院准教授を経て2020年より独立。身体と社会の繋がりを考えるメディア「からだのシューレ」にてワークショップ、読書会、新しい学びの可能性を探るメディア「FILTR」にて人類学のオンライン講座を開講。著書に『他者と生きるーリスク・病い・死をめぐる人類学』(集英社新書)『なぜふつうに食べられないのか――拒食と過食の文化人類学』(春秋社)、『医療者が語る答えなき世界――「いのちの守り人」の人類学』(ちくま新書)、『ダイエット幻想――やせること、愛されること』(ちくまプリマ―新書)、宮野真生子との共著に『急に具合が悪くなる』(晶文社)などがある。(オフィシャルサイト:www.mahoisono.com )
磯野 業績評価基準が単一的であるという点については、私が人類学者として研究活動を行ってきた中でも思うことがありました。もともと私は運動生理学が専門だったのですが、どうすれば人類学の知見を医療に応用できるか考えて、まずは摂食障害の研究を始めたんです。その時初めて書いた博士論文をもとに執筆した『なぜ普通に食べられないのか: 拒食と過食の文化人類学』(春秋社, 2015)という本は未だに多くの方々に読まれているのですが、人類学者からの評価は残念ながら芳しくありませんでした。
その理由は、「摂食障害」という研究対象を、人類学の理論的な発展のために使っていないから。私としては、人類学のシンプルな理論を使って摂食障害の新しい見方を提示したつもりだったのですが、そうすると人類学者として全く評価されない……という事態が起こってしまったんです。
私はそれで「もういいや」と割り切ってしまったのですが、人類学に限らず研究者は、たとえ一般向けのものであっても、研究者ウケを気にしたような知見の発表をしてしまう傾向にあるように思えます。もちろん全部ではありませんが、例えば、参考文献の詳細な紹介にこだわってしまうとか、正確に書こうとするあまり何を言いたいかが伝わりにくくなったりとか。
また、人類学という学問の枠内で理論的な新規性を求めると、「理論Aのこの点に問題があるため、この問題を解消し、昇華しました」といった形になりがちです。もちろんそうした研究が重要であることは言うまでもないですが、こういう形の研究は、理論Aの研究者以外には全く伝わらないのも事実でしょう。
一般の人からすれば参考文献の多寡やそれぞれの理論が持つ問題点の細部を突くことよりも、その知識がいかに応用できるかを知りたいはずなのですが、応用は研究者として評価されない。その副作用の一つとして、「研究の新規性を求めれば求めるほど、それについて語れる人数が減る」という状況がしばしば起こっているのです。おそらく学問のサイロ化は、こうして起こるのだと思います。
かといって、アカデミアの外に向けた言葉で伝えようとすると、人類学者として評価されない。人類学者のポジションはなかなか募集が出ないので、結果的に就職には結びつかないという負の循環が起こってしまう。アカデミックインキュベーター・プログラムは、こうして疲弊してしまった業績評価の基準に、少しでも風穴を開ける一助になり得るのではないかと思いました。
岡田 摂食障害の研究に人類学の知見を持ち込んだことは明らかに新規性がある。しかし、それが「人類学の学問的な発展に繋がっていない」という理由で学会からは評価されなかったと。従来はその学問が使われてなかった領域に応用している、といった「分野横断性」や「学際性」の観点は、デサイロ アカデミックインキュベーター・プログラムにおける「新規性」として審査基準に盛り込んでいきたいと思いました。
安田 そこは重要なポイントで、分野横断性や異なる学問の組み合わせなどを評価できるアカデミックなジャーナルは少ないんですよね。それぞれの分野の範疇にある基準でしか測れない場合がほとんどです。なので、単に新しいだけではなく、「どういった視点で新しいか」が重要になります。「複数のアプローチの掛け合わせ」「新しい視点の組み合わせ」を評価する基準を掲げることは、伝統的な業績や論文評価を超えていくための象徴的なメッセージになると思います。
「運動」的な研究あるいは、「Proof of Concept(概念実証)」の重要性について
岡田 ここまで議論してきた「研究と社会の接続」という論点に関して、主に社会運動についての研究を専門としつつ、執筆や講演など、積極的にメディアを通じた発信や社会へのアウトリーチを行っている富永さんにもご意見を伺いたいです。
富永京子(とみなが・きょうこ)
立命館大学産業社会学部 准教授/シノドス国際社会動向研究所 理事
1986年、北海道札幌市出身。2009年、北海道大学経済学部を卒業。2015年、東京大学大学院人文社会系研究科修士課程・博士課程修了後、日本学術振興会特別研究員(PD)を経て、現職。専門は社会運動論。社会学的視角から、人々の生活における政治的側面、社会運動・政治活動の文化的側面を捉える。著書に『社会運動のサブカルチャー化』(せりか書房)、『社会運動と若者』(ナカニシヤ出版)、『みんなの「わがまま」入門』(左右社)など。朝日新聞、北海道新聞でも連載中。
富永 積極的に発信していると紹介していただいたんですが、私自身は、メディアでの発信を後ろめたく感じているというか、どこか言い訳をしながらやっていますね……。私の研究課題に「日本の人々が社会運動に対する忌避感や抵抗感を持つのはなぜなのか」があり、各所から発言を求められるようになったのですが、メディアでの発信をしていると、自分が「正統な研究者像」から外れているんじゃないかという後ろめたさがある。
ただ、そもそも意義があると思っていなければそういった仕事を受けないですよね。社会に貢献できる仕事だからお受けしているわけですし、実際にメディアなどで活動すると、平板にしか捉えていなかった社会の存在が、少し具体的な像になった感覚はあります。例えば「日本人は社会運動への忌避感が高い」という事実一つとっても、メディアの向こうの人々は彼らの実感に即した表現で反応してくれる。それは質的研究者の自分にとっては貴重なことです。
しかし、そうした利点があっても、やはり後ろめたさや言い訳が伴ってしまう。このメディアでの発信に対する躊躇いは、かつての私が「運動」的な研究に抱いた抵抗感と繋がるかもしれません。私は一部の社会学の研究に対して「それは研究ではなく、『社会運動』なのでは?」と思うことがありました。最初にこれを思ったのは、女性学のゼミに初めて参加した時でした。社会学は安田さんと磯野さんがお話していたような典型的な業績評価から離れた研究も見られますし、目の前の社会問題の解決や提起に直結するコンテクストを取り扱う余地も大きい。ただ、そうしたコンテクストに馴染みのない立場の人間からすると、「それは運動なの?研究なの?」という問いを引き出してしまう。
この問いの背景にあるのは「正統な研究」がどこかにあり、それは「運動」とは相反する、という考えですよね。ただ安斎さんのお話と関連すると思うのですが、その二つは簡単に区分できるのか。今の私は「いや、それは研究ではなく運動でしょう」と簡単に切り捨てることにも問題があると考えています。なぜなら、「伝統的な評価基準に基づき、正当な業績を積める人」というのは、そもそも限られた人なんじゃないかと。ケア労働の負担が重い人は研究どころではないし、全ての学会に合理的配慮がなされているわけではないから、障害があると学会一つに出るのもすごく大変になる。そういったことが全然見えていなかったから、女性学や障害研究を「運動じゃん」と言って切り捨てた。研究の世界も自分たちのいる社会のひとつで、それを問い直す上でも、「運動」的な研究も重要だと教えてくれたのは、ある若手研究者の方です。
昨年逝去されたのですが、ご自身も当事者でミックスルーツの人々の研究をされていたケイン樹里安さんという方がいました。彼は優秀でプロダクティブな方ですが、社会的な活動もかなりされていた。彼と話したとき私はもったいないというか、「なぜ院生のうちからそんなに運動してるの?研究に専念してもいいのに」と感じてしまった。しかし、彼の立場からすると「研究に専念できる」ということが既にある種のマジョリティーの特権であり、それを「運動」的な研究を通して伝えなければいけなかったんですよね。だから、社会に貢献する研究は「研究の世界における公正性を問い直す」という意味においても重要である、と社会運動研究者の視点からは思います。
久能 「研究」と「運動」という考え方は非常に興味深いですね。「研究」とは、新しい概念を0→1で発見するフェーズで、「運動」とは、その概念が社会を変えられるのかどうかを仮説証明のために試行錯誤する1→10のフェーズなのであると言えるのかもしれません。
私は日本には良質な研究がたくさん存在すると思っています。しかし、その多くは0→1の「研究」段階で止まって埋もれてしまっている。なぜかというと、スタートアップ用語で言えば「Proof of Concept(概念実証)」としての、1→10の「運動」的ステップを進められる投資家的な存在やエコシステムが足りないという問題があるからです。「研究」によって生まれた種を、次は「運動」のフェーズで育ててみる。それが「概念の社会化」につながっていくのだと思います。
これはサイエンスで言えば試験管を振ることに似た行為なので、どれが成功するかはやってみなければわかりません。それでも、小さくたくさん概念をインキュベーションしてみて、Proof(実証)できるか試みる。そうやって芽が出るのをサポートしていくのが、デサイロの役割になるのかもしれませんね。
久能祐子(くのう・さちこ)
連続起業家、科学者。京都大学工学部で学部、同大学大学院工学研究科で修士、博士課程を修了(工学博士)。バイオベンチャーの共同創業者兼CEO等として、日米で研究開発、会社経営を経験。これらの事業を通して、1994年に世界初のプロストン系緑内障治療薬を商品化に成功。その後、2006年には慢性特発性便秘症及び過敏性腸症候群治療薬-クロライドチャネルオープナーの商品化にも成功した。2013年には、新型ワクチン開発を目指すVLPセラピューティクスを、2014年には、米国で滞在型・社会起業家インキュベーターHalcyonを、2017年には、京都で滞在型・起業人材育成インキュベーター、フェニクシーを共同創業した。現在は、ワシントンDCで社会起業家、フィランソロピスト等として活動している。京都大学理事(2022年9月まで)のほか、ジョンズホプキンス大学医学領域評議員(2023年6月まで)、お茶の水女子大学、沖縄科学技術大学院大学(OIST)の評議員、マネックスグループ株式会社、株式会社ディー・エヌ・エーの社外取締役も務める。
研究における「深さ」や「新規性」の定義を刷新していく
安田 「Proof of Concept」の話は、僕もとても納得感があり賛成です。ぜひ今回のプログラムの選考過程に反映したいですね。
ただ、一点だけ引っかかっているのが、意外と日本には既に、若手の研究者を引っ張り上げる仕組みが存在しているのではないかという点です。例えば新書が典型的ですが、そこまで研究を深掘りできていない人文・社会科学系の若手論者でも、現代社会論的な視点から面白ければ本を書かせる、という土壌があるのではないでしょうか。少なくとも、アメリカにはあまりそういった文化はない気がします。若手が活躍できる場が増える半面、まだ若くて“狭義の研究業績”が伴ってない人が気軽に出せる出版社があると、「人文系の研究者が、深い研究に行き着く前に新書で発表してしまう」という問題も起こるかもしれません。そちら側に若手が流れているのだとすると、悩ましいですよね。
磯野 重要なご指摘だと思います。付け加えるならば、「研究が深まっている」「ちゃんとした研究に昇華されている」状態とは何なのか、という問いについては考える必要がありそうですよね。「深まる」と一口に言っても、それが厳密性なのか、あるいは他分野と接合することなのか、困ってる人に本当に届くことなのか、さまざまな尺度がありそうです。
岡田 アカデミックインキュベーター・プログラムでは「De-Silo Publishing」での一般書の刊行も行うのですが、ご指摘いただいたポイントは悩む部分でもあります。「研究が深まる前に出すべきではない」という意見には真摯に向き合うべきですし、「面白いコンセプトの本でしたね」で終わらせたくはありません。先ほど久能さんがお話していたように、「1→10」のステップに伴走していくことで、デサイロならではの価値を生み出せたらと思っています。
岡田弘太郎(おかだ・こうたろう)
編集者。一般社団法人デサイロ代表理事。『WIRED』日本版エディター。クリエイティブ集団「PARTY」パートナー。スタートアップを中心とした複数の企業の編集パートナー。アーティストのマネジメント等も担当。研究者やアーティスト、クリエイター、起業家などの新しい価値をつくる人々と社会をつなげるための発信支援や、資金調達のモデル構築に取り組む。1994年東京生まれ。慶應義塾大学にてサービスデザインを専攻。Twitter: @ktrokd
磯野 ここまでの議論を踏まえて、デサイロが考える「新規性のある研究」とは、まず単にキャッチーな目新しさではなく、学問の基盤にしっかり立っていること。その上で、1→10のフェーズにいける新規性があることを基準にできるとよいのかもしれないですね。先ほど私が問題提起した「新規性を求めるほど、語れる人が減る」という問題に対して、「1→10」につながる研究は、概念をより一層社会に広げていく可能性を持つのだと思います。
久能 素晴らしいと思います。「インクルーシブな新規性」とも呼べるかもしれませんね。
安斎 0→1が「研究」で、1→10が「運動」や広めていく過程という考え方は、わかりやすくて僕も良いと思っています。
他方で、僕は「研究でわかったことを本に書いている」という感覚はあまりないんです。あくまで僕が本や論文として出したものが相手に届き、その人や社会とコミュニケーションをしながらフィードバックを得て、次の研究について考えて執筆していくというプロセスを経ている感覚があります。
僕は積極的に若手研究者と共著で本を執筆して出版する機会を増やすようにしているのですが、これは研究者としてのコミュニケーション能力、今日の議論に即して言えば「運動」能力が育まれていくプロセスこそが重要だと考えているからなんです。というのも、若手研究者は博士論文を書くと助成金を取り、その博士論文を単著の学術書として出版して、その後に長らく忙しくなり何も書かなくなる……というパターンが多い印象があります。その後、研究者が「社会と断絶したまま研究が止まる」「論文は書いてるんだけど社会と関わらない」というパターンに陥っていく端緒が、そこにある気がしていて。だから博論を書き終えて、学術書を書いたぐらいのタイミングの若手研究者に「ちゃんと一般書を書こう!」と声をかけ、一緒に取り組んでいるんです。つまり、研究を「広めてあげる」というよりも、本の執筆を通じて研究者としての社会と関わる“運動能力”を共に育むためにやっているんです。
富永 たしかに、アウトリーチを通じた研究者としての“運動能力”は社会との相互作用で育まれる部分がありますね。2019年に『みんなの「わがまま」入門』という一般書を出版したのですが、この書籍を読んだ方々、例えば女性誌や一般企業からさまざまなご相談を受けるようになったんです。会社や家庭などで問題提起をしたいけど、どうすればいいかわからないと悩んでいる方は数多くいらっしゃいます。そして、本書を読んだ方は「社会運動」という概念を手にして、それを自分のいる社会の中で声を上げていくための力に変えていただいているように思えるんです。
この“わがまま”という言葉は、とある講演で高校生に話す際に、「でも、社会運動って“わがまま”じゃないですか」と言われて、「社会運動への忌避をこう言い換えるのか」と思ったことをきっかけに書いたのです。普通に社会運動を研究しているとなかなか思いつかない表現ですが、安斎さんがおっしゃるように講演や執筆活動を通じて一般社会とコミュニケーションし、フィードバックを得るうちに“わがまま”という言葉にたどり着いた。その意味で、私にとって1→10の「運動」によるアウトリーチの成果の一つが、『みんなの「わがまま」入門』だったのかもしれないです。
安斎 非常に興味深いお話ですね。デサイロは「0→1」の良い種を見つけて広める活動をしたいのか、あるいは研究者たちに社会との関わり方を獲得してもらいたいのか。アカデミックインキュベーター・プログラムではそういった点も考えて試行錯誤していけると、「研究と社会の接続」「時代と社会への応答」といったミッションを実現する成功事例を、研究者とともに再現性をもって生み出せるようになるかもしれません。
岡田 そうですね。今回のプログラムでは、社会一般ではまだ広く認知されていないけれど素晴らしい研究者の方と出会いたいですし、「インキュベーション」という言葉にもあるように、そうした研究者の方々の研究が“深まり”、多様な社会との接点が生まれていくプロセスにデサイロとして伴走していきたいと思います。
皆さん、素晴らしい問題提起をありがとうございました。今回のプログラムでは、背景にある課題意識やプロセスをオープンにしながら、アカデミアを取り巻く課題について議論していくきっかけにできればとも考えています。研究者の皆さんからのご応募をとても楽しみにしております。
(Text by Tetsuhiro Ishida, Edit by Masaki Koike)
デサイロでは、アカデミックインキュベーター・プログラムへの参加者を募集しています。ご興味のある方は、下記リンクよりぜひご応募ください。
▶▶アカデミックインキュベーター・プログラムへの応募リンクはこちら
また、アカデミックインキュベーター・プログラムに関する情報は今後もニュースレターで継続的に発信していきます。ご興味のある方はニュースレターの登録や各SNSのフォロー、あるいはDiscordにぜひご参加ください。
■Discord:https://discord.gg/ebvYmtcm5P
■Twitter:https://twitter.com/desilo_jp
■Instagram:https://www.instagram.com/desilo_jp/
■バックナンバー:
人文・社会科学の研究者に「大学の常勤職員」以外の選択肢を。アカデミア外にも広がるキャリアの可能性を考える:磯野真穂 × 藤嶋陽子 × 岡原正幸
人文・社会科学と「社会」をつなぎ直すために──ニュース解説、ランダムな探索、企業内研究、アーカイブの視点から考える