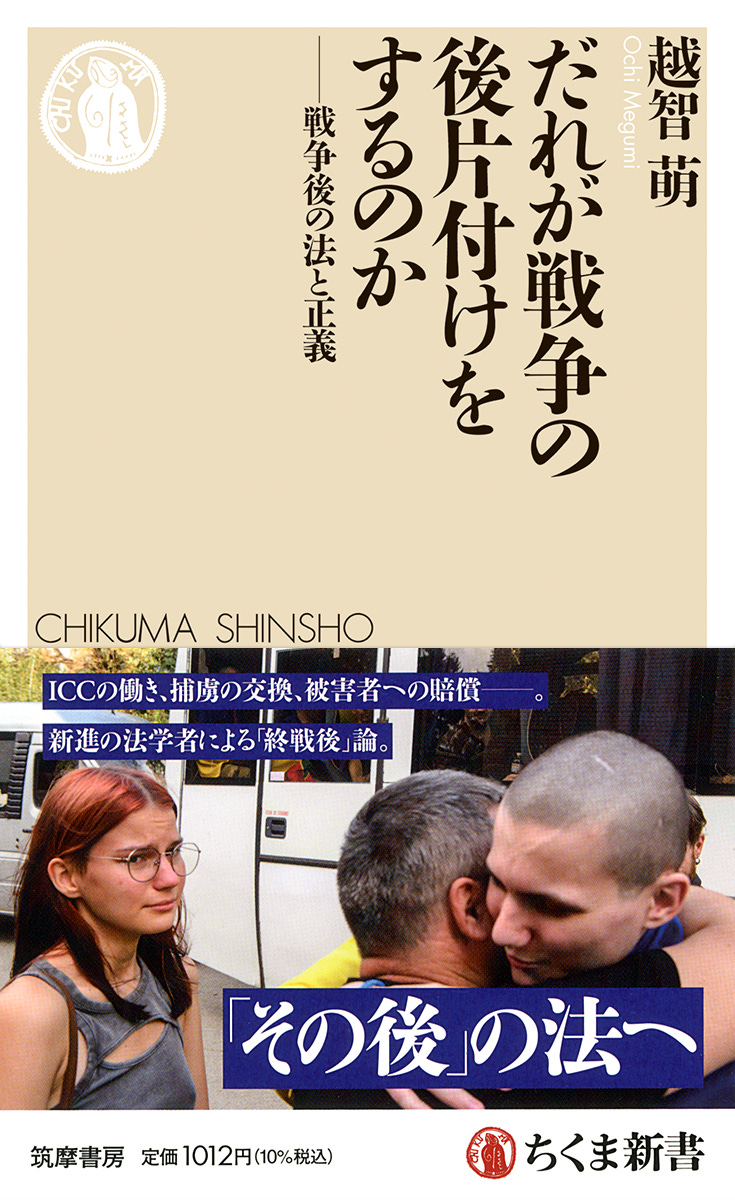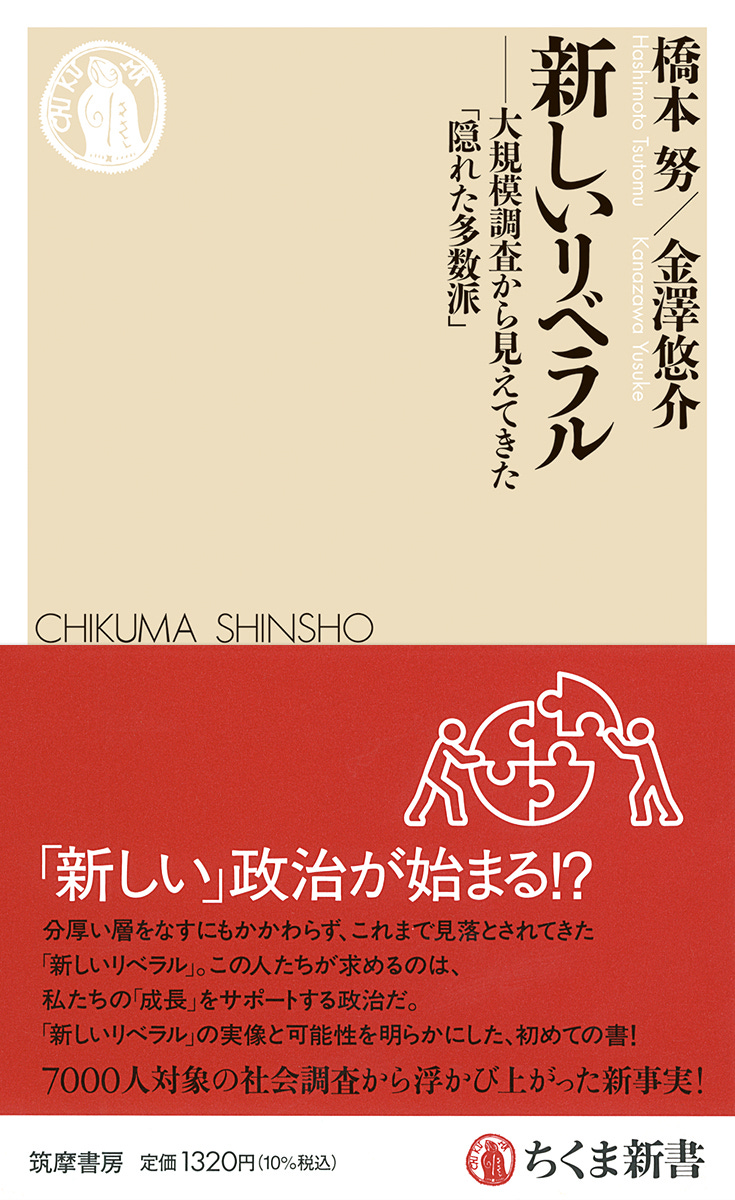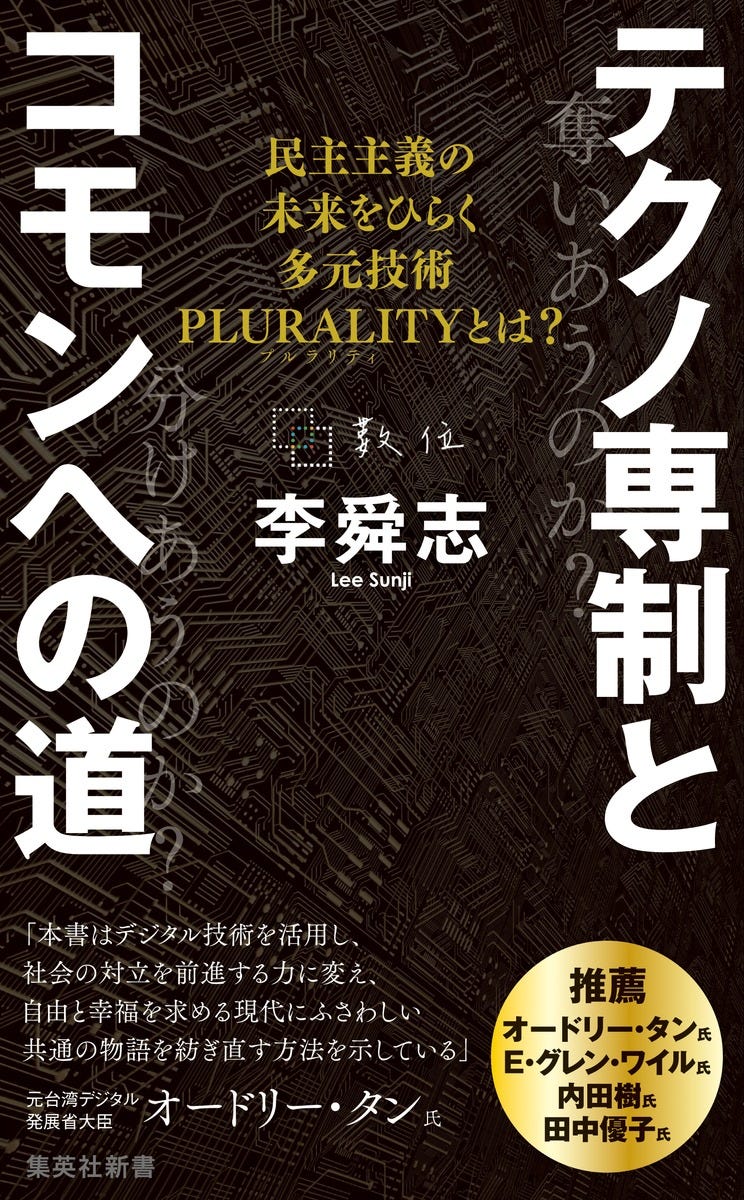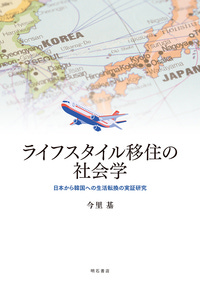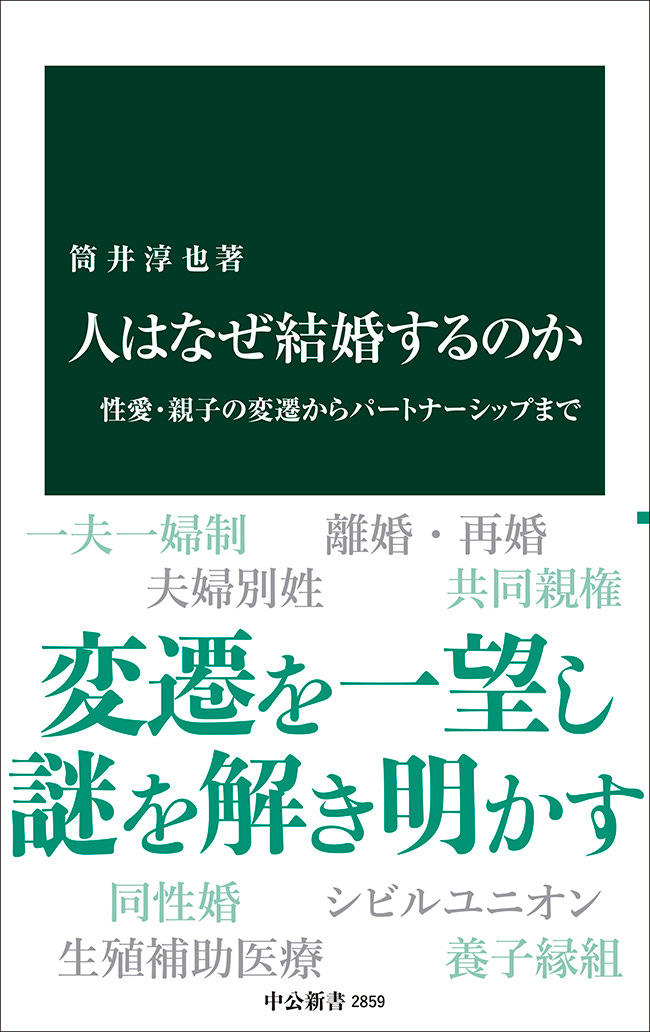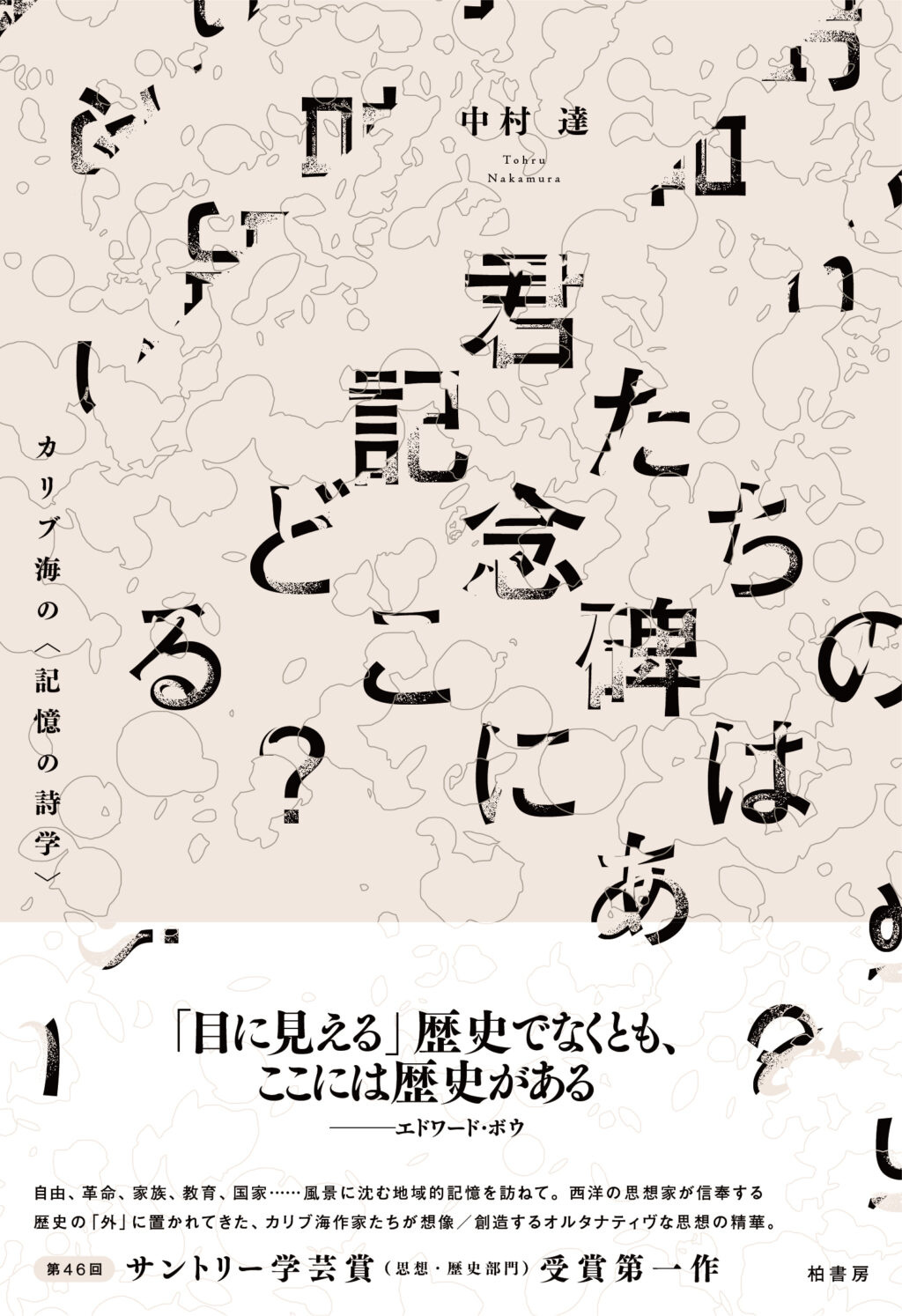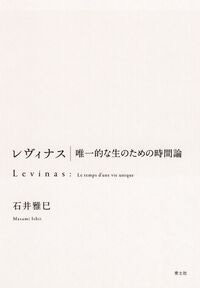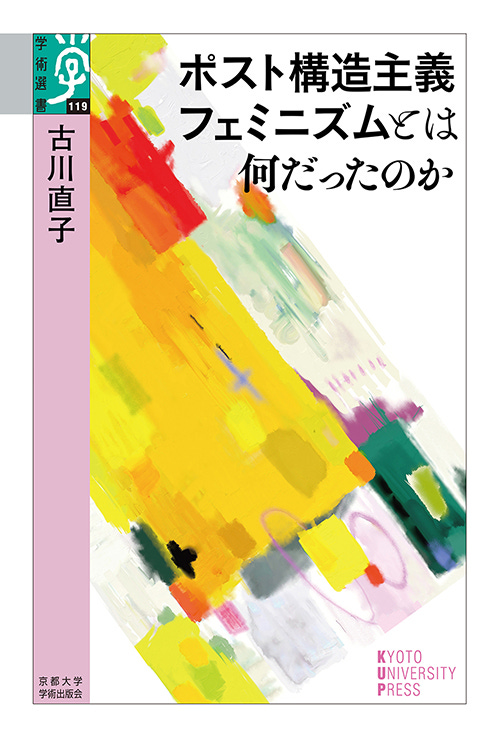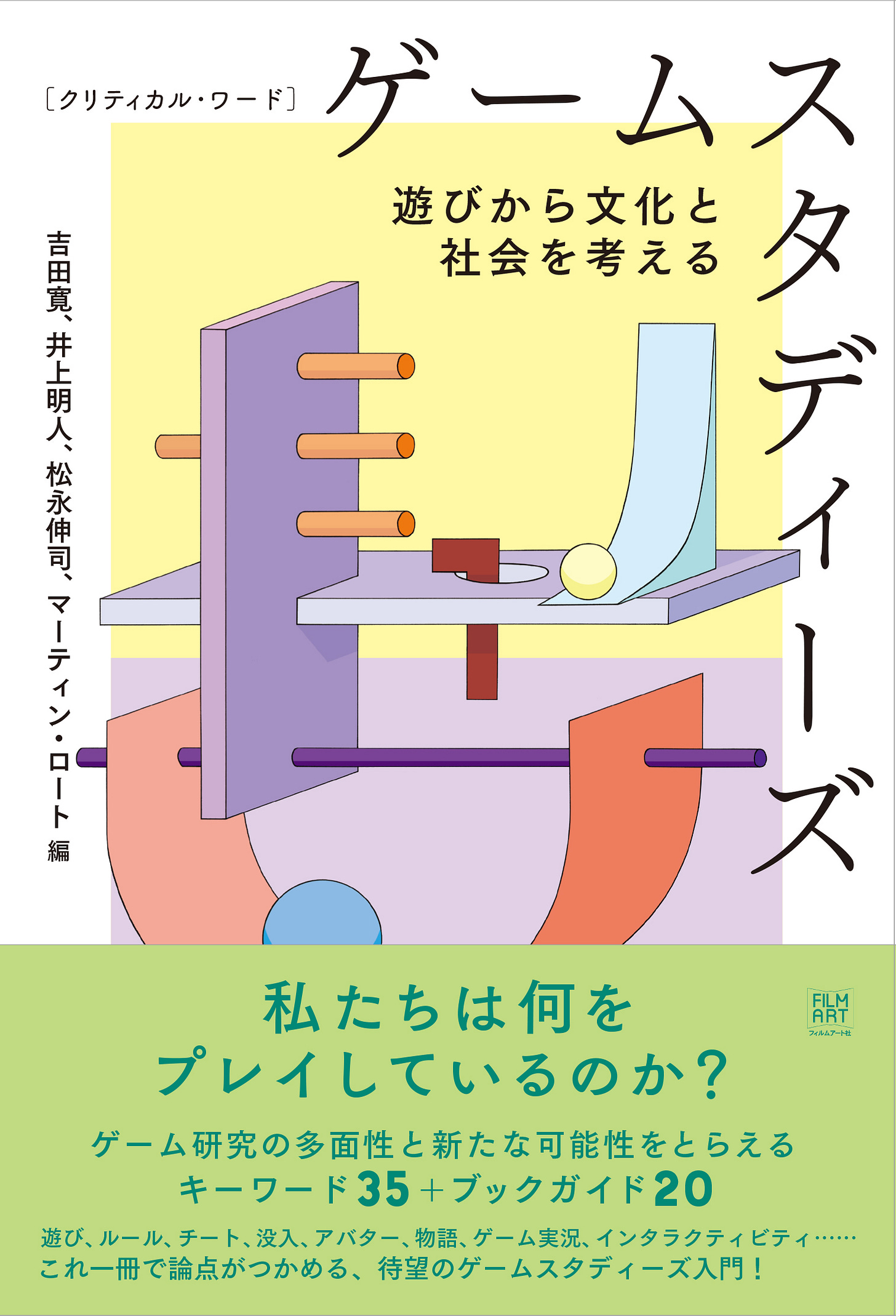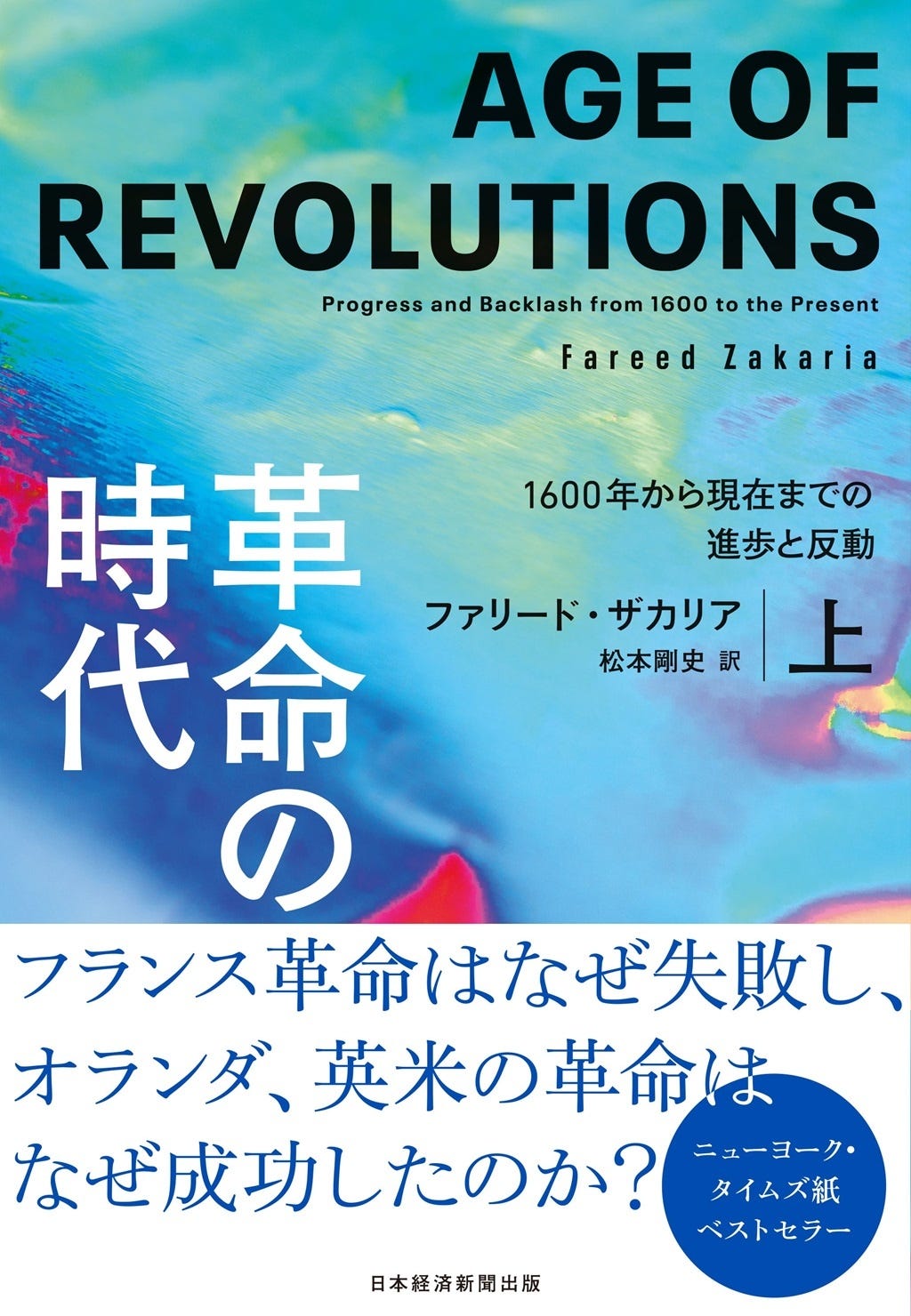【2025年6月刊】新しいリベラル、ポスト構造主義フェミニズム、アメリカの新右翼……デサイロが注目したい人文・社会科学の新刊16冊
「いま私たちはどんな時代を生きているのか」──人文・社会科学領域の研究者とともにこの問いを探り、研究のなかで立ち現れるアイデアや概念の社会化を目指すアカデミックインキュベーター「デサイロ(De-Silo)」。
2025年6月に刊行の人文・社会科学領域の新刊書の中から、デサイロとして注目したい16冊をピックアップしました。
気になるタイトルがあれば、読書リストにぜひ加えてみてください。
1.だれが戦争の後片付けをするのか——戦争後の法と正義
概要(版元ウェブサイトより引用)
「その後」の法へ
ICCの働き、捕虜の交換、被害者への賠償――。新進の法学者による「終戦後」論。
「本書では、研究の過程で戦争犯罪の悲しみに浸った私が感じた、一瞬の安らぎと希望を共有するために、「戦争の後片付け」の発展と未来について、できるだけ実際の事例を紹介しながら記述したいと思います。」
戦争にかかわる法は、人類の歴史のなかで着実につくられてきた。21世紀に入り、「戦争後の法(ユス・ポスト・ベルム)」と呼ばれる概念が注目されている。本書では、ロシア・ウクライナ戦争をおもな例にとりながら、 戦争犯罪の捜査・裁判、兵士の帰還、被害者への賠償といった戦後処理の実践を紹介する。類のない、「終戦後」論である。
著者
越智 萌(著)
立命館大学大学院国際関係研究科准教授。専門は国際刑事司法(国際法、国際機構論、平和紛争論)。「変革的正義」と題する学際的なプロジェクトを運営する。著作に、『国際刑事手続法の体系』『国際刑事手続法の原理』(ともに信山社)、共著に『ウクライナ戦争犯罪裁判』(信山社)などがある。2025年、「国際刑事手続法の研究」の業績で文部科学大臣表彰若手科学者賞受賞。
発売日
2025/6/11
版元
筑摩書房
2.新しいリベラル——大規模調査から見えてきた「隠れた多数派」
概要(版元ウェブサイトより引用)
「新しい」政治が始まる!?
実は日本には「新しいリベラル」と言いうる人々が存在することが、7000人を対象とする社会調査から浮かび上がってきた。
この人たちが求めるのは、私たちの「成長」をサポートする政治だ。
「新しいリベラル」は最多数派を占めるのに、これまで見落とされてきたのはなぜか? 「従来型リベラル」や保守層など他の社会集団と比較しながら、「新しいリベラル」が日本政治に与えるインパクトと可能性を示す。
「新しいリベラル」の実像と可能性を明らかにした、初めての書!
著者
橋本 努(著)
1967年、東京都に生まれる。横浜国立大学経済学部卒業。東京大学大学院総合文化研究科課程単位取得退学。博士(学術)。現在、北海道大学大学院経済学研究科教授。シノドス国際社会動向研究所所長。専攻は社会経済学、社会哲学。主な著書に、『自由原理――来るべき福祉国家の理念』(岩波書店)、『解読 ウェーバー『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』『経済倫理=あなたは、なに主義?』(ともに、講談社選書メチエ)、『自由の論法 ポパー・ミーゼス・ハイエク』(創文社)、『帝国の条件 自由を育む秩序の原理』(弘文堂)、『自由に生きるとはどういうことか 戦後日本社会論』『学問の技法』(ともに、ちくま新書)、『消費ミニマリズムの倫理と脱資本主義の精神』(筑摩選書)など多数。
発売日
2025/6/11
版元
筑摩書房
3.ラバーソウルの弾み方
概要(版元ウェブサイトより引用)
1960年代のカウンターカルチャーが清教徒革命、産業革命に匹敵する巨大な「精神の変容」を伴ったことを活写した記念碑的著作を全面改稿。2020年代まで射程を広げ、後期資本主義のエートスを描き直す。
著者
佐藤 良明(著)
1950年山梨県生まれ,群馬県育ち.東京外国語大学助教授,東京大学教授,NHK英会話講師,日本ポピュラー音楽学会会長,表象文化論学会会長,放送大学教授などを歴任.本書(旧版)以来,ポピュラー音楽を軸とした思索,執筆,教育を続ける.単著に『ビートルズとは何だったのか』『ニッポンのうたはどう変わったか』『ビートルズ de 英文法』『英文法を哲学する』など.共著・共編に『佐藤君と柴田君』『ロックピープル101』など.訳書にトマス・ピンチョン『重力の虹』『ヴァインランド』,ボブ・ディラン『The Lyrics 1961‒1973』『The Lyrics 1974‒2012』『ソングの哲学』,グレゴリー・ベイトソン『精神と自然』『精神の生態学へ』など.
発売日
2025/6/13
版元
岩波書店
4.テクノ専制とコモンへの道 民主主義の未来をひらく多元技術PLURALITYとは?
概要(版元ウェブサイトより引用)
世界は支配する側とされる側に分かれつつある。その武器はインターネットとAIだ。シリコンバレーはAIによる大失業の恐怖を煽り、ベーシックインカムを救済策と称するが背後に支配拡大の意図が潜む。人は専制的ディストピアを受け入れるしかないのか?
しかし、オードリー・タンやE・グレン・ワイルらが提唱する多元技術PLURALITY(プルラリティ)とそこから導き出されるデジタル民主主義は、市民が協働してコモンを築く未来を選ぶための希望かもしれない。
人間の労働には今も確かな価値がある。あなたは無価値ではない。
テクノロジーによる支配ではなく、健全な懐疑心を保ち、多元性にひらかれた社会への道を示す。
著者
李舜志(著)
1990年、神戸市生まれ。法政大学社会学部准教授。東京大学大学院教育学研究科博士課程修了。博士(教育学)。日本学術振興会特別研究員、コロンビア大学客員研究員などを経て現職。著作に『ベルナール・スティグレールの哲学 人新世の技術論』(法政大学出版局)。
発売日
2025/6/17
版元
集英社新書
5.赤ちゃんは世界をどう学んでいくのか ヒトに備わる驚くべき能力
概要(版元ウェブサイトより引用)
赤ちゃんは生まれながらに利他的である。自分の取り分が減っても他人に大事なものを分け与えるし、他者を助けることが好き。正義の味方を好み、悪者には処罰感情を持つ。生後半年で計算もできる。そして赤ちゃんはいつも、いつでも、学びたい。効率的に学ぶことができそうな相手を選んで瞬く間に自分のものにする学習能力は、最先端AIの能力をはるかに凌ぐ。これらはすべて最先端の心理学研究が明かした、ヒトが生まれながらに持つ――そして成長に伴って失われることの多い――驚きの能力である。赤ちゃんを研究することは、人間の本質的な能力を探ること。世界各国で大規模な研究が行われ、NTTが最先端の情報技術の研究所の中に「赤ちゃん研究チーム」を置いているのは、赤ちゃん学が未来の技術開発につながる研究であるからだ。これは、気鋭の赤ちゃん研究者で二児の母でもある著者が、最先端科学と自身の子育て経験を通じて人間の本質を問い、希望の未来を描く本である。
著者
奥村 優子(著)
NTTコミュニケーション科学基礎研究所 主任研究員
発売日
2025/6/18
版元
光文社新書
6.ライフスタイル移住の社会学――日本から韓国への生活転換の実証研究
概要(版元ウェブサイトより引用)
日本から韓国へと移住した人々のライフストーリーをふまえ、動機や生活実態、日本出身者コミュニティの特徴、移住を促した歴史的背景を多角的に分析。日韓を地続きのように捉え、機会や都合に応じていつでも「行き来(ワッタカッタ)」する新しい生き方にも着目。
著者
今里基(著)
1989年福岡市生まれ
福岡大学法学部卒業後、東西大学校(韓国)大学院日本地域研究科修士課程修了
立命館大学大学院先端総合学術研究科一貫制博士課程修了
博士(学術)
大阪公立大学ほか非常勤講師、2025年より立命館大学衣笠総合研究機構専門研究員
〔主な論文〕
「『帰属するエスニシティを徹底化しない戦術』の考察――日本在住韓国系ニューカマー第二世代の事例から」『立命館人間科学研究』38号、15-29頁、2019年
「ライフスタイル移住の限界――日本へ戻る日本出身者たち」『인문사회과학연구(人文社会科学研究)』24巻1号、497-522頁、2023年
「在韓日本出身者の韓流前の韓国生活――ノンフィクション作品を中心に」『多民族社会における宗教と文化:共同研究』26号、19-27頁、2023年
発売日
2025/6/19
版元
明石書店
7.人はなぜ結婚するのか-性愛・親子の変遷からパートナーシップまで
概要(版元ウェブサイトより引用)
離婚・再婚、選択的夫婦別姓、共同親権、同性婚、パートナーシップ制度、事実婚、生殖補助医療、養子縁組……。いま結婚のあり方が大きく揺らいでいる。リベラル派と保守派に分断され、個々の論点で議論がすれ違うなか、本書では共同性、性愛関係、親子関係の3点で結婚制度の歴史的変遷を根源から整理する。自由化した結婚が抱える「しんどさ」とは何か? 現行制度の本質と、今後のゆくえを展望するための羅針盤。
著者
筒井 淳也(著)
社会学者。計量社会学、家族社会学。 一橋大学大学院社会学研究科博士課程後期課程。博士(社会学)。 立命館大学産業社会学部教授。
発売日
2025/6/20
版元
中央公論新書
8.君たちの記念碑はどこにある?カリブ海の<記憶の詩学>
概要(版元ウェブサイトより引用)
西洋の思想家が信奉する歴史の「外」に置かれてきた、カリブ海作家たちが想像/創造するオルタナティヴな思想の精華。
著者
中村 達(著)
1987年生まれ。専門は英語圏を中心としたカリブ海文学・思想。西インド諸島大学モナキャンパス英文学科の博士課程に日本人として初めて在籍し、2020年PhD with High Commendation(Literatures in English)を取得。現在、千葉工業大学准教授。主な論文に、“The Interplay of Political and Existential Freedom in Earl Lovelace’s The Dragon Can’t Dance”(Journal of West Indian Literature, 2015)、“Peasant Sensibility and the Structures of Feeling of ‘My People’ in George Lamming’s In the Castle of My Skin”(Small Axe, 2023)など。日本語の著書に『私が諸島である――カリブ海思想入門』(書肆侃侃房、2023)。2024年11月、同書で第46回サントリー学芸賞(思想・歴史部門)を受賞。
発売日
2025/6/24
版元
柏書房
9.となりの陰謀論
概要(版元ウェブサイトより引用)
トランプは「闇の政府」と戦っている!?
オバマもバイデンもすでに処刑された!?
陰謀論はどこで生まれるのか。
そして、なぜ信じてしまうのか。
現代世界を蝕む病の正体を、気鋭のメディア研究者が明かす!
「陰謀論を生み出し増殖させるのは、人間の中にある「この世界をシンプルに把握したい」という欲望と、何か大事なものが「奪われる」という感覚です。これらの欲望や感覚は一部特定の人間だけが持つというよりは、社会状況に応じて誰の中にも芽生えてくるものだからです。
本書を通じて、陰謀論が誰にでも関わりのある身近な問題であり、それゆえ現代社会の抱える根源的な諸課題と深いところでつながっていることへと思いを馳せてもらえるのであれば、筆者としては望外の喜びです。
陰謀論は非常識な「彼ら/彼女ら」の問題ではなく、現代を生きる「われわれ」自身の問題であることに気づくことが、「陰謀論が支配する社会」という最悪のシナリオを回避するための肝心な一歩だと思います。」 ――「はじめに」より
著者
鳥谷 昌幸 達(著)
一九七四年生まれ。慶應義塾大学法学部政治学科教授。慶應義塾大学大学院法学研究科後期博士課程単位取得退学。博士(法学)。主な著書に 『シンボル化の政治学――政治コミュニケーション研究の構成主義的展開』(新曜社、二〇二二年)、『ソーシャルメディア時代の「大衆社会」論――「マス」概念の再検討』(共著、ミネルヴァ書房、二〇二四年)、訳書に『陰謀論はなぜ生まれるのか――Qアノンとソーシャルメディア』(共訳、慶應義塾大学出版会、二〇二四年)
発売日
2025/6/24
版元
講談社現代新書
10. レヴィナス 唯一的な生のための時間論
概要(版元ウェブサイトより引用)
「時間」を鍵にその思考の展開をたどる清新な試み
「私の主要な研究テーマは、時間の観念の脱形式化です」——晩年のレヴィナスの発言を手がかりに、具体的な生のなかに息づく時間を捉え、〈私〉や〈他者〉の唯一性を擁護しつづけた哲学者の特異な思考を鮮やかに描き切る。新鋭による意欲作。
著者
石井 雅巳(著)
1990年、神奈川県横浜市生まれ。慶應義塾大学大学院文学研究科後期博士課程単位取得退学。博士(哲学)。現在、山口大学教育学部講師。専門は西洋現代哲学と近代日本哲学史。2021年に論文「レヴィナスにおける反−歴史論の展開と変遷」(『倫理学年報』第70集)で日本倫理学会和辻賞(論文部門)を受賞。著書に『西周と「哲学」の誕生』(堀之内出版、2019年)、『レヴィナス読本』(共編著、法政大学出版局、2022年)、訳書にグレアム・ハーマン『四方対象――オブジェクト指向存在論入門』(共訳、人文書院、2017年)など。
発売日
2025/6/25
版元
青土社
11.ポスト構造主義フェミニズムとは何だったのか
概要(版元ウェブサイトより引用)
性的マイノリティやフェミニズムというテーマについて、近年かつてないほど急速に社会的な関心が高まりつつある。その一方で、ポスト構造主義フェミニズムの台頭によって、社会的な性別であるジェンダーのみならず、生物学的な事実としてのセックスもまた社会的構築物でしかないという見方が出現している。本書はこれらの見解を批判的に考察し、その問題点を明らかにすることよって、セックス/ジェンダーの概念的枠組みを刷新することを目指す。
著者
古川 直子(著)
長崎総合科学大学共通教育部門講師
京都大学大学院文学研究科博士課程研究指導認定退学。京都大学博士(文学)。
専門はジェンダー/セクシュアリティ理論、S・フロイト研究。
主な論文
「精神分析における抑圧概念の再検討―NichtwollenとNichtkönnenの問題系」『ドイツ研究』59、日本ドイツ学会(2025)、「S・フロイトの精神分析における外傷理論の再検討」『ソシオロジ』68(3)、社会学研究会(2024)など。
発売日
2025/6/25
版元
京都大学学術出版会
12.アメリカの新右翼:トランプを生み出した思想家たち
概要(版元ウェブサイトより引用)
アメリカを乗っ取った「危険な思想」の正体を明かす!
トランプ政権による国家改造の成否に関わらず、リベラル・デモクラシーへの不信感は決定的なものとなっている。左右両極の間で起きた思想戦争の内幕を追いながら、テック右派から宗教保守、ネオナチなどの思想家たちが、なぜリベラルな価値観を批判し、社会をどのように作り変えようとしているのか、冷静な筆致で読み解く。
著者
井上 弘貴(著)
1973年、東京都生まれ。早稲田大学大学院政治学研究科博士後期課程満期退学。博士(政治学)。早稲田大学政治経済学術院助教、テネシー大学歴史学部訪問研究員などを経て、神戸大学大学院国際文化学研究科教授。専門は政治理論、公共政策論、アメリカ政治思想史。著書に『ジョン・デューイとアメリカの責任』(木鐸社)、『アメリカ保守主義の思想史』(青土社)、訳書に『市民的不服従』(共訳、人文書院)など。
発売日
2025/6/26
版元
新潮社
13. ネオリベラル・フェミニズムの誕生
概要(版元ウェブサイトより引用)
「働く母になり、バランスよく幸せに生きろ」
20代ではキャリアを、30代では育児を。すべてが女性の肩にのしかかる「自己責任化」を促す、新自由主義的なフェミニズムの出現とは? 果たしてそれはフェミニズムと呼べるのか? Facebook(現Meta)の元COOシェリル・サンドバーグやイヴァンカ・トランプらのエッセイ、マミー・ブログやドラマ等を分析し、若い女性たちに示される「幸せな」人生の選択肢とその隘路を問う。アメリカ・フェミニズムのいまを映し出す待望の邦訳。
「教育があり階級上昇を志向する女性を総称的な人的資本へと完全に変換してしまうことに対して、ネオリベラル・フェミニズムはある種の対抗として機能していると理解されねばらない(…)。ネオリベラル・フェミニズムは、逆説的に、また直感に反するかたちで生殖=再生産を「上昇志向の」女性たちの規範的な人生の道筋の一部として保持し、バランスをその規範的な枠組みかつ究極の理念とすることによって、ネオリベラリズムを構成する本質的な矛盾の一つを解消する手助けをする。」(本文より)
【原著】 Catherine Rottenberg, The Rise of Neoliberal Feminism, Oxford University Press 2018.
著者
キャサリン ロッテンバーグ(著)
ロンドン大学ゴールドスミス校教授。専門はメディア、コミュニケーション、カルチュラル・スタディーズ。著書にPerforming Americanness: Race, Class, and Gender in Modern African-American and Jewish-American Literature (Dartmouth College, 2008), Black Harlem and the Jewish Lower East Side: Narratives Out of Time (State Univ of New York Pr, 2013)。共著にThe Care Manifesto: The Politics of Interdependence(『ケア宣言──相互依存の政治へ』大月書店、2021 年)
河野 真太郎(訳)
1974 年、山口県生まれ。専門は英文学、イギリスの文化と社会。専修大学国際コミュニケーション学部教授。著書に『新しい声を聞くぼくたち』(講談社、2022 年)、『この自由な世界と私たちの帰る場所』(青土社、2023 年)、『増補 戦う姫、働く少女』(ちくま文庫、2023 年)、『ぼっちのままで居場所を見つける──孤独許容社会へ』(ちくまプリマー新書、2024 年)など多数。訳書にトニー・ジャット『真実が揺らぐ時──ベルリンの壁崩壊から9.11 まで』(共訳、慶應義塾大学出版会、2019 年)、『暗い世界──ウェールズ短編集』(共訳、堀之内出版、2020 年)、ウェンディ・ブラウン『新自由主義の廃墟で──真実の終わりと民主主義の未来』(人文書院、2022 年)、アンジェラ・マクロビー『フェミニズムとレジリエンスの政治──ジェンダー、メディア、そして福祉の終焉』(共訳、青土社、2022 年)など。
発売日
2025/6/26
版元
人文書院
14.クリティカル・ワード ゲームスタディーズ 遊びから文化と社会を考える
概要(版元ウェブサイトより引用)
私たちは何をプレイしているのか?
ゲーム研究の多面性と新たな可能性をとらえる、キーワード35+ブックガイド20
遊び、ルール、チート、没入、アバター、物語、ゲーム実況、インタラクティビティ……
押さえておきたい理論から、ゲーム文化が理解できる幅広いキーワード、さらに深く学ぶための重要文献まで。
これ一冊で論点がつかめる、待望のゲームスタディーズ入門!
「ゲームと遊びを研究する総合的な学問分野」として生まれたゲームスタディーズは、今大きな注目を集める、まさに21世紀の学問分野と言えるでしょう。
本書は、さまざまな領域を巻き込み活況を呈するゲームスタディーズを学ぶうえで、知っておきたい基礎知識と重要な論点を、多様な視点とアプローチでわかりやすくコンパクトに解説した、本邦初・待望のゲームスタディーズの入門書です。
[遊び][ルール][インタラクティビティ]などの基礎概念、[チート][没入][アバター][物語]などのゲーム文化を形成するキーワード、ヨハン・ホイジンガからイェスパー・ユールまでゲーム研究の必読文献ガイドをバランス良くマッピングし、幅広い射程がありながらポイントを絞り込んだ、ありそうでなかった構成が本書の大きな特徴です。
ゲームとは何か、なぜゲームは面白いのか、私たちはいったい何を遊んでいるのか。
哲学や人類学、心理学、社会学、メディア研究、音楽学といったさまざまな領域を巻き込みながら展開してきたゲームスタディーズの、これまでの蓄積とこれからの可能性を概観できる本書は、ゲームを学びたい人だけでなく、ゲームをもっと楽しみたい人、語りたい人にとっても役に立つ、“最初に読むべき”一冊です。
本書という地図を片手に、ゲームスタディーズの世界へ、第一歩を踏み出してみましょう。
著者
・編著
吉田寛/井上明人/松永伸司/マーティン・ロート
・著者
池山草馬/井出草平/今井晋/武澤威/岡本健/尾鼻崇/木村知宏/倉根啓/小林信重/近藤銀河/西條玲奈/髙橋志行/髙松美紀/竹本竜都/田中治久/谷川嘉浩/根岸貴哉/福田一史/藤田直哉/藤本徹/ムン・ゼヒ/山口浩/楊思予
発売日
2025/6/26
版元
フィルムアート社
15.ネオ・ユーラシア主義: 「混迷の大国」ロシアの思想
概要(版元ウェブサイトより引用)
ウクライナ侵攻におけるプーチン・ロシアの思想的根拠として注目を集めた「ネオ・ユーラシア主義」。その見立ては正しいのか。大国の戸惑いを反映する思想の実相を、第一人者が解き明かす。
著者
浜 由樹子(著)
東京都立大学法学部教授。博士(国際関係学)。専門は国際政治学、ロシア地域研究。著書に『ユーラシア主義とは何か』、訳書にマルレーヌ・ラリュエル『ファシズムとロシア』など。
発売日
2025/6/27
版元
河出書房新社
16.革命の時代(上) 1600年から現在までの進歩と反動
概要(版元ウェブサイトより引用)
フランス革命はなぜ失敗し、
オランダ、英米の命はなぜ成功したのか?
著名コラムニストが歴史上の革命を振り返り、まさに「革命の時代」であるいまを歴史から照らし出す。
ニューヨーク・タイムズ紙ベストセラー。
現代は「革命の時代」である。世界中で劇的かつ急進的な変化が起きている。
* * *
台頭する中国と挑戦的なロシアによって、安定していた国際システムが急変しつつある。各国では古い政治秩序がひっくり返され、伝統的な右派と左派の境目を超えた新しい政治運動が発生している。トランプは自由市場と自由貿易を覆し、デジタル革命やAIといった新テクノロジーは人々のアイデンティティを揺るがしている。いま社会と経済、そして人々は、海図なき航海を余儀なくされている。 * * *
何が「革命の時代」をつくりだすのか? 「革命の時代」はどういう終わりを迎え、どのような結果を生み出すのか? 著名コラムニストである著者は、現代世界を形づくった3つの革命を振り返り、フランス、ロシア、中国の革命のように「血塗られた革命」にしないための重大な要素を浮き彫りにする。
* * *
「トランプ革命」が進むいまこそ読むべき書。
著者
ファリード・ザカリア(著)
イェール大学卒業、ハーバード大学政治学博士。フォーリン・アフェアーズ誌のマネージング・エディターを経て、現在、国際情勢を扱うCNNの主力番組「ファリード・ザカリアGPS」の司会者、ワシントン・ポスト紙のコラムニストとしてコラムを毎週連載。前作『パンデミック後の世界』を含む4冊のニューヨーク・タイムズ紙ベストセラーの著者。ニューヨーク在住
松本 剛史(訳)
1959年和歌山県生まれ。翻訳家。東京大学文学部社会学科卒。ダイヤー『米中 世紀の競争』(日本経済新聞出版社)、ヒューズ『対テロ戦争株式会社』(河出書房新社)、メンジーズ『1421』(ヴィレッジブックス)、ブース『暗闇の蝶』(新潮文庫)など訳書多数。
発売日
2025/6/30
版元
日本経済新聞出版
デサイロでは、ニュースレターやTwitter、Instagramなどを利用して、プロジェクトに関わる情報を継続的に発信中。Discordを用いて研究者の方々が集うコミュニティも運営しています。ご興味のある方はニュースレターの登録や各SNSのフォロー、あるいはDiscordにぜひご参加ください。
■Discord:https://discord.gg/ebvYmtcm5P
■Twitter:https://twitter.com/desilo_jp
■Instagram:https://www.instagram.com/desilo_jp/
■バックナンバー: